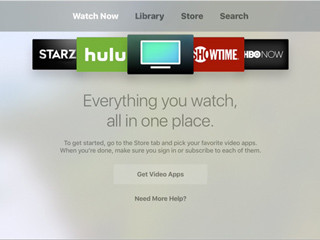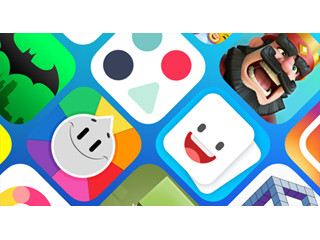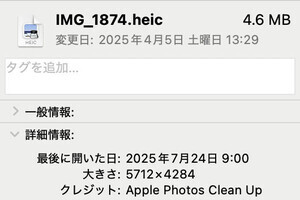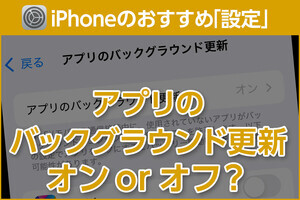繰り返しになるが、筆者がデジタルの辞書で大きなメリットの一つとして感じているは、履歴の情報だ。自分の検索履歴を振り返ると、何を知りたかったのか、そしてそれを覚えているか(定着したか)、といったことを思い出せる。
辞書を読む、Wikipediaを読むことが新たな知識を得る広義の「学習」と位置づけられるのであれば、その履歴は学習履歴であり、振り返りを与えることで、より学習の体験を高めることができる。あるいは、こうしたカジュアルな検索が学習として位置づけられるような「仕組み」が作られることは、今後重要になるのではないか、と思う。
このテーマについて考える際に、常々話題にしているのは、知識のアップデートについてだ。デジタル教科書は、教科書がデジタル化されることにフォーカスが当たっているが、重要なのは、自由な学習を妨げないことに加えて、何を学んだか、学んだ知識がどう変化したか、という点を記録し、追いかけ続けることができるようにする点だ。
例えば最近、トランプ大統領はNAFTAについて見直す、と発言した。NAFTAは、北米自由貿易協定の略で、米国、カナダ、メキシコで締結されている。これは小学校の社会科で習って以来、自分の頭の中でも放置されてきた知識だ。しかし、その体制が崩れるかもしれないという。米国に関連する経済ニュースは比較的大きく扱われやすいため、自分の知識の行く末がどうなるかを注視できる。保護主義的に動く米国の動向は、次のiPhoneのデザインがどうなるか以上に、個人的な興味でもある。
しかし、自分が持っている全ての知識の動向全てを毎日チェックすることはできない。
学んだことの全てが、なんらかの更新を受けたら、新着メッセージが届くみたいに通知が来たら良いのに、と思う。ただそのためには、自分の知識や触れた情報がスマートフォンやクラウドの中に全て蓄積されていなければならないし、体験を含めて適切に言語化され、デジタル化されていなければならないだろう。
これを叶えるプラットホームは今のところない。人の学びを変えるチャンスではないか、と思っているのだが……。

|
松村太郎(まつむらたろう)
1980年生まれ・米国カリフォルニア州バークレー在住のジャーナリスト・著者。慶應義塾大学政策・メディア研究科修士課程修了。慶應義塾大学SFC研究所上席所員(訪問)、キャスタリア株式会社取締役研究責任者、ビジネス・ブレークスルー大学講師。近著に「LinkedInスタートブック」(日経BP刊)、「スマートフォン新時代」(NTT出版刊)、「ソーシャルラーニング入門」(日経BP刊)など。ウェブサイトはこちら / Twitter @taromatsumura