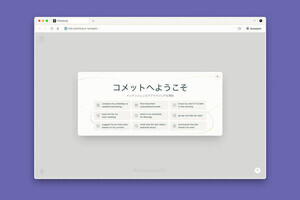Wendy'sがダイナミックプライシングを導入する計画を発表し、ネット上で強い非難を浴びた。インフレに疲弊している消費者は需要を利用した値上げを警戒している。しかし、「価格変動=値上げ」ではない。すでに導入した中小規模の飲食店で、収益を最大化しながら顧客体験も向上させている例が見られる。→過去の「シリコンバレー101」の回はこちらを参照。
Wendy‘sが「変動価格制」を導入
レストランのメニューに「時価」の2文字を発見した時、どのような印象を抱くか。「時価=高い」ではない。素材が潤沢に供給されている時など、通常よりお値打ちになる可能性もある。しかし、価格が伏せられていて、不当な値段を押し付けられそうな不安の方が膨らんでしまう。
ハンバーガーチェーンのWendy‘sが直近の決算説明会で、2025年末までに2000万ドルを投資して米国内のレストランにデジタルメニューボードを展開し、価格を動的に変化させる「ダイナミックプライシング(Dynamic pricing:変動価格制)」を導入する計画を明らかにした。それに対し、失望や怒りをあらわにする消費者の声がネット上で広がり、Wendy‘sは対応に追われることになった。
ダイナミックプライシングは、需要や市場状況の変化に応じて価格をリアルタイムで調整する。ピーク時には価格を引き上げ、逆にオフピーク時に価格を引き下げることで、ピーク時間帯の混雑を減らし、より節約したいという顧客の要望にも応えられる。
価格は上昇すれば、下落もする。ダイナミックプライシングはすでに、航空券、ホテル、オンラインショップなどで一般的に受け入れられており、その仕組みを消費者も理解しているはずである。
しかし、Wendy'sの計画に対して、需要を利用した値上げ、いわゆる「サージプライシング(Surge pricing)」になると警戒する見方が大半だった。そうした反応を受けて、CEOのカーク・タナー氏がさまざまなメディアのインタビューを通じて「需要が高い時に価格引き上げを行う意図はない」と説明したが、実際にダイナミックプライシングが始まっていないこともあり、懐疑的な反応は収まっていない。
長引くインフレで消費者は値上げに嫌気が差しており、簡単に値段を書き換えられるデジタルメニューボードを今導入するリスクは大きい。飲食店にとって顧客の拒絶は利用者離れを意味する。
中規模チェーンで広がるダイナミックプライシング
だが、一方で今、独立系または中規模チェーンの飲食店、食料品店、小売業者の間でダイナミックプライシングを試みる動きが拡大しているのだ。例えば、サンディエゴにある"スローフードのファストフード"「Cali BBQ」は、オンラインオーダーのプルドポーク・サンドウィッチに価格変動を導入し、12ドル〜18ドルの変動でデリバリーの売り上げを5%伸ばすことができ、他のメニューにも価格変動を拡大し始めた。
新型コロナによる行動制限が解除され、飲食店は本格的な営業を再開できたものの、インフレで原材料費が値上がりし、さらに人手不足で人件費も上昇している。飲食店が新たな困難に直面する中、Tock、Uber Eatsといった飲食店向けのプラットフォームが価格変動の活用を提案し、Juicerのようなオンライン注文価格を自動調整するサービスも登場している。
オンライン活用でコロナ禍を生き抜き、テクノロジーを利用する価値に気づいたビジネスが、今あるリソースで収益を最大限化するためのテクノロジー活用に目を向け始めている。その1つがダイナミックプライシングである。
価格変動は、売り上げを伸ばすだけではない。その日の売れ行きが鈍いメニュー、期限切れが近い材料を使っているメニューの価格を下げて在庫管理に役立てたり、天候が悪い日はデリバリーに力を入れるなど、コスト削減や効率性の向上も実現できる。
McKinseyが2021年に公開した「The dos and don'ts of dynamic pricing in retail」の中で、オンラインで買えるもの、オンラインで注文できるものが増えるに従って価格設定が重要な競争ツールになり、「特にダイナミック・プライシングは、これからの小売業界において、勝者を際立たせる中核的な能力の1つになる」と予測している。それには飲食産業も含まれる。
なぜWendy'sは強烈な反発を浴びたのか
では、なぜWendy'sは強烈な反発を浴びてしまったのか。ダイナミックプライシングには、収益を最大化しながら顧客体験も向上させられる大きな可能性があるが、これまで一部の産業でしか利用されてこなかった理由もあり、他の産業が導入する際に注意すべき落とし穴がある。そこにWendy'sはハマってしまっている。
消費者は航空運賃が絶えず変化することを期待する一方で、ハンバーガーやシャンプーのボトルの価格にはある程度の一定性を求める。そうした商品には、たとえ需給データが許容しても、消費者が意識的に許容できない常識的な範囲がある。それを超えた値上げや頻繁な価格変更は、消費者を混乱させ拒絶を生む。
また、「価格が変わり続ける=価格がわからない」という消費者の不安を払拭するのが重要であり、デバイスやチャネル(オンライン、オフライン)を問わず、わかりやすく一貫した価格を示す必要がある。そして、価格変動においてビジネスは、価格が下げたことを伝えるのに消極的になりがちだが、価格が下がることを宣伝しないと価格変動は効果を発揮しない。
Juicerは米国で数十のレストランに採用されており、それらの価格変動の平均は約15%である。いずれのレストランでも顧客離れは起きていないそうだ。共同創業者のドリュー・パターソン氏は、レストランが顧客に価格変動に順応してもらうためには、価格が上がり下がりすることを明確に説明し、ハッピーアワーのような身近な例を示すなど、顧客が得することを思い出してもらう必要があると述べている。
-

厨房のキャパシティを最大化する設備とレイアウト、セルフオーダー・キオスク/オーダー・ピックアップ棚/モバイル・オーダー・ピックアップ専用駐車場などデジタルファーストの設計、デリバリーへの最適化を取り入れたWendy'sの「Global Next Genレストラン」
Wendy‘sは、価格変動だけではなく、時間帯によって異なるサービスやメニュー、天候や様々な要因に基づいたメニュー提案など、AI分析を活用する取り組みにデジタルメニューボードが不可欠と考えている。
消費者を魅了できそうなさまざまなアイデアを持っているのだが、そのビジョンの示し方を誤ってしまった。しかし、実際には、全米レストラン協会が成人1000人を対象に行ったオンライン調査では、レストランが営業状況に応じて価格を上げ下げする変動価格制を61%が支持している。若い層ほど支持率は高く、数年後には閑散している時に値段が下がらないメニューが嫌われることになるかもしれないのだ。