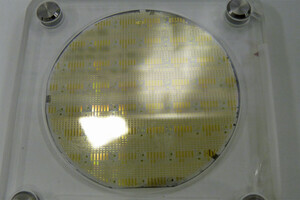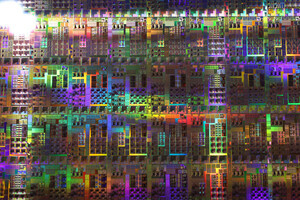「規格外野菜」と聞いて皆さんが思い浮かべるのはどんな野菜だろうか。大きすぎる、長すぎる、虫食いがあるなど、スーパーマーケットで目にする統一感のある野菜とは異なる野菜ではないだろうか。→過去の回はこちらを参照。
「規格外と一口に言っても産地によって独自の基準がありますが、例えばブロッコリーは上から見て真ん丸ではなく、かつ直径15cmを超えていたら、ズッキーニは180gを超えていたら、小松菜のような葉物は軸が折れていたら規格外となります。規格外野菜は1農家あたり全収穫量のうち3割に達するのが一般的です」(竹下さん、以下同)
こう語るのは、社会起業家集団であるボーダレス・ジャパン傘下で規格外野菜に関する事業を行うタベモノガタリ 代表取締役の竹下友里絵さんだ。中学のころ、国際協力に関心を持ち始め、高校でのカナダ留学でフードロスを知り、大学で立ち上げた学生団体ではフードロス削減を目指し、規格外果物を販売するビジネスをスタートしている。
起業後に事業化した、規格外野菜のフードロス問題に取り組む「八百屋のタケシタ」(2021年9月に事業クローズ)を経て、現在は収穫体験「やさいハンター」をメインの事業として展開している。SDGs(持続可能な開発目標)17の目標でいうと「12.つくる責任 つかう責任」で社会をより良くしていく事業に迫る。
食べ物を捨てる人、食べられず困窮する人がいる世界で
1996年、兵庫県神戸市で生まれた竹下さん。中学時代から英語が好きで、貧困問題や国際協力に興味を持ち、高校2年次にはカナダ留学を果たす。
ホームステイ先の家庭で大量の食べ物が残され捨てられるのを連日のように見て、「食べ物を大事にしなさい」と言われて育ち、米を一粒残さずきれいに食べる習慣が身についていた竹下さんは衝撃を受ける。
日本を含む世界のどこかでたくさんの食べ物を捨てる人がいて、別のところでは食べられずに困窮している人がいる、食糧需給のアンバランスさに問題意識を持つようになっていた。
大学では国際協力を学ぶため、関西学院大学総合政策学部に進学したが、国際協力分野の中でも特に飢餓問題に関心があると気づき、食糧に特化した学びがしたいと3年次に神戸大学農学部に編入する。高校時代からあった問題意識である食の分配を深める食料境経済学で、農産物流通の仕組みや農村活性化などを学んだ。
2018年3月、インターン活動を中心にビジネスを学ぶ過程で、大学の同級生に声をかけ、フードロス削減をテーマに掲げ、加工用果物の流通事業を始めたのがタベモノガタリの原型となった。
神戸にはパン屋とケーキ屋が多く、彼らにヒアリングしたところ、規格外でもいいから地元産の果物を使いたい、しかしそれらを流通させる事業者がなく、専門商社から果物を仕入れているとの話を聞いた。
半年ほど事業を続け、ソーシャルビジネスの登竜門コンテストとして知られる「ユヌス&ユーソーシャルビジネスデザインコンテスト2018」に参加。
「ボーダレス・ジャパン賞」を受賞したのを機に事業をブラッシュアップし、在学中の2019年2月にボーダレスへ参画。タベモノガタリ株式会社を設立した。同9月に大学を卒業するまで、起業家と学生の二足の草鞋を履く生活を続けた。
事業は好調。でも、農家のためになっているのか?
そうして生まれたのが規格外野菜のフードロス問題に取り組む「八百屋のタケシタ」だ。
兵庫県で生産される野菜は地産地消率が高く、特に都市近郊農業で知られる神戸は、農家からJA→卸売市場との流通経路が一般的だ。そんな神戸の農家から食味に影響のない規格外野菜は適正価格(規格に当てはまる野菜と同一の価格)で、美味しさが落ちていて農家が処分対象として考えているものは安価で買い取り、神戸市営地下鉄の駅構内で平日に販売した。
「販売時間帯は試行錯誤しましたが、最終的には14~19時の営業としました。出店した駅は路線内で乗降客数が2番目に多く、住居メインのエリアなので帰宅時のお客さまを中心に利用していただき、新鮮で美味しい野菜を買いたい方から好評をいただいていました。朝どれを昼過ぎには売っていたので、市場に流通しているものよりフレッシュかつ美味しい自信があり、売り上げも好調に推移していたのですが……」
しかし、2020年以降のコロナ下で、公共交通機関の利用者が大幅に減少するにつれ、顧客も半減。駅構内での販売方法に暗雲が漂い始め、竹下さんは移動販売をスタートした。
2~3カ月、週6回もの移動販売をする過程で、スーパーに企画提案し、産直野菜コーナーへの出店を実現。「竹下屋」としてスペースを借りて、スーパー7店舗に販路を広げる一方、駅構内での販売は週2回に減らすなど、時世に合わせた販売の形を模索してきた。
しかし、売上拡大に向けてさらなるステップへと進み始めた2021年8月ごろ、竹下さんは事業のクローズを考え始める。このとき「この事業は農家のためになっているのか」との違和感がもたげるようになっていたという。
取引先の農家は多くが年間の手取り収入が300万円台と決して豊かではなく、農業従事者にとって人件費は最大の経費であり、人を雇い入れるのも、人を増やさずに生産量を拡大するのもハードルが高い。
そこでたどり着いたのが、農家が収穫体験を通じて副収入や固定ファンを作り、持続可能な農業を展開していく事業「やさいハンター」だった。
市場から取り残された有機農家を支援したい
「具体的な話をすると、有機農業に従事する農家の収入を年間100万円向上させることを目標にしています。収穫体験や農業体験など、“体験”を販売することで、生産者に副収入を作れないかと考えたのです」
なぜ有機農家に絞っているのかと聞くと、竹下さんは「八百屋のタケシタ事業での反省を踏まえている」と振り返り、八百屋のタケシタでは事業で支える対象を明確にできなかったと語る。
農家が100軒あれば100軒が抱える規格外野菜というテーマを問題意識として抱えていたが、農家と一口に言ってもそのあり方は多種多様だ。
農薬を用いて効率よく農業をするなら、コストを下げてJAを通して市場へ流通させる既存の方法で問題はない。規格外野菜は約3割発生するものとして、廃棄を見越して栽培すればいい。
「しかし、有機農家は取り残されています。虫食いひとつ許さない市場に出荷するとなると、生産する野菜の約7割が規格外となる彼らの野菜は、既存の販路では販売できません。肥料代や草取りなどのメンテナンスコストは高く、道の駅などに出荷しても他の野菜と比べて安さで負けてしまう。そう考えると有機農家の選択肢は少なく、彼らのために事業をしたいなと考えるようになりました。特に都市近郊で、狭い土地で効率がいいとはいえない生産をしているのが神戸の農家の特徴です。そして、その中には有機農業に従事している人もいます。消費地との近さを利点とした事業は実現可能です」
ありのままの環境と共存するような農業をしたい、アトピーの我が子の身体に悪い影響がない野菜を食べさせたいなど、有機農業を選ぶ理由は農家によって異なるが、それぞれに強い思いがある。
現時点では2組の有機農家と組んでスタートしたやさいハンターは、その名の通り野菜に限定した収穫体験だ。一度で複数の野菜を収穫できるのが売りとなる。
しかし、果物狩りと比べて野菜狩り、加えて単品の取り扱いとなると集客力の低さが懸念となる。それを乗り越えるため、竹下さんはカードを使ってゲーム形式で差別化する施策を取り入れている。
5月の大型連休中には、玉ねぎをはじめスナップエンドウやニラなど、野菜4品目の収穫体験が開催された。参加費は子ども1,500円、同伴者800円で、決済手数料は5%、農家に売上の8割が入る。集客はタベモノガタリ、運営は農家、カード(コンテンツ)制作は共同と、役割分担は明確だ。
中長期的に持続可能な農業システムを作る
やさいハンターのメインターゲットは3~10歳の子どもで、コアターゲットは5~8歳としている。「食育」か「週末レジャー」か、どちらでマーケティングするか考えた末、お出かけに困る子連れ層が浮かび、週末レジャーの文脈を選択することに。8歳を過ぎると習い事に行く子どもも増え、週末に遊びに行く先に悩む親も減るのだという。
竹下さんは、やさいハンターの事業でベースとなるSDGs目標「12.つくる責任 つかう責任」を今廃棄している規格外野菜をなくすという短期的な視点だけでなく、中長期的な視点でもとらえている。
「これまでの一般的な農業のやり方は単品・大量生産でした。ただ、約80年前にできた市場の仕組みに基づいているため、もうそろそろ限界が来ていると思います。売値が決まらない段階から生産を始め、いざ販売となると気候や需要で金額が変わるというのは、環境に左右されるばかりで非常に大変なこと。やさいハンターという収穫体験を入口にしてもらい、農家が“誰かのために野菜を作ること”が当たり前になる世界を目指しています」
竹下さんが描く未来は、収穫体験を通じてその有機農家を知った顧客が、彼らから野菜を直接購入するようになり、顔が見える関係性でやりとりが行われることだ。消費者が生産者に対して購入費用を前払いするシステム「地域支援型農業(CSA)」に近いとも竹下さんは補足する。農家は副収入を得られるだけでなく、ファンを獲得でき、長期的な視野でも事業を継続しやすくなる。
やさいハンターは全国展開を前提にビジネスを作っている。レジャーのピークである夏休みには神戸以外の地域でも展開予定だ。フードロス削減、規格外野菜への課題意識から生まれた事業は持続可能な農業実現を目指し、進化を遂げていく。