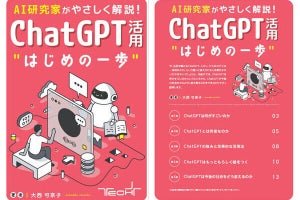前回、営業担当者(セールス)の育成を社内で行うメリットについて、具体例を交えてご説明しました。セールスイネーブルメントの重要性や期待できる効果については、お分かりいただけたのではないかと思います。
ここで、「セールスイネーブルメント組織をわざわざ作らなくても、営業部門内で育成の仕組みを考えて実践すればよいのでは」と考える人もいるかもしれません。確かに、新たに組織を立ち上げるとなるとそれなりに労力がかかります。しかし私は、それでも専任の部署を設けることをお勧めします。セールスイネーブルメントに限らず、こうした大規模で新しい取り組みは、責任の所在がいつの間にかわからなくなるということが往々にして起こり得るからです。
部署を設ける際には、組織図上はもちろん、座席も営業部門のすぐ近くにしましょう。離れてしまうと現場の状況も課題もわからず連携がとりづらくなり、セールスも育成に対して受け身になりがちです。セールスメンバーと密なコミュニケーションをとり続けられる体制をまずは目指しましょう。
自社でセールスイネーブルメント組織を立ち上げるにあたって重視すべきポイントは、以下の3つです。
- ロールモデルの設定を間違えない
- 「独立するまでサポートすること」を前提に体制を整える
- 成果として判断する「指標」を経営陣と握っておく
今回はまず、1つ目のポイントについて見ていきましょう。
「適切なロールモデル」とは?
セールスイネーブルメントにおいて大切な要素の1つは、セールスに目指してもらうゴール、つまり「ロールモデル」の設定です。結論からお伝えすると、ロールモデルには「自社で高い成果を出しており、再現性があるトップセールス」が適しています。彼・彼女の要素を抽出し、育成コンテンツに組み込むのが非常に大切です。
まず第1のポイントは「自社で高い成果を出している」こと。他社でいくら活躍していたとしても、自社で高い成果を出していない限りはロールモデルに適しません。社員たちが自然と「あの人のように、自分もすごいセールスになりたい!」と思える人物を選ぶべきです。
しかし、特定の人が長年トップを独走しているのではない限り、「自社で高い成果を出している」トップセールスはたくさんいるでしょう。そこで次に大切なのは再現性、つまり「なぜ成果を出せるかを言語化でき、習得難易度が高すぎないスキルを持っていること」です。
“まねできるトップセールス”から要素を抽出
実例をご紹介しましょう。私の所属するGA technologiesにも、長期間にわたって活躍しているトップセールスが複数います。ある人は圧倒的にコミュニケーション力が高く、どんなお客さまにも愛される不思議な才能を持っています。またある人は、業界経験も長く非常に豊富な専門知識を持っており、お客さまから絶大な信頼を得ています。しかし前者は天性の才能であり、なぜ長期間活躍できるかを本人も言語化できません。また後者は、言語化はできるものの習得するのに長い時間がかかるため、中途入社者の早期立ち上げをメインの目的としていた当社の場合、ロールモデルには適していませんでした。
そこで私がロールモデルに選んだのが、自らの商談をプロセスに分け、それぞれのフェーズで必要なコミュニケーションを考えて実行していたトップセールスです。この人は、特別コミュニケーション力が高いわけでも、論理的に隙のない説明ができるわけでもありません。しかし、常に自分の商談を客観視しており、最初から最後まで目的と意図を持ってお客さまと向き合っていました。そこで私は彼の考え方を取り入れ、お客さまとの最初の接点からご購入に至るまでの流れを3つのプロセスに分けました。次に、各プロセスごとに実施すべき重要なコミュニケーションを「キーアクション」としてチェックリストにし、トークスクリプトにも反映しました。
現在、弊社ではキーアクションをプロセスごとに15個以上設定していますが、プロセスとキーアクションは会社ごとに必要な数が変わってくるはずです。ではどのくらいの粒度でキーアクションを設定すればよいのでしょうか。
例えば、「お客さまがどこまで自社の商品に対して理解していただけたか確認する」というキーアクションがあります。これを怠ると、商品について誤解があったことが購入直前に判明したりして、顧客体験の悪化につながるのです。キーアクションをできるだけ細かく設けることで、どんな人でも一定基準の商談ができるようになりますし、一つ一つは難しい動作ではないので誰でも実践できます。
キーアクションを育成のジャーニーとすることで、育成の進捗確認も容易になります。チェックリストにするだけでなくトークスクリプトに盛り込むことで、どこでつまずいているかが一目瞭然な上、自分で練習する機会を増やすことができるので、育成のスピードも早まるでしょう。
ロールモデルに必要なのは「一貫性」と「柔軟性」
ロールモデルは顧客ニーズの変化や、扱う商品やサービスの増加に応じて見直すことをお勧めします。当社でも、ここ数年で高い成果を出しているセールス2名から要素を抽出し、既存のロールモデルに追加しました。ちなみに、この2名は2019年と2021年に入社した若手の新卒社員であり、育成の成果を感じられた嬉しい出来事でもありました。
きっかけは、現在のモデルになっているトップセールスがマネジメントに移り、実際に商談をしなくなって3年が経ったことでした。この間にオンライン商談の普及や、日本全体で投資への注目度も上がるなど、私たちを取り巻く環境は大きく変化しました。そこで「今の時代に合わせてロールモデルのアップデートが必要だ」という声が現場から上がったのです。そこで、実績を出している2名のセールスの要素を加えることになりました。
ここで大事なことは、ロールモデルをガラッと変えるのではなく、基本は変えずに要素だけ追加するということです。全てを変えてしまうと現場の上長が行う指導と合わなくなってしまい、会社としての「セールスの基準」がなくなってしまいます。会社として「この人は自社を代表するセールスパーソンだ」と言える人を最初のロールモデルとして選んでおけば、会社を取り巻く環境が多少変化しても、一部の要素を変更すれば済みます。だからこそ、最初のロールモデル選定には、十分な時間をかけることを強くお勧めします。