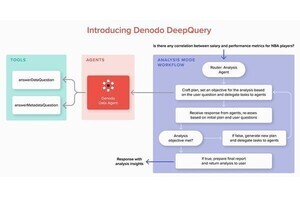24回と長期間にわたり、「システムの統合化」という観点からさまざまな事例を見てきたが、これまでは航空機や艦艇などといったプラットフォーム、あるいはそこに搭載するウェポン・システムの話が主体だった。
しかし、プラットフォームにしろウェポン・システムにしろ、それを製造したり、維持管理したりする仕事が必要になることを忘れてはならない。→連載「軍事とIT」のこれまでの回はこちらを参照。
サプライチェーン管理から整備補給まで
一つの製品を構成する部品やコンポーネントを、すべて同じメーカーが内製しているわけではない。「餅は餅屋」で、専門メーカーに委ねる形が一般的である。すると、サプライチェーン管理という課題ができる。
また、低コストかつ効率的な生産を行うためには、「どこで何をどれだけ作らせるか」だけでなく、「作ったものを、どのタイミングで運び込んで生産ラインに投入するか」も問題になる。遅れるのは問題だが、早すぎても保管場所というコストが発生する。
一方、できた製品を維持管理する場面では、寿命が来たり、故障したり、壊れたりしたパーツやコンポーネントを交換する必要がある。すると、交換用の予備を常に確保しておかなければならない。それは何もないところから湧いてくるわけではない。在庫状況を見て、適宜、発注をかけて調達しておかなければならない。
しかも、在庫している現場と、それを必要としている現場は違うのが普通だから、そこでモノの移動が発生する。モノが移動すれば在庫に関するデータが変動するから、それも正しく記録・管理しておかないと、「あると思っていたモノがない」ということが起きる。
そして、整備や交換の作業をいつ行うか、あるいは行ったか、というデータも重要である。それがなければ、例えば「所定の整備が完了して、即応できる状況にある機体が何機あるか?」という問いに答えられない。そんな調子では作戦計画も立てられない。
こうしてみると、兵站支援……というより戦務支援という用語の方が適切だが、「手持ちの資産を調達・配備・維持管理して戦闘に備える」プロセスを一元的に見られる方が好ましい。実はこの分野でも、統合的なソリューションは必要なのだ。
調達、配備・輸送、整備や維持管理といった業務が、それぞれ別個の組織の下、別個のシステムを用いて動いていたのでは、情報管理に齟齬や矛盾が生じかねないし、それを解決するために余分な人手と経費を要することにもなる。
IFSとロッキード・マーティンが組むN-MRO
そこで米海軍は2021年に、航空機や艦艇、陸上配備の装備、総数3,000あまりを対象とする、単一かつデジタル化した兵站支援ソリューション「N-MRO(Naval Maintenance, Repair, and Overhaul)」の導入を決めた。
この「単一」がキモで、装備品の可用性を確保するために必要となるさまざまな作業を、一元的に管理しようとの話になる。実際、N-MROに関するリリースでも「視覚化された中央リポジトリに、資産と部品のデータを統合」との言及がある。どこに何がどれだけあるかを可視化かつ一元管理しようという話である。
それを担当することになったのが、IFS(Industrial and Financial Systems)と、御存じロッキード・マーティン。IFSというとなじみが薄い方がいらっしゃるかもしれないが、コンポーネントベースのビジネス・アプリケーション、設備資産管理、フィールドサービス管理のソリューションを提供している会社で、特に航空宇宙・防衛分野に強い。
航空宇宙・防衛という分野は、扱う製品が複雑かつ高度であり、しかも人命や国家安全保障に関わるだけに高いセキュリティ・レベルが求められる難しさがある。それを実現してきた実績があるからこそ、米海軍からの採用を決めることができたといえようか。
航空機にしろ艦艇にしろ、見た目は一つのヴィークルだが、それを構成するパーツやコンポーネントの数は数千から数万、もしかしたら数十万のオーダーに達する。それを適切に管理・交換・整備するとともに、どこに何がどれだけあるか、いつ整備作業を実施したか、その結果としての可動状況はどうか、といったデータを常に管理・更新しておかなければ仕事にならない。
-

米海軍の沿海域戦闘艦 (LCS : Littoral Combat Ship)「デトロイト」(LCS-7)の機関室で。機関がちゃんと動作しなければ、艦はただの鉄の塊になってしまう 写真 : US Navy
特に海軍が難しいのは、相手が陸上の固定された場所にあるわけではないこと。艦艇は世界を股にかけて行動しているし、航空機は陸上基地だけでなく空母や水上戦闘艦からも運用している。交換用のパーツやコンポーネントは、そうした現場に適切に送り届ける必要がある。
そうなると、モノの動きが複雑になるだけでなく、相手がオフライン環境になることも想定しなければならない。ことに戦闘状況下にある艦艇では、一切の電波の発信を止めてしまうことがあるから、そうなるとデータ更新をどうするかという課題ができる。それに対して適切な解決策を用意できなければならない。
TBMからCBMへの変化と予察機能
そしてこの業界でも、TBM(Time-Based Maintenance)からCBM(Condition-Based Maintenance)への移行という動きがある。つまり、「一定の時間ごとに、決められた内容の点検整備を行う形」から、「対象物の状況を把握して、それに合せて適切な点検整備を行う形」への移行となる。
また、不具合を未然に防ぐ観点からすれば、状況把握(状態管理)のデータと整備点検の記録を活用した、予察機能が重要になる。「こういう状態になったから、こんな故障があり得るのではないか」と予測する種類の話だが、それを実現するための支援手段として、人工知能(AI : Artificial Intelligence)やデジタル・ツインといった話が欠かせない。
そうした仕組みも、前述した「単一かつデジタル化した兵站支援」の枠組みに組み込む。そうしないと、予察に基づいた整備や交換作業が円滑に進まない。
著者プロフィール
井上孝司
鉄道・航空といった各種交通機関や軍事分野で、技術分野を中心とする著述活動を展開中のテクニカルライター。
マイクロソフト株式会社を経て1999年春に独立。『戦うコンピュータ(V)3』(潮書房光人社)のように情報通信技術を切口にする展開に加えて、さまざまな分野の記事を手掛ける。マイナビニュースに加えて『軍事研究』『丸』『Jwings』『航空ファン』『世界の艦船』『新幹線EX』などにも寄稿している。このほど、本連載「軍事とIT」の単行本第5弾『軍用センサー EO/IRセンサーとソナー (わかりやすい防衛テクノロジー) 』が刊行された。