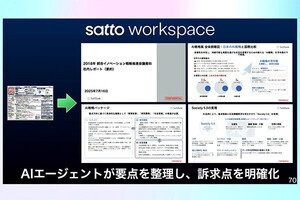普通、水上戦闘艦が備える戦闘システムといえば、その内容は固定的である。ここでいう戦闘システムとは、眼や耳の役割を務めるセンサー、頭脳の役割を務める指揮管制システム、実際に破壊を受け持つ武器(エフェクター)、これらすべてを指す。そして、それぞれどういう機器を搭載するかは最初から決まっている。→連載「軍事とIT」のこれまでの回はこちらを参照。
頓挫はしたがLCSはモジュール式
しかし、何事にも例外は発生するもので、モジュール方式をとる水上戦闘艦もある。つまり、戦闘システムの構成要素を独立したモジュールにして、必要に応じて脱着・交換する方式。
そうした水上戦闘艦の一つに、米海軍の沿海域戦闘艦(LCS : Littoral Combat Ship)がある。当初の構想では、以下に示す3種類のミッション・モジュールを用意して、必要に応じて艦に積み込むはずだった。
- 対水上戦 (ASuW : Anti Surface Warfare)ミッション・モジュール : 機関砲や艦対艦ミサイルで構成
- 対潜戦 (ASW : Anti Submarine Warfare)ミッション・モジュール : 潜水艦の捜索に使用するソナー、捜索と交戦を受け持つヘリコプターで構成
- 対機雷戦(MCM : Mine Countermeasures)ミッション・モジュール : 機雷の捜索や掃討を担当する無人ヴィークル群と、それらを管制するシステムで構成
ミッション・モジュールも管制する艦側の指揮管制装置
ただし艦側がスッピンというわけではない。最低限の固有兵装として、対空捜索レーダー、対水上レーダー、個艦防御用の短射程艦対空ミサイル、艦載砲、これらを管制する指揮管制装置などがある。
そして、艦側の指揮管制装置は、常に存在する固有兵装だけを管制していれば済むわけではない。それでは、ASuW・ASW・MCMといったミッション・モジュールが加わったときに、それらが単独で動作することになる。これを指揮官の立場から見ると、艦の中に独立した離れ小島ができてしまう。
例えば、ASuWミッション・モジュールを搭載していたとする。すると艦対艦ミサイルを用いた交戦が可能になるが、その前段階として、まず交戦すべき相手を見つけなければならない。
その情報は、自艦の対水上レーダーや、他の艦艇・航空機(自艦の搭載ヘリコプターも含む)から得られる。他の艦艇や航空機からは、データリンク経由で探知情報を受け取るが、その情報は指揮管制装置に入ってくる。
そこでASuWミッション・モジュールが離れ小島になっていると、どうなるか。せっかく、敵艦の探知情報が手に入っても、それをASuWミッション・モジュール側の射撃指揮システムに、手作業で入力し直さなければならない。それでは時間がかかるし、ミスの可能性もついて回る。
LCSに限った話ではない
LCSでは紆余曲折の結果、「必要に応じてミッション・モジュールを積み替える」方式はボツになり、搭載するミッション・モジュールを艦ごとに固定化する方向になった。だから「積み替え式」ではなく「共通化したプラットフォームから、さまざまな用途の艦を生み出す艦」に変質したといえる。
しかし近年、水上戦闘艦の分野では、「多用途区画」を確保して、さまざまな用途に充てられるようにする構想がいくつか出てきている。すると、単に「LCSの場合にはこうだ」という話ではなく、もっと一般化する形で、「モジュール単位で機能が付いたり外されたりする艦において、戦闘システムの統合化をどう実現するか」を考えなければならないだろう。
また、米海軍が実験を進めているLUSV(Large Unmanned Surface Vessel)では、搭載する「積荷」そのものが固定的ではない。センサー機器を積み込むこともあれば、対地攻撃用のミサイルを積み込むことも、対空ミサイルを積み込むこともあるだろう。
ともあれ、こうした事情によって固有装備ではない武器やその他の装備が加わったときに、前述したような「離れ小島」を作らないようにするには、何が必要か。
そのためには、追加するモジュールも艦側のシステムに接続して、一体となる、統合化したシステムを構成しなければならない。ことに戦闘任務に関わるモジュールの場合には、統合化は必然となる。
ところが、接続するモジュールの内容や仕様を、当初に固定できるとは限らない。状況の変化に合わせて、新種のモジュールが登場する可能性を考える必要がある。それは、就役後の能力向上のためにも必要なことである。パソコンの周辺機器を、より高機能・高性能の新型に変えたり、新しい周辺機器をつないで新しい機能を加えたりするようなものだ。
この、付加機能を必要に応じて脱着する仕掛けのことを、ミリタリーの業界でも民間と同様に “Plug and Play” と呼ぶことがある。では、それを実現するためには何が必要か。
艦艇の “Plug and Play” 化に必要な要素
その、艦艇の “Plug and Play” 化を実現するには何が必要だろうか。
まず、十分な伝送能力と抗堪性を持たせた艦内ネットワークは不可欠である。戦闘システムを構成するセンサーもコンピュータも武器も、みんな同じネットワークに接続して、相互に通信できるようにする。
それだけなら特段珍しいことではないが、“Plug and Play” 化を図ろうとすると、モジュールの参加や退出を検出する機能が必要になる。
これが、パソコンとその周辺機器の “Plug and Play” 化なら、パソコンが持つインタフェースの使用状況を見ていれば良い。ところが、ネットワークに接続する場合は、そのネットワークを通じて参加や退出を知らなければならない。
ということで、その辺の具体的な話は次回に考察してみる。
著者プロフィール
井上孝司
鉄道・航空といった各種交通機関や軍事分野で、技術分野を中心とする著述活動を展開中のテクニカルライター。
マイクロソフト株式会社を経て1999年春に独立。『戦うコンピュータ(V)3』(潮書房光人社)のように情報通信技術を切口にする展開に加えて、さまざまな分野の記事を手掛ける。マイナビニュースに加えて『軍事研究』『丸』『Jwings』『航空ファン』『世界の艦船』『新幹線EX』などにも寄稿している。このほど、本連載「軍事とIT」の単行本第4弾『軍用レーダー(わかりやすい防衛テクノロジー)』が刊行された。