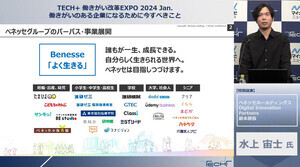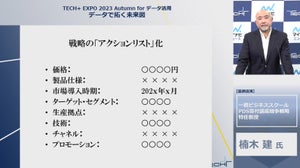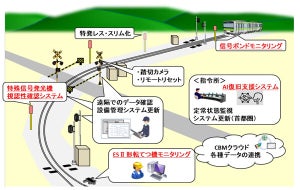企業の情報システム部門の責任者に、業務内容や課題、DX(デジタルトランスフォーメーション)への取り組み等を聞く本連載。業種は異なっていても、情報システム部門が抱える課題には共通項目が多い。他社の課題解決の方法やDXを知り、ぜひ自社の改革に生かしてほしい。
初回となる今回は、自動車メーカーSUBARUのCIOである阿部一博氏に話を聞いた。阿部氏は、ボディの構造設計、米国工場駐在を経て、商品企画に25年間在籍していたが、昨年の4月からIT戦略本部に異動したという変わった経歴を持つ。
阿部氏によれば、同社のIT戦略本部は、共通部門や販売部門、サービス部門などの業務システムの企画開発、導入、運用がメインだが、最近は、コネクティッドカーの領域とデータ活用に力を入れているという。
コネクトは、クルマに搭載されているハードやソフトと外部システムの接続に関するもので、IT戦略本部は、クラウドにつながるサーバの企画と開発を担っている。
データ活用は、クルマの企画、販売、サービスまでのプロダクトライフマネジメント(PLM)をデータでつなぎ、さまざまな効率化やデータ分析を行って、業務プロセス改革につなげていく取り組みだ。
データ活用の狙い
データ活用について、阿部氏は狙いが2つあると述べた。
「クルマの企画から販売、販売後のサービスも含めて一気通貫でつなげないと、せっかくのデータがまったく活用できません。ある部門のデータが別の部門で使えない。使いたかったら、再度インプットし直さなければならない。そんな状態では競争に勝てるわけがありません。また、現場で見つかった不具合データを使いたい人もいるので、それをデジタル化して使えるようにしていく。しかも、単にデータを見せるだけではなく、分析して表現するところをやりたいと思っています。それが広がっていけば、DXにつながっていくと思っています」(阿部氏)
データ活用に向け、同社は基盤としてグローバルPLMを3年かけて構築した。また、データガバンスを効かせるために、一定のルールも決め、大きな会議では、ルールを守ってデータ活用していくことが重要であることを繰り返し話したという。
また、せっかく作ったプラットフォームが利用されないという状態を防ぐため、データは会社のものであり、データを使うことによるメリットも例を挙げて説明したという。
「ガバナンスを効かせながら、メリットを提示してやっていくことが重要だと思っています。このデータが、後に、どういうメリットをもたらすのかを社内セミナーで伝えてきました」(阿部氏)
データ活用を推進する部署を新設
データ活用においては、データを提供する側と利用する側のレベル合わせも重要だ。提供する側は「これで十分」と思っても、使う側は「もっと詳細なデータがほしい」「別の軸で集計したデータがほしい」ということがある。こうしたミスマッチを防ぐために、両者を仲介するデジタルイノベーション推進部という部署を新設した。
この部署は、データプラットフォーム構築の推進、データ活用のスキル教育、現場におけるデータ活用支援、さらには多くの人が使い易くするためのデータ管理まで幅広く行っている。
「データを活用すれば課題が解決できるのではないか。そういう意識を持っている人が社内にいます。逆に言うと、そういう人がいなかったらデータ活用が進まないと思います」(阿部氏)
同社では、こうしたデータ活用の基盤にトレジャーデータのCDP(カスタマーデータプラットフォーム)を導入している。活用例としては、次のようなものがあるという。
「例えば、テレビCMの効果は、かつては視聴率やCM好感度などで評価する方法しかなかったのですが、それでは視聴率や好感度が高くてもなぜか売れないといった事象が起きます。顧客の行動と直接つながらないからです。CMの放送ログとWebサイトのアクセスログ、顧客の行動ログを統合することで、CMを流した後の顧客の行動を追うことができるようになりました。そうすると、CMを流した後のWebサイトのアクセスログを収集し、時分秒単位でどういう人が流入して、流入した人の何割が購入し、流入後の行動はどう違うのかを分析することによって、こういう時間に、この番組で流入した人はこういう行動をとった結果、買った、買わなかったということが分かります。そこで、そういう行動をさせるためにコンテンツはどう変えればいいのかといった改善の施策につなげるための動きができるようになります」(阿部氏)
自動車業界では、売上アップに向けて、ディーラーと呼ばれる販売店からの情報も重要だ。そのため同社は販売を行う各特約店に対して、DMS(ディーラーマネジメントシステム)を一元的に提供している。このシステムのデータは、SUBARUのデータになっており、購入の有無、来店時のアンケートといった顧客に関する重要なデータが入っているという。
「これらの行動とお客様の情報、そしてその販売がどうなったかという流れを、すべて一本の線でつなげて見ることができることが、当社の強みになっています」(阿部氏)
また、データ活用では、使う人は良く活用するが、使わない人はまったく使わないといった活用頻度に濃淡が出て来る。こうしたことを防ぐため、同社ではトップを上げるアプローチとボトムを上げるアプローチ両方の教育に力を入れているという。
DXを通した業務改革を推進
ここ数年、企業ではDXが注目されているが、同社でもDXを通した業務改革に取り組んでいる。
「業務プロセスを改革していくことがITの役割だと思います。手書きの文書をデータにするだけではなく、今までのやり方を変えると良くなるという部分を作っていくのもITだと思います。また、ITによって、今まで5分かかっていたものが1分でできるようになる、数秒できるようになるという効率化も実現します。1つの効率化の効果は小さくても、1万人いればその効果は高まります。そういうITを基軸に効率化を行うことと、業務プロセスを改革していくことの2つがDXの目的です」(阿部氏)
そのために同社は昨年の4月、スマートワークDXプロジェクトをスタートし、かなりの効果が出ているという。ただ、DXを進める上では、情報システム部門の意識を変えることも重要だと同氏は述べた。
製造業のシステムの基本的に自動化を実現するものであり、これまでは自動化をするためにシステムを使うという意識があったという。
「手作業をシステムで自動化することを何十年もやってきているので、情報システム部門の人たちも自分たちが業務のプロセスを改革するところに入っていくという感覚が弱いです。私はもともと情報システムにいたわけではなく、業務部門から異動しているので、そういったことにとても違和感がありました。なぜそんな無駄なやり方をしているのかということが、外の人の方がよく見えることがあります。自分のやっていることも非効率だと思っていたので、情報システム部門の人と一緒に仕事ができることになった時に、単純に言われた通り自動化への要求を受けていてはいけないと感じました。逆に、その非効率な仕事を変え、それをシステム化するというスタンスでリードできるようにと言っています」(阿部氏)
同社では50年ほどコンピュータが使われており、当時は意図を持って入れていたロジックも、今ではそれを作った人がいなくなってロジックだけが残り、現場ではそこから出て来るものが正だという感覚になるという。ただ、情報システムの人はロジックを読むことができるため、別のロジックに変更したり、業務のプロセス自体を変えたりといった提案ができるはずだと阿部氏は語っていた。