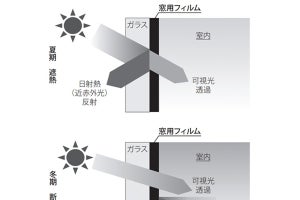前回、前々回と一般住宅の冷房効果について詳しく解説してきた。その結果を踏まえ今回は、アトピー性皮膚炎と冷房の関係について解説する。
アトピー性皮膚炎患者の自宅温熱環境に関する研究
アトピー性皮膚炎患者は長期調査に賛同を得た6名を対象とした。患者宅の概要は以下の通りである。
-

アトピー性皮膚炎患者宅の概要。冷房頻度の項目は、在室時にはほぼ毎日使用と回答した住宅を「頻度が高い」、暑いときに使用するが「やや高い」、あまり使用しないを「頻度が低い」、使用しないおよび保有していないを「不使用」としている(出典:日本建築学会環境系論文集, 605, 55-62)
患者に関する属性は以下の通りだ。
これらのアトピー性皮膚炎患者宅の7〜8月の室温の日平均と標準偏差、室内外気温差、外気温と室温の相関係数rおよび回帰係数aと、同様に検討した絶対湿度の結果が下の表である。
平均室温は家屋の構造や冷房の使用頻度に関係なく27℃~28℃で一般住宅との差は認められなかった。冷房使用頻度の低いB宅の内外気温差は、1.1℃で外気より有意に高く、冷房頻度の高い住宅のうち室内気温が有意に低いのはF宅のみで、冷房頻度と室温低下の関連は不明瞭であった。
一方で、室内絶対湿度はすべての患者宅で外気よりも有意に低く、冷房使用頻度の高い住宅の内外差は-2.6g/kg’~-7.3g/kg’と、頻度の低いB宅と比較して低下が大きかった。
以上より、一般住宅と同様に患者宅でも絶対湿度は気温よりも冷房頻度との関連性が高いと推察された。
患者宅の外気温と室内気温の関係をみると、室内気温が外気温よりも高い日が多いA、B宅と低い日が多いC〜F宅に分けることができた。前者の回帰係数はそれぞれ、a=0.31、0.42、後者の回帰係数はa=0.16~0.24であった。
また、絶対湿度をみるといずれの住宅も室内絶対湿度の方が、外気絶対湿度よりも低く、回帰係数は冷房頻度の低いB宅で最も大きく、A、C、F、E、D宅の順に小さくなった。
これら、冷房頻度の高い住宅では、A宅を除いて絶対湿度の内外差が大きいほど回帰係数が小さく、室内外絶対湿度差、つまり除湿量と回帰係数の関係に対応が見られた。
一般住宅とアトピー性皮膚炎患者宅の温熱環境の違い
以上の結果をもとに、一般住宅とアトピー性皮膚炎患者宅の室内外気温差と室内外絶対湿度差の平均値を求め、冷房効果を室内外絶対湿度差を基準に比較検討したのが以下の図だ。
アトピー性皮膚炎患者宅6戸にのうち4戸(B、C、E、F宅)は一般住宅の結果とほぼ一致したが、2戸(A、D宅)では絶対湿度が大きく低下しているにもかかわらず、室温の顕著な低下はみられなかった。
A宅では絶対湿度差が-4.1g/kg’と大きかったが、気温差は1.6℃と外気よりも室温が高かった。また、D宅では絶対湿度差が-7.3g/kg’と大きかったが、気温差は-0.7℃であり、これら住宅では、患者宅の冷房を強化しながらも、室温の低下を抑制している可能性が高いと推定された。
このような相違はアトピー性皮膚炎の病態生理学的な特徴が関係していると考えられる。
アトピー性皮膚炎患者の表皮は角質細胞間脂質のセラミドの含有が低く、非病変部でも乾燥傾向にある。このような皮膚の特徴として、低湿度などの様々な刺激によって症状が出現、悪化しやすいことが挙げられる。また、低湿度環境(気温25℃、相対湿度40%)でアトピー性皮膚炎患者の皮膚水分率が低下し、入室10分後に症状が出現することが実験的に示されている。
さらに、厚生労働省のアトピー性皮膚炎患者治療ガイドラインにおいても、乾燥対策について言及されている。一方、アトピー性皮膚炎患者では体温調節機能、特に発汗能の低下が報告されており、気温30℃、相対湿度75%で患者の皮膚温は健常者よりも約0.5℃高く、皮膚水分率は逆に低いことから、発汗量の低下が高皮膚温の原因であるとも考察されている。
これらの病態生理学的な特徴をもとに今回の結果を推論すると、アトピー性皮膚炎患者は発汗機能が低下しているので、高温下で熱を敏感に感じ、冷房強度を高めている可能性が考えられる。
しかし、冷房を強化すると空気中の水分量がより低下し、皮膚水分が喪失し乾燥状態が出現する。そこで患者は冷房による室温低下が悪化要因であると考え、除湿運転など室温の低下を避けると考えられる。A、D宅が絶対湿度の低下が著しいにもかかわらず、室温の低下が一般住宅と比較して小さい原因は、このことを示唆している。
また、冷房の強化にともなう湿度低下は、皮膚炎の悪化や治療の遅れの要因となっている可能性があるため、上図が示す結果は患者が冷房環境下で悪循環に陥っている可能性を示唆している。
このような推論の当否は皮膚科学からの検証を要するが、今回の検討結果から、アトピー性皮膚炎患者は健常者とは異なった温熱環境下で暮らしている可能性が高いと推定される。
したがって、さらに多くの患者を対象として、アトピー性皮膚炎の症状の変化と冷房との関連を本研究結果にもとづいて検討することは、アトピー性皮膚炎患者の暮らしに適した室内温熱環境の構築上、極めて重要な課題であると考えられる。
湿度とアトピー性皮膚炎の関係
3回に渡り紹介した本研究の内容は、一見、専門的な用語で難しい内容に思えるかもしれない。しかし、内容を簡潔にまとめると以下のようになる。
1回目では住宅の室温に着目して冷房効果を検討したが、成果が見えにくかった。 そのため2回目では冷房の除湿効果に着目し空気中の水分量(絶対湿度)を検討した結果、室温の変化よりも顕著な傾向が見られたため、冷房効果を検討するには絶対湿度で評価する方がよいと考えた。
3回目では一般住宅とアトピー性皮膚炎患者宅の室内外の気温差および絶対湿度差の傾向を比較したところ、一般住宅よりも室温が低いにもかかわらず、絶対湿度が大きく低下していた。
この原因は、患者宅では室温低下によって乾燥し症状が誘発されていると考え、除湿運転などすることで室温の低下を避けたためと推察された。しかし、そのような傾向は、僅かな気温差で絶対湿度を大幅に低下するため、悪循環に陥っているのではないかと考えられた。
今回は冷房による影響について紹介したが、もちろん暖房に関する研究論文もある。いずれにしても、空気中の水分状態について議論している。興味があれば、ぜひ、暖房とアトピー性皮膚炎についても調べてみるとよいだろう。