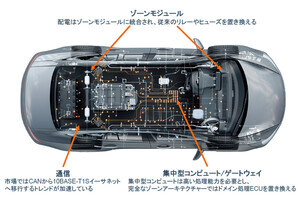8月20日に、ドイツ海軍のフリゲート「「バーデン・ヴュルテンベルク」が東京国際クルーズターミナルに寄港した。「なぜ、航空機の連載なのに軍艦の話を?」と奇異に思われそうだが、同艦はリンクスMk.88ヘリコプターを2機搭載しており、そのヘリコプターのハンドリングが今回のお題なのである。
ちなみに、「バーデン・ヴュルテンベルク」については、別連載連載「軍事とIT」の「東京に登場、非対称戦に特化した独フリゲート」において、詳しくお伝えしているので、興味がある方はこちらを参照されたい。→連載「航空機の技術とメカニズムの裏側」のこれまでの回はこちらを参照。
ハープーン・グリッド・システムは移送ができない
本連載の第155回で、「ハープーン・グリッド・システム」を取り上げた。円形のパネルに小穴がたくさん開いていて、これをヘリ発着甲板の中央部に取り付ける。
ヘリコプターが着艦するときには、胴体の下面にプローブを突き出して、この小穴に突っ込む。小穴はたくさんあるので、どれかの小穴にひっかかってくれる。これなら、多少の動揺や傾斜があっても安全にヘリを甲板に降ろすことができる。
ところが第155回でも指摘したように、ハープーン・グリッド・システムは「拘束」の機能だけである。着艦させたヘリコプターは、その前方にある格納庫に取り込まなければならないが、そのための移送装置がない。手で押して動かすのでは、それこそ動揺や傾斜があったときに危険だ。
日本やアメリカの艦では、カーティス・ライト社のRAST(Recovery Assist, Secure and Traverse)あるいはASIST(Aircraft Ship Integrated Secure and Traverse System)などといった機器を備えている。これらは前後方向に設けられたレールに沿って拘束装置が動く仕組みになっている。
だから、着艦したヘリコプターを拘束装置で捉えたら、拘束装置ごとレールに沿ってズリズリ動かせば良い。するとヘリコプターは格納庫に引き込まれる。逆の動きをすれば出庫になる。
では、ハープーン・グリッド・システムを備えている艦はどうするか。その問いに対する解答の一つが「バーデン・ヴュルテンベルク」の艦上にあった。
FHS社製Type 110移送装置
「バーデン・ヴュルテンベルク」のヘリ発着甲板を見ると、後方の左右に謎の機器が置かれている。その機器を見ると、どうやら、左右方向に走るレールに沿って動くようである。
これが、FHS(Foerder - und Hebesysteme GmbH)社製の、Type 110ヘリコプター移送装置。ヘリコプターが着艦して、ハープーン・グリッド・システムによって拘束されると、普段は左右の端に寄せてある移送装置が、レールに沿って横移動して、ヘリコプターの位置まで寄ってくる。
ヘリコプターを移送する仕組み
次に、装置が前方に延びて、ヘリコプターの降着装置を支える形で持ち上げる。これで機力によるヘリコプターの移送が可能になる。その際の位置合わせには光学センサーを使用しており、精確にヘリコプターの位置を把握できる、というのがメーカー側の説明。
RASTやASISTでは、ヘリ発着甲板の中央にある着艦位置から直接、格納庫に向けてレールが延びている。そして、拘束装置が掴んだ機体はそのまま移送される。米海軍のアーレイ・バーク級フライトIIA駆逐艦みたいにヘリ格納庫が2機分並んでいる場合には、レールは着艦位置を頂点としてV型に配されており、左右のどちら側にでもヘリコプターを送り込めるようになっている。
一方、「バーデン・ヴュルテンベルク」はどうかというと、ヘリコプター格納庫は左右並列に2カ所ある。ところが、そこから後方に延びる移送用レールは艦の首尾線と平行しており、V型にはなっていない。よって、着艦した位置から直接、ヘリコプターを格納庫に取り込むことはできない。
そこでType 110移送装置は、まずヘリコプターを左右に移動して、左右いずれかの移送用レールの位置に持って行く。それから、移送用レールに沿ってヘリコプターを前方に動かして、格納庫に押し込む流れとなる。
-

「バーデン・ヴュルテンベルク」のヘリ発着甲板。移送用レールが格納庫から首尾線に沿って伸びている様子がわかる。テイルブームの向こう側に、ハープーン・グリッド・システムの穴あきパネルも見て取れる 撮影:井上孝司
ただ、前後方向の移送を人力で行うのでは、動揺が激しいときに危険だ。だからメーカーは「自動的に移送できる」と説明している。ただし、その仕組みについては、外から見る限りでは判然としなかった。Type 110の本体をめいっぱい延ばしても、格納庫には届かないように見えるのだが。
ザクセン級(124型)フリゲートなどにも搭載
ちなみにこのシステム、バーデン・ヴュルテンベルク級(125型)フリゲートだけでなく、ザクセン級(124型)フリゲートやベルリン級(702型)補給艦でも用いられているそうだ。
Type 110は最初期のモデルで、同社の移送装置にはさらに、Type 210、Type 310、Type 320、Type 410/430/450、Type 420/440/460といったモデルがある。Type 410/430/450とType 420/440/460は基本的に同系列だが、移送に使用するウインチの数が異なる由。
著者プロフィール
井上孝司
鉄道・航空といった各種交通機関や軍事分野で、技術分野を中心とする著述活動を展開中のテクニカルライター。
マイクロソフト株式会社を経て1999年春に独立。『戦うコンピュータ(V)3』(潮書房光人社)のように情報通信技術を切口にする展開に加えて、さまざまな分野の記事を手掛ける。マイナビニュースに加えて『軍事研究』『丸』『Jwings』『航空ファン』『世界の艦船』『新幹線EX』などにも寄稿している。このほど、本連載「軍事とIT」の単行本第4弾『軍用レーダー(わかりやすい防衛テクノロジー)』が刊行された。