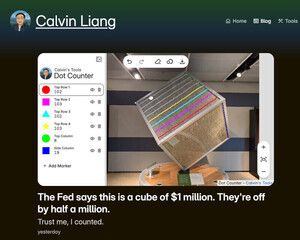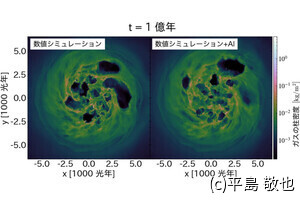クレーンといっても起重機の話ではなくて。米国防高等研究計画局(DARPA : Defense Advanced Research Projects Agency)では、一般的な動翼を使用しない新技術の試験機として、CRANE(Control of Revolutionary Aircraft with Novel Effectors)という計画を進めている。今回は、このCRANEを取り上げる。→連載「航空機の技術とメカニズムの裏側」のこれまでの回はこちらを参照。
Active Flow Control
このCRANE計画、名称を逐語訳すると「新手の手法で制御を行う革新的航空機」という意味になるが、例によってバクロニムの匂いがしなくもない(DARPAのプログラムではよくあること)。
そのCRANE計画は、2023年1月に、オーロラ・フライト・サイエンスがフェーズ2契約の担当に決まった。
同社はまず、2022年12月に4,200万ドルのフェーズ1契約を得て、予備設計の作業を実施した。それに続くフェーズ2では、詳細設計と飛行制御ソフトウェアの開発を実施して、最終設計審査(CDR : Critical Design Review)まで作業を進めることとしている。
その後のフェーズ3で、7,220lb(3,278kg)級の実験機「X-65」を製作して、飛行試験を実施する計画となっている。2024年の初めに、機体の製造を開始している。
では、CRANE計画では何を実証しようとしているのか。それがAFC(Active Flow Control)という技術。つまり、補助翼、昇降舵、方向舵、フラップといった動翼を動かす代わりに気流を用いた制御を行うことを企図している。
どこかで聞いたような話だなと思ったら、本連載の第264回で取り上げた、BAEシステムズの「MAGMA」がやはり、動翼の代わりに気流を使用する話だった。
MAGMAの場合、補助翼の代わりはエンジン抽気を後縁部のスロットから超音速で噴射する “wing circulation control” を、昇降舵と方向舵の代わりは空気の噴出によってジェット・エンジンの排気を偏向する “fluidic thrust vectoring” を利用することとしていた。
ダイヤモンド翼を持つ実験機はX-65
すでに、X-65の想像図はリリースされている。機体は無人で、最大速力はマッハ0.7(463kt/857km/h)。翼幅は30ft(9.14m)だから、そんなに大きな機体ではない。
動力源は後部胴体に組み込まれたジェットエンジンで、機首の下面に空気取入口を設ける。それとは別に、機首の内部にAPU(Auxiliary Power Unit)を組み込む。
機首からは後退角がついた翼面が、尾部からは前進角が付いた翼面が伸びて、それらがつながった先に(外側に)、さらに小さな翼面が伸びている(ダイヤモンド翼と呼ばれている)。また、尾部には双垂直尾翼が立っている。
これらの翼面の表面に、空気吹出口とおぼしき物体が描かれている。そこに高圧の空気源から供給する空気を噴射して、機体表面の気流をコントロールすることで、三軸方向の動きを可能にする。空気の噴射によって、エネルギーや運動量を直接的に加えて気流を変更するのだという。空気の噴射は、空気配管の途中に設けられたバルブの開閉によって制御する。
BAEシステムズのMAGMAでは、エンジンの推力偏向を併用する手法だった。それに対して、DARPAのAFCではエンジン排気はいじらず、機体の表面を流れる気流の制御だけで実現しようとしているようである。
ただし、双垂直尾翼には方向舵を、ダイヤモンド翼の後縁にはフラップを設置する。従来型の操縦翼面とAFCの両方を設置することで、両者の比較ができるという考えなのだという。AFCを使用するときには、方向舵やフラップをロックしてしまえば良いわけだ。
オーロラ・フライト・サイエンスがX-65に関する動画を公開しているので、リンクを張っておく。
X-65: Designed to Demonstrate Active Flow Control
なお、機体表面に設置して空気を噴射する「エフェクター」は全部で14カ所にあり、これは交換可能。また、外翼も交換可能な設計で、エフェクターや外翼を別のものに変更して比較試験に供することもできる。
AFCのメリットとは
DARPAの説明では、CRANE計画を通じて、AFCに関わる技術と設計ツールを熟成するとともに、それらを設計プロセスに取り込むとしている。
AFCそのもののメリットとしては、ヒンジを介して動く動翼をなくすことで、重量を軽減するとともに、構造をシンプルにできる点を挙げている。確かに、動翼を動かすためには索やロッドやリンク機構やアクチュエータが必要で、これは複雑な仕掛け。しかも使えなくなったら一大事だから、高い信頼性が求められる。
その辺の仕組みがシンプルに、かつ軽くまとまれば、機体の軽量化につながるし、捻出した空間や重量を他の用途に回すこともできる。それだけでなく、機体表面の形状が変化しなくなれば、対レーダー・ステルス性能の向上というメリットも期待できよう。これは軍用機に限定される話だが。
また、空気抵抗の低減、高迎角飛行の達成、翼厚の増加による構造効率の向上と燃料搭載量の増加、というメリットも挙げられている。
著者プロフィール
井上孝司
鉄道・航空といった各種交通機関や軍事分野で、技術分野を中心とする著述活動を展開中のテクニカルライター。
マイクロソフト株式会社を経て1999年春に独立。『戦うコンピュータ(V)3』(潮書房光人社)のように情報通信技術を切口にする展開に加えて、さまざまな分野の記事を手掛ける。マイナビニュースに加えて『軍事研究』『丸』『Jwings』『航空ファン』『世界の艦船』『新幹線EX』などにも寄稿している。このほど、姉妹連載「軍事とIT」の単行本第4弾『軍用レーダー(わかりやすい防衛テクノロジー)』が刊行された。