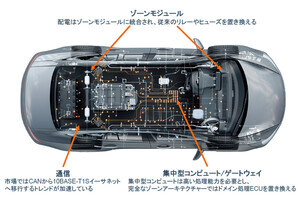第419回で戦闘機のキャノピーについて書いた。それよりかなり前となる第34回でも窓の素材や構造について書いた。どちらにしても、人間の目玉が外部の様子を見られること、という前提条件があり、それを満たすための素材や設計が取り入れられている。そこで、その他のセンサーも含めて、「センサー窓」の話を。→連載「航空機の技術とメカニズムの裏側」のこれまでの回はこちらを参照。
-

乱暴なことをいえば、風防やキャノピーはMk.1アイボール(つまり人間の目玉)のためのセンサー窓だが、写真のF-2みたいに透明な素材ばかりとは限らないのが面白い。視界を妨げずにレーダー電波などの反射をを減らす工夫をしているため、そうなる 撮影:井上孝司
センサー窓が満たすべき条件とは
飛行機の機体構造は一般的に、アルミ合金が主役。近年では炭素繊維強化樹脂(CFRP : Carbon Fiber Reinforced Plastic)を初めとする複合材料の使用事例も増えているが、やはり金属が主役。たまにステンレス・スチールの使用例もあるが、これとて金属であることに変わりはない。
そして金属素材にしろCFRPにしろ、広義の電磁波を遮ってしまう。電波はもちろんのこと、可視光線も赤外線も紫外線も遮ってしまい、直接的な伝播はできなくなる。その内部にセンサー機器を設置しても仕事にならない。
だから、センサー機器を設置する場合には、そこに一種の「窓」を開ける必要がある。センサーをむき出しのままで設置したのでは損傷する危険性があるし、凸凹が増えて空気抵抗の源にもなる。ステルス機ではステルス性を損ねる原因にもなる。
だから、機体内にセンサーを設置して「窓」を開けたり、外部に突出する形でセンサーを設置してフェアリングで覆ったりしている。
ところが、航空機で使用する材料では強度や耐久性の要求水準が高い。温度変化に耐えられるだけでなく、強い紫外線を浴びても劣化しないことも求められよう。また、金属製の機体構造が圧力変化や温度変化によって伸縮したときに、センサー窓が変型したり割れたりしては困る。吸湿による素材の劣化が問題になることもあるそうだ。
となると、耐久性が高い素材を開発することはもちろんだが、交換が容易にできる設計、定期的に交換する消耗品と見なして製造コストを抑制する設計も求められそうである。
可視光線や赤外線の場合
コックピットの風防やキャノピーにしろ、旅客機の側窓にしろ、可視光線を透過する「窓」を設けて外部視界を確保するためのもの。だから、窓の素材は可視光線を通せるものでなければならない。
これが赤外線センサーなら赤外線を通す素材、紫外線を使用するミサイル接近警報装置なら紫外線を通す素材が要る。
そこで、例えばターゲティング・ポッドや電子光学センサー・ターレットの現物を観察してみると、可視光線を用いるセンサーのセンサー窓はもちろん透明だが、赤外線を使用するセンサーのセンサー窓は黒っぽく、透明ではない。
F-35が備えるAN/AAQ-37 EO-DAS(Electro-Optical Distributed Aperture System)でも、赤外線センサーの設置場所には黒っぽい色のセンサー窓が設けられているので、一目でそれと分かる。
調べてみたら、赤外線透過素材の例として、合成石英、サファイア、ゲルマニウム、フッ化カルシウム、フッ化マグネシウムなどが挙げられていた。素材によってそれぞれ適性があり、サファイアは近赤外線をよく通すが、中波長赤外線になるとゲルマニウムの方が透過率が良いという。赤外線の波長が異なると、それが素材に影響するということか。
このほか、N-BK7という素材がある。BK7とは屈折率ガラスの一種で、それのRoHS指令適合材料がN-BK7、正体はホウケイ酸クラウンガラスだという。ホウケイ酸ガラスとは、通常のガラスよりホウ酸の含有率が高いガラスなのだそうだ。
レドームやアンテナ・フェアリングの場合
では、もっと周波数が低く、波長が長い電磁波はどうだろうか。つまり、いわゆる電波のことである。電波といっても周波数のレンジは広いが、いずれにしても金属素材で遮られてしまう。だから、電波を使用するセンサー機器のアンテナに、金属製の覆いを設けたのでは仕事にならない。
そのため、合成樹脂などの非金属素材を使用するのが一般的となる。調べてみると、グラスファイバー、テフロン、シアネートエステルなどの素材が出てくる。もちろん、電波を透過する観点からいっても、機体を軽量化する観点からいっても、できるだけ薄くて強固な構造にしたい。
そこで、ハニカムコアと繊維強化樹脂を組み合わせたサンドイッチ構造にする事例もあるそうだ。ただし、ハニカムコアが金属製では電波を遮ってしまうから、ガラス繊維強化樹脂(GFRP : Glass Fiber Reinforced Plastic)、あるいはムクの合成樹脂みたいな非金属素材を使う。
レドームは機首に設置することが多いから、空力的な負荷がかかりやすい。機首以外の場所に設置するレドームでも、空気抵抗は少ない方がいいに決まっている。そして空力設計を優先すれば形状が先に決まってしまうから、設計通りの形状のものを安定した品質で製造できること、という要件も出てくる。
ここまでは素材の話だが、ことにレドームでは外部塗装が問題になるかもしれない。使用する塗料の素材が電波の透過に悪影響を及ぼすと困るからだ。しかし一方で、素材の保護、そして軍用機では視認性の低減という要求もあるから、無塗装というわけにも行かない。
センサー窓の手入れ
レドームやアンテナ・フェアリングを雑に扱って良いわけではないが、気を遣うといえばやはり、可視光線を使用するセンサーの窓であろう。
風防やキャノピーにゴミや傷がついていると、視界の妨げになる。すると、フライトの前にせっせと磨くことになるが、そこで傷をつけるようなことになっても困る。ことに戦闘機の整備員が苦労するところだろう。
旋回・俯仰が可能な電子光学センサー・ターレットであれば、以前にも書いたように、使用しないときは後ろ向きにしてセンサー窓を保護するのは一般的な運用。しかし、風防やキャノピーはそれができない。地上では、保護のためにカバーをかけていることがあるが。
では、ブームXB-1みたいに風防のサイズを局限して前方の映像をカメラで得るようにした機体はどうだろうか。と思ったが、風防の手入れがカメラ窓の手入れに変わるだけだから、大きな違いにはならないと思われる。
著者プロフィール
井上孝司
鉄道・航空といった各種交通機関や軍事分野で、技術分野を中心とする著述活動を展開中のテクニカルライター。
マイクロソフト株式会社を経て1999年春に独立。『戦うコンピュータ(V)3』(潮書房光人社)のように情報通信技術を切口にする展開に加えて、さまざまな分野の記事を手掛ける。マイナビニュースに加えて『軍事研究』『丸』『Jwings』『航空ファン』『世界の艦船』『新幹線EX』などにも寄稿している。このほど、姉妹連載「軍事とIT」の単行本第4弾『軍用レーダー(わかりやすい防衛テクノロジー)』が刊行された。