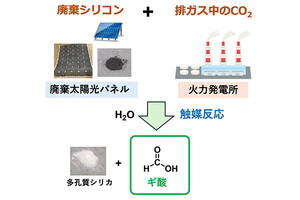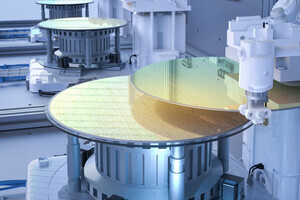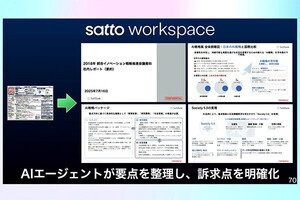正確にいうと「名前は違う」のだが、一つの開発プログラムの中で異なる平面型の主翼を両方試してしまえ、という話が出た事例が、今回のお題。
デルタ翼 vs 後退翼
1953年8月に、旧ソ連のスホーイ設計局に「前線戦闘機と防空戦闘機を開発せよ」とのお達しが出た。
前線戦闘機とは、制空、つまり空対空を主体として、対地攻撃もできる戦闘機。西側では戦術戦闘機と呼ぶ種類のものだろうか。対して防空戦闘機は、対地攻撃能力は要らない。全天候戦闘能力を持たせるために射撃管制レーダーを積んで、長射程の空対空ミサイルを載せる。それぞれ求められる機能・性能が違うから、別個の機体として開発する。これは分かる。
ところが当時のソ連では、後退翼とデルタ翼と、どちらにすればいいかという結論が明確になっていなかった。ここでいうデルタ翼とは無尾翼デルタ翼ではなくて、水平安定板を併用するデルタ翼のこと。有名なところでは、MiG-21がこれである。
さんざん悩んだ(?)結果、「両方とも実機を作って飛ばしてみよう」ということになった。順列組み合わせからいえば4種類の試作機を造ることになる。ところがその後の経緯により、後退翼の前線戦闘機案とデルタ翼の防空戦闘機案だけが生き残り、「同じ機体で主翼が2種類」は実現しなかった。
もっとも、MiG-21の先祖筋では後退翼の試作機Ye-2と水平安定板付きデルタ翼の試作機Ye-5の両方が造られたから、こちらは「同じプログラムで2種類の主翼」といえる。最終的に両者の性能は互角になり、それなら構造が簡単で軽く造れるデルタ翼の方が良いとの結論になった。それを具現化したのが、ベストセラーとなったMiG-21である。
後退翼→部分的な可変後退翼
先のスホーイの件では、後退翼を備える前線戦闘機は結局、Su-7として結実した。一方、デルタ翼を備える防空戦闘機は、Su-9として結実した。胴体の設計は似ているが、主翼の平面型と用途が違う2機種ができたわけだ。
ただし以前にも書いたように、主翼の空力中心は平面型や後退角の影響を受ける。仮に前縁後退角が同じでも、後退翼とデルタ翼では空力中心の位置は同じになるとは限らない。
だからSu-7とSu-9の平面型を比べると、後退翼を使うSu-7の方が、主翼が機首に近い位置に取り付いているようだ。そうなると、翼胴結合部を初めとする胴体の構造設計も違ってくるのが自然な成り行きだろう。その辺の事情は、Ye-2とYe-5でも同じだったと思われる。 その後、Su-7の燃料搭載量や兵装搭載能力を強化した改良型ができた。ところが、インフラが整っている本国での運用を前提にできる防空戦闘機と違い、前線戦闘機は前線に近い、短い滑走路しかない場所を拠点にする可能性もある。にもかかわらず、燃料や兵装の搭載量を増やすと離着陸時の滑走距離が伸びてしまう。何か、離着陸時の滑走距離を短縮するためのブレークスルーはないか。
そこで出てきたアイデアが、「後退翼の外翼だけ可変後退翼にする」というもの。ただし可変後退翼にすると、後退角の変化によって空力中心が前後に移動するので、それと機体の重心位置との関係をどうするんだという問題が出てくる。ところがスホーイのそれは、主翼をまるごとではなくて、内翼は固定式にして外翼だけ後退角を変える方式にしたので、空力中心の移動に伴う影響も少なくて済んだらしい。
こうして登場したのが、Su-17と、その輸出型・Su-22。完全な可変後退翼機に比べれば見劣りする部分はあるかも知れないが、堅実に離着陸性能の向上を達成したのだから、これはこれで正しい。
Su-17やSu-22の内翼は固定式だから、兵装搭載もやりやすい。可変後退翼の下に兵装パイロンを取り付けると、後退翼が変化したときに追従できるようにピポット付きのパイロンにしないといけない。ところが、固定式の内翼に兵装パイロンを取り付ければ、そんな気遣いは要らない。
面積が違う主翼を試す
このほか、基本的な平面型は同じであるものの、面積が異なる主翼を同時並行的に試した事例もある。それが、第2次世界大戦中に大活躍したドイツの戦闘機、フォッケウルフFw190。開発の過程で、面積が異なる2種類の主翼を用意した。
いうまでもなく、主翼が大きくなれば翼面荷重が小さくなり、一般的傾向として運動性の面では有利である。しかし、速度性能を最優先するのであれば、主翼が小さく、翼面荷重が大きい方が有利である。そこで、実機を使って実際に操縦してもらい、判断の材料にしようと考えた。
その結果、面積が異なる2種類の主翼を備えた機体を実際に造り、飛ばすことになった。そして、大きい主翼を備えるモデルが採用された。最高速度は少し落ちるが、要はトータルバランスということであろうか。
なお、翼端をちょん切ったり延ばしたりして、翼幅を変えたモデルをいろいろ用意した事例もある。事情はさまざまだが、スーパーマリン・スピットファイアの場合、低空性能を重視したり、高空性能を重視したり、といった事情が絡んでいた。純粋に趣味的観点からすると、翼端をストレートにちょん切った低空性能重視のLF型は、そこだけ角張っていて「なんだか、スピットファイアらしくない」のだけれど。
著者プロフィール
井上孝司
鉄道・航空といった各種交通機関や軍事分野で、技術分野を中心とする著述活動を展開中のテクニカルライター。
マイクロソフト株式会社を経て1999年春に独立。『戦うコンピュータ(V)3』(潮書房光人社)のように情報通信技術を切口にする展開に加えて、さまざまな分野の記事を手掛ける。マイナビニュースに加えて『軍事研究』『丸』『Jwings』『航空ファン』『世界の艦船』『新幹線EX』などにも寄稿している。