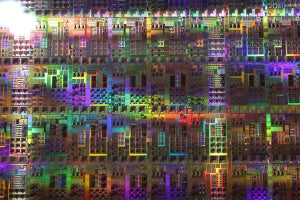Rapidus(ラピダス)とシンガポールQuest Global Services(クエスト・グローバル)は3月25日、ラピダスが提供する2nmプロセスのファウンドリサービスを提供する顧客向けに、クエスト・グローバルが半導体設計を支援することを目指す協力覚書(MOC)を締結したことを発表した。
パイロットラインは予定通り2025年4月より稼働
ラピダスはビジネスモデルとして、「設計ソリューション」「前工程」「後工程」を三位一体で提供することで、他社よりも早く半導体デバイスを提供する「RUMS(Rapid and Unified Manufacturing Service)」を提唱し、これまでに半導体前工程工場「IIM-1」の建設をはじめ、後工程として研究開発拠点「Rapidus Chiplet Solutions(RCS)」を、IIM-1近くのセイコーエプソン千歳事業所内に開設するなど、ハードウェア側の取り組みを中心に推進。IIM-1については、製造装置の搬入を終えており、当初の予定通り2025年4月より、パイロットラインの各種設備や装置の稼働を行っていける状態にあるという。
今回の協業は、残る設計ソリューションを強化することを目的としたもの。ラピダスの小池淳義 代表取締役社長は「この3つが組み合わされることで、RUMSが実現される」ことを強調。これまでのDFM(Design for Manufacturing)と、設計のための製造であるMFD(Manufacturing For Design)を組み合わせ、設計と製造を同時最適化する「DMCO(Design for Manufacturing and Co-Optimization)」を実現するためには、設計側のノウハウも重要となることから、そうした半導体設計の高速化を実現する設計支援を担うとして、さまざまな半導体設計支援をグローバルに展開してきたクエスト・グローバルをデザインハウスのパートナーとしてエコシステムに参画してもらうこととなったとする。
-

DMCOの実現には製造からフィードバックされたデータを設計に活かす必要があり、そうした設計の肝ともいえる部分をクエスト・グローバルが支援することで、顧客の開発負担の軽減と開発速度の向上を期待することができるようになる
「今回の協業の目的は、顧客それぞれのニーズに応じた半導体のカスタム化を進めながらも、開発期間の短縮を実現すること」(小池氏)であり、それを実現するうえで重要になるのがデザインハウスの存在だとする。


IDM、水平分業、RUMSのビジネスモデルの違い。RUMSで重要になるのは、Rapidusが1社で丸抱えするのではなく、エコシステムの中で、それぞれが連携し、強みを共有するところにある。その中でクエスト・グローバルは「デザインハウス」に位置づけられる
世界の半導体設計を縁の下で支えるクエスト・グローバル
クエスト・グローバルそのものはオフショア企業であり、航空宇宙・防衛」「自動車」「エネルギー」「ハイテク」「医療機器」「鉄道」「半導体」「通信」という8つの業界を中心にプロダクトエンジニアリングサービスを提供してきた。同社の共同創業者 兼 最高経営責任者(CEO)であるAjit Prabhu(アジット・プラブ)氏によると、現在、従業員は全世界で約2万1000人ほどで、各業界に精通したエンジニアが、設計・開発から製造、MRO(Maintenance Repair and Operations)に至るまで、顧客の製品のライフサイクル全般をサポートするビジネスを展開しているという。
このうち、半導体分野の専従エンジニアは約2000名超。これは半導体回路設計と半導体製造装置開発の両方を合計した数だが、そのほか、自動車や通信など、ASICを活用する産業分野にも半導体設計に従事するエンジニアがおり、全体で3000名以上が関わっているという。
ただし、同社はオフショア企業であるため、自社の半導体デバイスのブランドを有していない。今回の協業においても、あくまでラピダスの2nmプロセスを活用して半導体デバイスを製造する顧客の半導体回路の設計を支援するという役割となる。協業内容は今後、詳細を詰めていく予定としているが、大枠としてはこうしたラピダスの顧客が設計した半導体回路を実際にテープアウトさせ、製造ラインに流し、そこで得られたウェハごとのパラメータを踏まえて、回路に修正を加えて性能を高めるチューニングといった部分を担うことが見込まれている。
半導体の設計と一言で言っても、回路構成を決定する論理設計から始まり、その後、そうした論理式や状態遷移表などから論理回路を作るための論理合成を行い、回路レイアウト、配置・配線といった複数の手順を踏んで、ようやくそれがフォトマスクに描画され、それをもとに前工程の製造ラインでシリコンウェハに回路が形成されることとなる。この一連の回路設計作業だけで場合によっては2~3年かかることもあり、しかも製造も回路規模などにもよるが前工程だけで数か月から半年、場合によっては1年近くかかる場合もある。しかも、最終的に性能評価を行い、求めるパフォーマンスが出ていなければ、回路設計に戻って1からやり直すというリスクもある。RUMSでは、この設計から製造までの一連の流れをデータで結び付けることで、手戻りを少なくし、また手戻りがあったとしても、それまでの製造データなどを踏まえて、どのように回路を修正すれば良いかを短い時間間隔で導き出して、最適解にたどり着くことを目指している。そうした意味でも、半導体回路設計に長けているエンジニアを多く抱えるクエストグローバルがパートナーとなることが重要となる。
Prabhu氏は、ラピダスに協力するエンジニアの数を初期で500人ほどと見積もっている(日本国内で抱える数ではなく、インドなど海外のエンジニア含む)。また、日本で雇用するエンジニアの数も、今後5年間で倍増させる計画を打ち出し、ラピダスやほかの日本のパートナーとのビジネスの拡大に備えるとする。
さらに、グローバルなエンジニアネットワークを形成しており、ラピダスが想定している北米の西海岸のAI半導体企業などにも人材を派遣する体制も構築することも考えているとするほか、ラピダスの2nmプロセスを活用する顧客が増えれば、より多くのエンジニアリソースをラピダスに振り分けることも考えていることを語っている。
なお、小池氏は「今日のパートナーシップは第一歩」と説明するが、それでも半導体の設計支援として数百人規模のエンジニアリソースを確保したこととなり、「顧客に満足してもらうためにも、この連携は重要」(同)と、その意義を強調。今回の連携が、すでに水面下で進めている商談の成立に向けた後押しとなるとするほか、ラピダスとして気づいていなかった(クエスト・グローバルが付き合いのある)顧客の紹介につながる可能性もあるとし、いよいよ4月より稼働するパイロットラインでの半導体製造含め、今後の事業の立ち上げ・拡大を推進していきたいとしている。