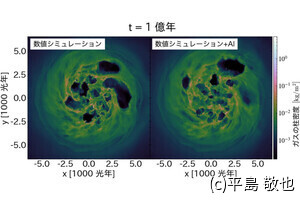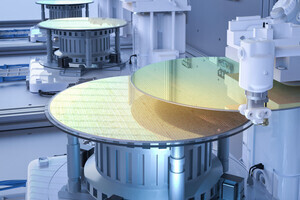プロツールと呼ばれる、製造業や建設現場で使われる工具や間接材の卸売業であるトラスコ中山は、直近の10年で売上が2倍、25年で見れば3倍という成長を遂げている。同社 取締役 経営管理本部 本部長 兼 デジタル戦略本部 本部長 兼 オレンジブック本部 本部長の数見篤氏は、在庫拡大戦略を中心とした、顧客目線でのDXを推進してきたことが成長の理由だと話す。
8月22日~23日に開催された「TECH+EXPO 2024 Summer for データ活用」に同氏が登壇。サプライチェーン全体の利便性向上を目指したという同社の“顧客目線DX”について解説した。
在庫はリスクではなく成長の源泉
講演冒頭で数見氏は、同社が現在60万点を超える在庫を保有していることを紹介し、「在庫はリスクではなく、むしろ成長の源泉だと考えている」と話した。一般的には在庫の回転率を高め、在庫をできるだけ持たないようにすることが重要だとされているが、トラスコ中山の考え方はむしろその逆だ。
それでも同社の売上はこの25年間で約3倍に伸び、ここ数年は売上、利益ともに過去最高を記録し続けている。これは“トラスコなら何でも揃う”ということを目指して在庫を増やし続けてきた結果なのだ。在庫があるということを顧客から見れば、同社に問い合わせれば欲しいものがすぐ手に入る可能性が高いということを指す。そのため、なにか欲しいものがあれば“まずトラスコに聞いてみよう”となる。よく使われる売れ筋のものばかりではなく、巨大な三角コーンや12メートルのハシゴ、超巨大スパナといった、まれにしか売れないような商品も保有しているのはこのためなのだという。
したがって事業規模の割に在庫金額は大きく、競合他社の約2.7倍にあたる508億円にもなるが、今後は100万点を目指して在庫をさらに増やす予定だ。そのために設備投資も行っており、物流センターには自走型搬送ロボットやバケット自動倉庫、高速自動梱包出荷ラインなども導入。莫大な在庫を効率的に管理できるようにしている。
在庫管理システムや工具版“置き薬”で顧客の利便性を向上
これほど常識外の在庫を持つことができるのは、トラスコ中山が積極的にデータ活用を行っているためだ。その1つが「ZAICON」と呼ばれる在庫管理システムである。従来は物流センターの担当者が目視しながら、経験や勘によって手作業で在庫調整や発注を行ってきた。その過程では品切れが発生することもあったが、長年の実績データも積み上がった。ZAICONはこのデータを活用することで、1品ごとの需要を予測して在庫を管理している。地域ごとに、どんな商品がどのように使われているかを分析し、最寄りの物流センターや在庫保有支店に必要だと思われる商品の在庫量を予測計算。さらにそれが品切れにならないよう発注管理まで自動的に行われるシステムになっている。
“富山の置き薬”の工具版とも言える「MROストッカー」と呼ばれる取り組みも行っている。工場や工事現場などでは、1つの工具、1本のネジが足りないだけで作業が止まってしまうため、不足したものがある場合にはすぐに入手しなければならない。それに応えるため、よく使われる工具などの商品をユーザーの手元に置いておくものだ。ユーザーはMROストッカーに置いてある商品のバーコードをスマホでスキャンし、数量を入力するだけで必要なものをすぐに使うことができる。そしてそのデータは瞬時に同社や販売店にも共有されるため、使った分がすぐに補充される。いざというときに必要なものがすぐ手に入るこのサービスは「かなり好評」だと数見氏は話した。
在庫出荷率の高さが価値になる
同社がKPIとして何よりも重視しているのは、在庫出荷率だ。これは注文されたものを在庫から出荷した比率のことで、現在の在庫出荷率は92.1パーセントとなっている。つまり100個の注文のうち、92個以上は同社物流センターからすぐに顧客に届けられたということになる。数見氏は「1個でも多く物流センターからすぐに商品を届けられることが、私たちの価値の1つ」だと語る。だからこそ、在庫を拡充していくという考え方につながるのだ。
その一方で、在庫が増えれば商品を廃棄せざるを得ないこともある。廃棄率を0にすることはできないが、最小限にするための取り組みも行っているそうだ。その結果、現在の廃棄率は0.13パーセントという低い値に抑えられている。
サプライチェーン全体の利便性向上を目指したDXの事例
売上が拡大している理由は、「とにかく顧客目線のDXを徹底したこと」だと数見氏は言う。それも、仕入先、販売店、ユーザーも含めたサプライチェーン全体の利便性を向上させることを重視してきたそうだ。サプライチェーンで川上にあたる仕入先のメーカーの情報は同社だけでなく販売店やユーザーとも共有するために、ユーザーの情報はメーカーに伝えることを目的に、様々な取り組みを行っている。
例えば販売店向けには、「即答名人」と呼ばれるAI自動見積システムを導入している。従来は全国の営業所への電話やFAXでの問い合わせに対し、社員が価格や在庫を調査して電話やFAXで回答していたが、問い合わせは毎月3万件もあり、さばききれないこともあった。朝一番に見積を受けても回答が夕方になってしまうと、競合他社にその顧客を奪われることもあり得る。そこで価格計算や在庫調査などを全て自動化し、Webで見積を受けてから約5秒で回答を送れるようなシステムをつくった。顧客のストレスを軽減できたのはもちろん、早く回答することで受注率が高まることも分かってきたそうだ。
販売店とユーザーに向け、商品検索サイト「トラスコ オレンジブック.Com」も開設している。顧客に対しては、商品を素早く探すことができ、24時間365日注文ができる利便性を提供、その一方で社内の受注業務も軽減することができる。また商品データベースの「Sterra(ステラ)」は、メーカーの利便性を図るものだ。画像や動画も含めた商品のデータを、メーカーが簡単にデータベースに登録できるポータルをつくり、そのデータを販売店やユーザーへ共有できるようにしている。これらの施策により、現在では販売店からの受注の86.3パーセントがシステム経由になっているという。
最速、最短、最良の納品の実現を目指す
現状は、顧客が欲しい商品を検索したり問い合わせたりして注文するという流れだが、今後はデータを活用してさらに短時間での納品を目指している。目標は、「『最速』『最短』『最良』の納品。ベストなモノが、もうそこにある」(数見氏)という状態だ。例えば前述のMROストッカーであれば、顧客の情報を基に需要予測を行い、必要になるであろう商品を先読みして置いておくなどすれば、利便性をさらに高めることができる。
最後に数見氏は、「DXというとどうしても業務効率化や業務の自動化など社内に目が向きがちだが、顧客に目を向けたDXこそ重視すべき」だと話した。
「どんな企業にもお客さまがいます。そのお客さまにとって良いことを実現するために、デジタルの力、データの力を駆使することが重要です。私たちもそうやって独創的な競争力を高めていきたいと考えています」(数見氏)