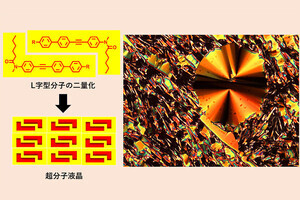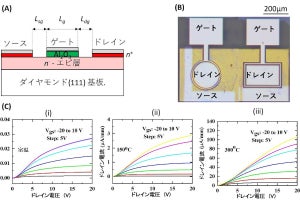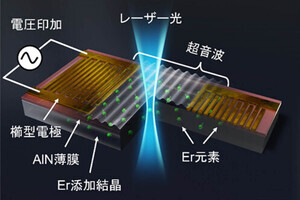東京大学(東大)と科学技術振興機構(JST)の両者は1月29日、非対称な棒状分子がすべて同一方向にならんだ極性単結晶薄膜を塗布形成できる新たな有機半導体を開発したことを共同で発表した。
同成果は、東大大学院 工学系研究科 物理工学専攻の井上悟助教、同・長谷川達生教授らの研究チームによるもの。詳細は、多様の分野の基礎から応用までを扱う学際的なオープンアクセスジャーナル「Advanced Science」に掲載された。
井上助教や長谷川教授らの研究チームは、薄膜トランジスタの構築に適する優れた層状結晶性を与える塗布型有機半導体として、キャリア輸送の源になる「π電子骨格」を、柔軟な「アルキル(-Cn)鎖」により非対称に置換した棒状分子が極めて有効なことを、これまでの研究で明らかにしている。
非対称分子が同じ向きに並んで得られる単分子層は、層に垂直な向きに極性を持った配列構造を有する。結晶化の際には、分子がすべて反平行な向きにならんだ層同士が対になって積層する2分子膜型構造を取り、単分子層の極性は互いに打ち消し合う。研究チームは、もしこれら極性の単分子層をすべて同じ向きに積み重ねることができれば、結晶全体で極性を持てる可能性があるとする。
そして今回、2分子膜型の積層様式の安定化は、π電子骨格の末端同士の相互作用が、アルキル鎖の末端同士の相互作用よりも強いことに理由があることが判明。そこで今回の研究では、π電子骨格の末端同士が近づく際に立体障害となるメチル基を骨格末端に導入し、2分子膜型の積層様式を抑制する仕掛けを施した有機半導体を新たに開発したという。
今回の研究では、優れた半導体を与える基本的なπ電子骨格である「BTBT」の両端に、「パラトリル(pTol-)基」とアルキル鎖が連結された分子構造を持つ有機半導体「pTol-BTBT-Cn」が開発された。なお同半導体は、2分子膜型構造を取る「Ph-BTBT-Cn」のフェニル(Ph-)基の末端にメチル基を付与する分子設計で開発された。
そしてアルキル鎖の長さが異なる(n=5~14)分子を合成して解析を行ったところ、ある長さ以上(n≧9)のアルキル鎖で置換した場合、棒状分子の向きが層に対して垂直かつ同じ向きに揃った極性の単分子層の形成が確認されたという。これら単分子層内の分子配列は、アルキル鎖の長さによらずほぼ同一であるものの、同鎖の炭素数が奇数の場合は2分子膜型の反極性結晶(エレクトレット)に、また偶数の場合は単分子層がすべて同じ向きに積み重なった極性結晶となることがわかったとのこと。極性を意味する「ポーラー」と、分子層内におけるBTBTの配列が「ヘリンボーン構造」であることから、この分子配列構造は「極性型層状ヘリンボーン構造」と命名された。
-
(A)pTol-BTBT-C10の分子構造(上)と、アルキル鎖の炭素数の偶奇の違いによって形成される極性/反極性型構造の模式図。紫の矢印は、各分子層の極性の向き。アルキル鎖が奇数の場合には反極性型、偶数の場合には極性型の層状結晶が形成される。(B)単結晶X線構造解析によって得られたpTol-BTBT-C10の極性結晶構造(水素原子は省略)(出所:共同プレスリリースPDF)
研究チームは次に、分子層同士の積層様式がこのような顕著な偶奇性を示す理由を調査。その結果、単分子層の最表面の形状が、アルキル鎖の炭素数の偶奇により大きく変化するためであることが突き止められた。「オールトランス構造」を取るアルキル鎖の末端の炭素-炭素間の結合は、炭素数の偶奇に依存して2種の方位を取ることが知られている。今回の研究で用いられた単分子層の最表面の形状は、アルキル鎖の炭素数が偶数の場合に、π電子骨格側のパラトリル基先端からなる最表面の形状に類似しており、これらがピタリとはまることで効果的に分子層間の相互作用が働き、極性結晶が安定化することが解明された。
-
極性形積層様式の起源、層面の立体形状の違い。(A)pTol-BTBT-Cnの単結晶構造における各分子層の、トリル基側とアルキル鎖側の分子層面の原子配置(中央)。(B)アルキル鎖が奇数の場合の層面とトリル基面との噛み合わせを想定した模式図。図は空間充填モデルで描画されており、球が占有している領域が、実際に原子が空間を占有する体積。アルキル鎖面がトリル基面に対して深くまで噛み合うことができず、極性結晶構造の形成には不利となる(実際には2分子膜型構造を形成)。(C)アルキル鎖が偶数の場合の層面とトリル基面との噛み合わせが示された図。実際に観測されている結晶構造から描画したものであり、それぞれの面の隙間を埋めるように原子が密に充填されていることがわかる(出所:共同プレスリリースPDF)
続いて今回得られた材料について、常温・常圧下での塗布製膜による薄膜結晶化が検討された。すると、基材上に厚さが10~50nm、大きさが数mm角に及ぶ大面積の単結晶薄膜が形成できることが確認された。さらに、単結晶薄膜の極性とその分極方向も調べた結果、単一の単結晶ドメインに波長800nmのレーザー光を照射すると、波長400nmの強い第二次高調波発生(SHG)光が観測され、その強度は基板の傾斜角(レーザー光の入射角)の増加と共に強くなることが判明。これにより、層間方向に自発分極があることが確認できたという。
-
pTol-BTBT-Cn結晶薄膜の非線形光学応答性。(A)カバーガラス上に塗布製膜で作製された単結晶薄膜を用いたSHG応答性評価の模式図。SHG応答が観測される場合には、波長800nmの光を入射することで、その半分の波長となる波長400nmの光がSHG光として検出される。(B)基板を傾斜させた場合のSHG光の強度変化。黒丸は極性結晶薄膜(n=12)、白丸は非極性結晶薄膜(n=11)での測定結果。今回開発された材料では、基板に対して垂直方向に分子の向きが揃った(極性を持った)薄膜となるため、基板を傾けることでSHG光が観測されるようになる(出所:共同プレスリリースPDF)
そうした結果を受け、これら単結晶薄膜を用いた電界効果トランジスタを作製した結果、極性結晶を与える分子配列構造は、トランジスタ性能を改善する上でも有効なことが確認されたとする。pTol-BTBT-Cnの、nが偶数で極性結晶を形成するものと、奇数で反極性結晶を形成するものからなるトランジスタの特性もそれぞれ調べたところ、6~10cm2/Vsのキャリア移動度が得られたとした。
さらにスイッチング性能の指標となるSS値は、反極性結晶の場合と比べ極性結晶の場合により優れた値(100mV/dec)を示すことが確かめられた。これは積層様式の違いにより絶縁性のアルキル鎖層の厚みが大きく異なることが、電極からのキャリア注入などに影響したためと考えられるという。
研究チームは今後、極性結晶を構築するために有効だった分子設計に基づき、分子層間の相互作用を制御するための置換基のさらなる検討を進めていくとのこと。それと同時に、それらを多種のπ電子骨格に適用することにより、結晶の極性を自由自在に制御可能な新たな結晶工学手法へと発展させていく計画とする。またそれらの材料開発と共に、極性結晶を応用したオプトエレクトロニクス・ピエゾエレクトロニクスに有用な新たなデバイス機能の開発を進めていくとしている。