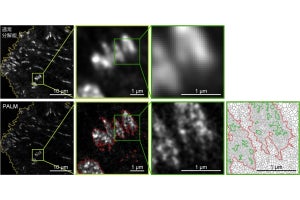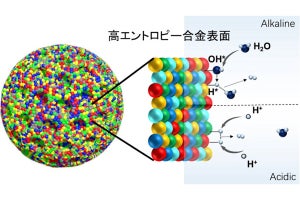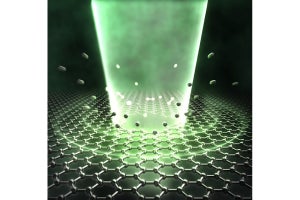京都大学(京大)は8月2日、さまざまな気体分子が混合したガス中から、温室効果ガスである二酸化炭素(CO2)に対してのみゲートを開いて吸着するフレキシブル多孔性材料の開発に成功したことを発表した。
同成果は、京大 物質-細胞統合システム拠点(iCeMS)の北川進特別教授、同・大竹研一特定助教、同・Yifan Gu特定研究員(現・中国同済大学 教授)に加え、中国同済大学の研究者も参加した国際共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。
工場や発電所、化学プラントなどから排出される廃棄ガスやオフガスなどには、CO2以外にも水素(H2)、窒素(N2)、一酸化炭素(CO)、酸素(O2)、アセチレン(C2H2)、エチレン(C2H4)、エタン(C2H6)など、多様な成分が含まれている。効率良く目的の成分のみを分離する技術が産業と環境問題の両面から求められているが、CO2の選択的な回収は容易ではないという。それは、CO2が中程度のサイズと吸着性を持っていることが理由で、従来はエネルギー効率の良くない化学吸着法などが用いられていた。
近年、エネルギー効率が高いとされるガス分離手法を実現できる可能性があるとして注目されているのが、多孔性材料を利用した吸着分離法だ。同手法では、微細なナノサイズの細孔を持つ多孔性材料を利用して、混合ガスから特定のガスのみを吸着するというものである。
しかし、従来の多孔性材料を用いたガス分離の研究では、主に2成分混合ガスに焦点が当てられており、多数の類似成分ガスから単一成分のみを分離する多孔性材料の研究開発はほとんど行われておらず、そのような材料の設計指針が知られていなかったという。そこで研究チームは今回、構造柔軟性を持つフレキシブル多孔性配位高分子(PCP)および金属有機構造体(MOF)に着目したとする。
PCP/MOFは、有機分子と金属イオンをパーツとした結晶性の多孔性材料であり、規則的に配置された無数の細孔を持つ。一般的な多孔性材料とは異なり、PCP/MOFは細孔構造をデザインすることで機能性を持たせることが可能だ。そして、iCeMSの北川特別教授らが開発したのが、ガス分子の吸着に応答して構造を柔軟に変化させてさらに吸着させるという性質を持つ「フレキシブルPCP/MOF」だ。
フレキシブルPCP/MOFは、ガスの吸着前には細孔が閉じており、一定の圧力に達すると構造を変化させて細孔を拡大させ、ガスを吸着するという特性を持つ。この特性は「ゲートオープン挙動」と呼ばれ、圧力スイング法による効率的なガスの分離と回収に活用されることが期待されている。しかしこれまで、ゲートオープン挙動を利用したガス分離では、狙ったガス分子以外のガスも一緒に吸着しやすくなるという選択性の制御に課題があったという。そこで今回の研究では、設計と、選択的なゲートオープン挙動を相乗的に利用する構造の開発に取り組んだという。