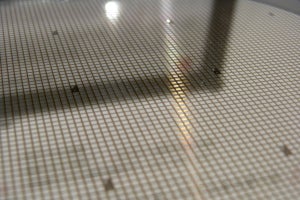インフィニオン テクノロジーズ ジャパンが7月6日に開催したプライベートカンファレンス「Infineon MCU Partner & Solution Day 2023」。この基調講演にOmdiaのシニアコンサルティングディレクターの南川明氏が登壇。2023年以降の半導体業界、ならびに日本の半導体産業の方向性の見通しについて語った。
半導体を含むエレクトロニクス産業は2023年7月時点で、さまざまなアプリケーションで在庫調整が進められている状況で停滞期にあると言える。また、中国が8月よりレアアースの輸出制限を実施することを公表するなど、市場に混乱が生じている。南川氏は「これは予測された動きで、これからどうなるかというと、特にコバルトに関しては日本がかなり消費しており、それなりの影響がある」との見通しを示すほか、「ガリウムも相当影響がでてくると思っている」ともし、「おそらく輸出制限は現実に行われる。そのため、いち早く中国以外へシフトしていく必要がある。実際には在庫がそれなりにあるので、数か月から半年程度は持つとは思うので、その間に、そうした動きを進める必要がある」と、速やかな中国以外の入手先確保に動く必要があることを強調する。
2023年の経済は米国がけん引役に
2023年も残り半分となったが、世界経済のけん引役になるのは米国だと南川氏は指摘する。背景には53年ぶりの低水準を記録している失業率となっているにも関わらず、平均時給は高止まりしており、また米国企業のフリーキャッシュフローも過去最高に近いレベルとなっていることが挙げられる。「米国は失業率とリセッションに相関関係があり、失業率が上がり始めてしばらくするとリセッションが始めるというのがパターン。それを踏まえれば、現在の米国はそう簡単にはリセッションに入らない」と、好況が続くとの見立てを示し、「米国企業が次に考えていることは、現在はまさに非連続の成長の迫間にあるということ。GAFAMの多くもこれまでのビジネスモデルが立ちいかないとの見方から、大きく転換しようとしている。それが生成AIやメタバースの活用で、それを収入源としていこうという取り組みで、これが第4次産業革命につながっていく」と指摘。その実現のためには、IoTで現実のデータを大量に収集し、ビッグデータとしてそれを活用し、AIを教育し、分析させ、それをサービスにつなげるということが必要であるとし、まさに今こそがそうした大きな転換点を迎えているタイミングであるとした。
「米国企業は潤沢なフリーキャッシュフローを見てわかるように、投資の準備ができている段階で、その最適なタイミングを待っている。おそらく、それは2024~2025年が実施のタイミングになる」とし、そうした動きが、新たな経済の流れを生み出していくことにつながると説明する。
変化する世界経済が日本に追い風
そうした大きな変化がくるであろう世界経済の中において、日本の半導体産業に追い風が吹いているという。大きな要因は円安に大きく振れてきていること。
「企業の経常利益率は2014年以降に上がり始めている。製造業にとって円安はプラス要因が大きい。1ドル130円台くらいが日本の製造業によってのスイートスポットと言われているが、円安により輸出比率の高い製造業の環境が良くなっているほか、全体的にもプラス要因になっており、海外からの投資を呼び込む要因にもなっている。日本政府も投資誘致を支援しており、そうした取り組みもあり海外の多くの企業が何かしらの拠点を設けようという動きがでてきた」と南川氏は、円安が日本の製造業に恩恵をもたらすだけでなく、海外企業にとっても魅力的であり、日本への投資が進むことが期待されるとする。
また、半導体市場を取り巻くトレンドとしても、コロナ禍を経て、各国政府が2050年までにカーボンニュートラルの実現を目指す動きを見せるなど、これまでの個人消費頼みであった半導体の消費量が、そうしたいわゆるグリーントランスフォーメーション(GX)ならびにデジタルトランスフォーメーション(DX)という政府の取り組みでも消費されることが期待されるようになる。
そのため、「主要国のグリーン関連投資を見てみると、複数年にまたがる形だが、総額で500兆円規模が投資されることが期待される。この規模がどのくらいかというと、2008年のリーマンショックから回復するのに世界が投じた金額が200兆円と言われている。そのうちの70兆円が当時は中国が投資をしたわけだが、今回は米国を中心に主要国がカーボンニュートラルを旗印に大きな投資を行っていく。当然、半導体産業にもプラスの影響がでてくる」とGX・DXに対する投資がこれからの半導体市場のけん引役の1つになっていくとする。


これまでの半導体市場はPCにしろスマホにしろ個人消費がけん引役となり、その市場の浮き沈みの影響を受ける形で市場のサイクルが生じていたが、コロナ禍以降、世界的なデジタル化、そして脱炭素の流れにより、そこに政府レベルの半導体消費が加わることになり、半導体市場は長期安定した成長期に入ることが期待されるという
主要アプリごとに在庫調整の終了時期はまちまち
これまで半導体業界をけん引してきた主なアプリケーションはスマートフォン(スマホ)、PC、サーバで、スマホが世界の半導体消費の30%ほどを、PCが15%ほどを、サーバが10%強をそれぞれ占めてきた。いずれも市場としては低調だが、それぞれの回復時期の見通しについては、「スマホは秋ごろに半導体の在庫調整が終わる見通し。PCは秋以降までかかる見通し、そしてサーバは秋には回復する見通し」としている。中でもサーバについては、2023年の秋以降は急速に成長することが期待されるという。理由は「生成AIをビジネスとして活用できるようになるためには、3年程度、前年比25%増くらいのペースで投資を行って行かなければ、実用的なものがでてこない。生成AIに必要なプロセッシングパワーは検索に対して10倍ほどとも言われており、2027年までに現在の3倍以上のプロセッシングパワーが生み出せないと、本格的なビジネス活用可能なAIサービスにたどりつけない。それが年間25%増の投資が必要という判断の根拠」としており、AIサーバ向けGPUを中心に積極的な購入が進むことが期待されるとしている。
また、自動車の半導体消費量も増加傾向にある。xEV市場が伸びているが、1台あたりの半導体の平均消費額はガソリン車で平均550ドルであったのが、バッテリー式電気自動車(BEV)では平均1600ドル、テスラは2500ドルと3~5倍ほどに金額が跳ね上がる。「今でも自動車メーカーは半導体不足という話をしているが、内訳はパワー半導体がメイン。IGBTやSiCが使われていくことになり、そこにロジックが組み合わせていく形になる」と、自動車のエレクトロニクス化も追い風になるとする。
世界がうらやむ日本政府の半導体政策
6月6日に経済産業省(経産省)は、2021年6月に策定した「半導体・デジタル産業戦略」を、現在の世界情勢の変化を踏まえた改訂版として公表した。
2021年に公表されたものでも半導体支援として、IoT用半導体生産基盤の緊急強化を第1段階(Step1)に、日米連携による次世代半導体技術基盤の日本での確立を第2段階に(Step2)、そしてグローバル連携による将来技術基盤の構築を第3段階(Step3)としていたが、この2年の間に、Step1としてTSMCを誘致、Step2としてRapidusの設立がなされた。今回の改訂でポイントとなるのがStep3 で、「半導体を使う人を育てよう、というのがポイント。特にAI半導体を日本で設計して、作れるようにして、それをデータセンターや自動車などに応用していこうという動き。そこに政府の支援が入ることになる」と南川氏は今回の改訂のポイントを説明する。
「日本としてはSiCやGaNといった次世代パワー半導体の育成も明確化している。それは日本のパワー半導体メーカーだけが対象ではなく、海外のメーカーであっても、日本に投資をして、一緒にやってくれるのであれば支援を行うという話。また、もう1つの技術として、チップレット分野にも注力していく。先端プロセスを日本でもやるが、そこには競合としてTSMCやSamsungなど、先行する強い企業がいるので、そこだけで1番を目指すのではなく、後工程で複数のチップを1パッケージ化するチップレットの分野、日本には材料メーカーや装置メーカーも多いので、そこに注力することで強みを生み出していくという姿勢を打ち出している」と、単に先端ロジックを日本で製造することだけが日本政府としての思惑ではないことを指摘。その判断に至る背景には、コンピュータサービスの国際収支を見ると、日本のほとんどの企業が海外のデータセンターのサービスを借りており、その費用は2021年度で約1.8兆円。これが2030年には8兆円ほどに膨れ上がることが予想され、サービス収支が悪化していく可能性があるためだという。「この金額は石油の輸入金額よりも大きい。日本にデータセンターを作って、活用していくことで、この収支を改善しようというのが理由の1つだ」と説明する。
ただし、すべてを実現するためには日本政府だけが資金提供しても足りないため、民間の参加も税制優遇などを活用して呼び込むことで、官民合わせて150兆円ほどの投資を今後の10年で呼び込み、日本として、各地域に分散される形でデジタルインフラを構築。各地の大学とも連携し、半導体教育をそれぞれの地域で受けられるようにするといったことも注力していくことが予定されているという。
こうした矢継ぎ早に政策を推し進めている現在の日本の動きを海外勢も認知しており、Omdiaにも海外企業を中心に、「なぜ日本はこれほど動きが早いのか」といった問い合わせが来ているという。
すでに日本は過去2年の間に約2兆円強の半導体育成プログラムをスタートさせ、国内で工場の新増設などを行う半導体メーカーへの補助金支給や、Rapidusへの支援などといった動きを見せている。一方、日本に先立って米国では「CHIPS and Science ACT of 2022(CHIPS法)」を制定する動きを見せたが、実際には審議が難航、ようやく申請の受付が始まった形で、欧州も米国CHIPS法と似たような法案を策定したが、いずれも動きは日本に比べて遅く、「スピード感は日本の方が圧倒的に速い。過去にないくらい早い」と南川氏も絶賛。「ただし、早いから上手くいくかと言われると、失敗するプロジェクトもあるかもしれない。しかし、それだけのスピード感で動いていることは海外からも驚きをもって受け止められている。その驚きを上手く利用して、海外からの投資も呼び込み、積極的に動いていくことがこれからの日本の存在感を増すために求められる」と、日本の積極的な動きを武器として海外に示し、投資などにつなげるべきだとした。
なお、南川氏は「非連続な成長がこれから始まる。今はそのちょっと手前。これからの成長のけん引役はGX・DX、そして生成AI。これらの実現のための投資は2024年より本格的に進む。米国はそのための資金をすでに有している。2023年は後半もある程度暗い状況が続くが、その後は明るい時代が訪れる」と、2023年後半以降の見通しを示し、そうした中、日本の半導体産業に力を付けるために動き出している日本政府の取り組みを含め、この数年を好機に変えるために日本の半導体産業を応援していきたいとしていた。