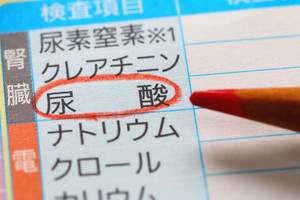岡山大学、分子科学研究所(分子研)、京都大学(京大)の3者は4月3日、尿路結石形成に関わるシュウ酸分解菌が、腸内からシュウ酸を吸収する時に利用するシュウ酸輸送体の立体構造を、大型放射光施設のSPring-8を用いて解明したと共同で発表した。
同成果は、岡山大 学術研究院 医歯薬学域(薬)の山下敦子教授、分子研の岡崎圭一准教授、京大大学院 医学研究科の島村達郎特定准教授、理化学研究所 放射光科学研究センターの平井照久チームリーダー(研究当時)らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。
尿路結石は、3大激痛の1つともいわれる激しい痛みを引き起こすことで知られている。この結石は、体内のシュウ酸の量が過剰になることで、血中に含まれるカルシウムと不溶性の塩を形成してしまうのが原因だ。またシュウ酸そのものは、野菜やお茶、ナッツ類などの食品から日々摂取されている。
腸内細菌の1種であるシュウ酸分解菌「O.formigenes」は、ヒトのシュウ酸代謝と深い関わりを持つ。同菌は、腸内のシュウ酸を唯一の炭素源として吸収し、その分解によってエネルギーを得て生息している。そして同菌がシュウ酸を分解してくれるおかげで、尿路結石が形成されるリスクが減少しており、同菌は善玉菌とされる。実際、何らかの事情で腸内に同菌がいなくなるか、または少なくなってしまうと、尿路結石形成のリスクが高くなることが知られている。
そのO.formigenesに存在するシュウ酸輸送体「OxlT」は、この過程の鍵ともいえる、シュウ酸の菌体内への吸収と、その分解産物であるギ酸の菌体外への排出を担う物質だ。この過程は、食品から摂取して消化された多種多様な物質が流れる腸内環境下で起こるが、OxlTがどのようにしてその中からシュウ酸だけを見分け菌体内に取り込んでいるのか、その詳しいメカニズムは不明だったという。そこで研究チームは今回、SPring-8を用いて、X線結晶構造解析によりOxlTの立体構造を解明したとする。