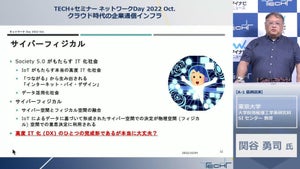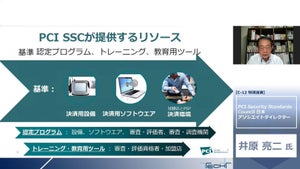国内約370万台の自動車のコネクテッドデータを活用し、事業開発を進めてきた本田技研工業(以下、Honda)。2017年からは「Honda Drive Data Service」として、データを活用した情報分析サービスを提供している。しかし、現在に至るまでには紆余曲折があったという。同社 コネクテッドソリューション開発部 主幹 福森穣氏は、11月10日、11日に開催された「TECH+ EXPO 2022 Winter for データ活用 戦略的な意思決定を導く」で、Hondaがどのようにしてデータを駆使した事業を拡大してきたのかについて紹介した。
【あわせて読みたい】「TECH+ EXPO 2022 Winter for データ活用 戦略的な意思決定を導く」その他のレポートはこちら
「広告は売れないが、データであれば売れるのでは」という仮説
2015年にIT部門から経営企画部門へ異動となった福森氏は、カーナビを活用した広告事業のプロジェクトにアサインされ、ドライブ中に現在地・目的地周辺のグルメや名所などのおすすめ情報をスマートフォンアプリやWebサイトへ配信するサービス「ROAD H!NTS」を開発した。しかし、同サービスは期待どおりに拡大しなかった。「Hondaの車を買った人にしか情報を見てもらえないので閲覧数が低く、広告主にお金を出してもらうのが難しかった」と福森氏はその理由を説明する。
事業自体は上手くいかなかったものの、そこから得られた学びもあった。とある外食チェーンの取締役が、コネクテッドデータの価値を高く評価したのだという。
「当時同社はロードサイド店の強化を開始しており、自動車の流入ルートのデータは非常に有効だと言っていただけました。ロードサイドのチェーン店は売上予測がしにくいという課題を抱えており、ここにコネクテッドデータを活用できれば、課題解決できるのではという期待があったのです。この経験から、広告は売れないが、データであれば売れるのではないかと感じるようになりました」(福森氏)
広告事業からパートナーシップ戦略へと大きく舵を切る
元々、Hondaは10年以上前から事故削減や災害対応に向けたデータ活用を進めていた。例えば、2007年からは、急ブレーキの回数が多い箇所のデータを自治体に提供し、事故防止対策につなげる取り組みを行っており、埼玉県の事例では急ブレーキの回数を約1/3にまで減らすことに成功している。また、東日本大震災の翌日には、自動車の走行実績データを活用した通行実績情報を公開し、復興に貢献した。
しかし福森氏は当時の状況について「あくまで各部署のルーチンに組み込まれた活動というイメージで、注力されていたわけではなかった」と振り返る。こうした状態を「もったいない」と感じた同氏は、2017年ごろにメンバー2人という小規模体制で、データ活用をメインに据えた事業企画の提案をスタートさせた。
「国内約370万台とは、交通量全体のおよそ3~4%を占める数字です。コネクテッドカーからは、速度、走行ルート、走行距離など位置情報に関するデータに加え、ワイパーやエンジンのON/OFF、加速度といった車両状態に関する特有のデータが取得できます。特徴は、車両データがリアルタイム更新できる点にあり、過去データも分かるため、比較も可能です。ペルソナの偏りもなく、全体の大きな傾向は捉えることができます。より多くのお客さまに話を聞けば、さまざまなユースケースが見つかるのではと考えました」(福森氏)
福森氏らの地道な取り組みによって、まちづくりや渋滞対策、交通安全、防災・減災、観光、マーケティングなどにHondaのデータを活用してもらえることが分かってきたが、事業拡大にあたっては、社内のリソース不足が大きな課題となった。そこで同氏が考えたのは、パートナーシップ戦略であった。
当時はスマートシティや都市OS、データ連携基盤などがあちこちで検証されている時期だったため、福森氏は「Hondaが一気通貫で取り組むのではなく、企業間で連携をする将来像が現実的」だという発想に至った。そして、都市OS、建設関連のコンサルティング、データアグリゲーター、レポート提供企業など、さまざまな企業とアライアンスを締結するビジネスモデルへと大きく舵を切ることを決めた。