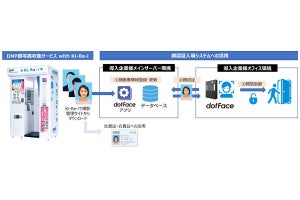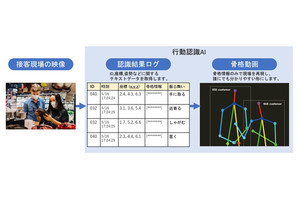デジタル庁は2021年に、デジタル技術が0と1の2進法によって情報を処理することにちなみ、10月10日および11日を「デジタルの日」と定めてさまざまなイベントを開催した。また、2022年以降は「毎年10月の第1日曜日、月曜日をデジタルの日」とし、さらに「毎年10月をデジタル月間」とすると発表していた。
デジタルの日に合わせて、デジタル庁は「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化」に貢献している、または今後貢献すると思われる個人や企業・団体の取り組みを表彰する「good digital award」を発表した。
今回、good digital awardのアート部門で部門最優秀賞を獲得した、大日本印刷(以下、DNP)のDNPコンテンツインタラクティブシステム「みどころシリーズ」を体験してきたので、紹介しよう。
DNPが開発したみどころシリーズは、美術館・博物館 / 図書館 / 文書館といったMLA(Museum、Library、Archiveの各頭文字を取ったもの)の所蔵品などを高精細にデジタル化し、知的な情報と組み合わせることで、作品に対する興味のきっかけを与える目的で開発されたシステムだ。
このシステムでは、デジタル化された作品だけでなくその作品の知的な情報も一緒に鑑賞する機会を提供するので、さらなる興味の促進や作品へのアクセシビリティを高める狙いがあるという。
同社は2019年より、フランス国立図書館(以下、BnF)のリシュリュー館の創設以来初となる12年間にわたる全館改修を行う「リシュリュー・ルネサンス・プロジェクト」に参画し、BnFが所蔵する歴史的遺産の3Dデジタル化とその普及に挑戦してきた。その一環として、2022年9月にはリシュリュー館に開設されたミュージアムに、みどころシリーズの一つである「みどころビューア (R)」を設置し公開した。
今回、デジタル庁が募集したgood digital awardにDNPが応募したきっかけについて、みどころシリーズの開発を主導した田井慎太郎氏に話を聞いた。田井氏はDNPが参画したリシュリュー・ルネサンス・プロジェクトにおいて、デジタルコンテンツの導入に向けたプロジェクトリーダーを務めた。
「DNPとBnFは、昨年デジタルデータを用いた展示会を実施しました。数百名のMLA関係者や企業の方々にこのシステムを見ていただき、その時の反響などから手応えを感じていました。good digital awardの取り組みを知って、私たちが開発したシステムが社会にどのような価値を提供できるのか、どう貢献できるのかを知るために応募しました」と田井氏は語った。
「みどころシリーズ」の開発に際しては、コンセプトの設計に苦労したようだ。近年は美術館や博物館の所蔵品をデジタルデータ化する動きがグローバル規模で加速している。日本は世界の動きからやや遅れを取っているものの、国立国会図書館や文化庁などが主導したプロジェクトが進められている。
そうした中で、デジタル化が進められる歴史的遺産のデータに対して、どのような体験を付与して新たな価値を創造するのか、そのコンセプトを定めるための模索が続いたとのことだ。
大きな転換となったのは、新型コロナウイルスの流行である。BnFとのプロジェクトが走り出した2019年当初は、BnFの所蔵品を東京に運び多くの来場者を迎えて公開する予定だったという。しかし、世界がコロナ禍に突入し展示物の搬送や集客が困難となったのだが、これが結果的に後述の「みどころグラス (R) 」など新しい価値体験のあり方につながった。
田井氏と共に「みどころシリーズ」の開発を担当する、DNPマーケティング本部の平澤公孝氏は「good digital awardの受賞にあたり、私たちの取り組みがこのような結果として評価されたのは非常に嬉しかったです。このシステムが社会にとって役立つと認識されたのだと受け取っていますが、その一方でプレッシャーも感じており、今回せっかく受賞したからには具体的な価値をこれから社会に提供していきたいです」と述べ、改めて気を引き締めた様子だった。