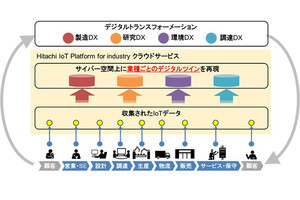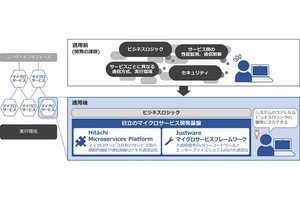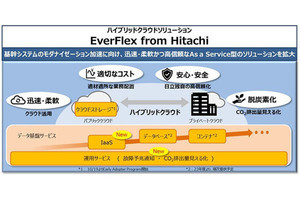日立製作所(日立)のオンラインイベント「Hitachi Social Innovation Forum 2022 JAPAN」が10月25日から27日まで開催されている。同イベントでは、日立が共創パートナー企業とともに、未来に向けて何ができるのか、何をすべきなのか、その戦略とともに先進的な取り組みを紹介している。
25日の講演のトップバッターを務めたのは執行役社長兼CEOの小島啓二氏。同氏は「日立がめざすサステナブルな社会~データとテクノロジーで人々の幸せを支える~」と題した基調講演で、日立が目指すサステナブルな社会と、その実現に向けた取り組みを紹介した。日立が描いている青写真は、いったいどのようなものだろうか。
日立が目指すサステナブルな社会とは?
小島氏は冒頭、「日立が目指すサステナブルな社会は、人々の幸せな暮らしと、健全な地球環境が同時に達成できる社会だ」と説明した。続けて、「これからの社会における人々は、価格や品質以外の点も考慮した意思決定をするようになるだろう。つまり、社会をより良くするための自分らしい行動を選ぶ余地が広がる」と補足した。
-

日立製作所 執行役社長兼CEO 小島啓二氏
昨今、異常気象やパンデミック、地政学上の対立など、世界を取り巻く環境は複雑さを増している。また、日本の円安を筆頭に世界各国でインフレが顕著になっている。小島氏は「当面このような厳しい状況が続くことが予想されるが、この壁を乗り越えた先には新たな成長が待っている。私はそう確信している」と述べた。
その理由として、同氏は「景気後退が起ころうとも、『グリーン』と『デジタル』への対応は、企業にとっての至上命題だからだ。この動きに加えて、Web3.0をはじめとする次世代のデジタル技術が新しい需要を喚起するだろう」と持論を述べた。
1990年代半ばからの時代を指すWeb1.0では、パソコンが普及してブラウザが登場し、誰もが簡単に情報検索と閲覧ができるようになった。そして2000年代半ばから現代までの時代を指すWeb2.0では、スマートフォンが普及してクラウドが登場し、さまざまなSNSにより、個人が世界に向けて情報発信ができるようになった。
そして、2020年からの時代を指すWeb3.0は、プラットフォーマーが個人情報を集中管理していたWeb2.0に対し、ブロックチェーン技術を駆使し、各ユーザーが個人情報を分散管理するのが特徴だ。ブロックチェーン技術により、セキュリティが担保されたIoT(モノのインターネット)が普及し、信頼できるコミュニティ形成ができるようになった。
「Web3.0が普及する将来、不透明だったデータを私たち自身で得られるようになる。例えば、企業の地球環境保護への取り組みに関するデータや、地域社会への貢献度といった情報。私たちはこれらのデータを軸とした選択ができるようになり、社会をよりよくするための選択肢が広がる」と、小島氏はWeb3.0の魅力を語った。同氏は続けて「人々が自分らしい行動を選んで、自分らしく生きることを可能にしていきたい」と、意気込みを示した。
例えば、とあるカフェでは、生産地の社会状況や物流がもたらす地球環境への影響がメニューに表示されている。価格に好みの味に加えて、情報に基づいた生産者への信頼が決め手になる。日立が目指すのはそんな世界だ。
人々の意思決定を支えるデジタルインフラ
その目標に向けて日立が取り組んでいること。それは人々の意思決定を支えるデジタルインフラの構築だ。「将来、こうしたデジタルインフラは、人々の日々の暮らしの中に完全に溶け込み、特に注意を払うことなく簡単に利用することができるようになるだろう」(小島氏)
街全体の交通網をデジタル化
日立ではこうしたデジタルインフラの構築に向けて2つのプロジェクトを実行している。1つはイタリアのジェノバ市におけるスマートモビリティの取り組み。同社はジェノバ市において、公共交通とカーシェアなどの民営交通を含む都市全体の交通網をデジタルでつなぐプロジェクトを実行している。
2020年3月に起きたパンデミックにより、ジェノバ市は都市封鎖し、人々の移動は激減して、バスや列車の運行がストップした。徐々に人の動きは回復したが、多くの市民は公共交通機関を避けて自家用車を利用するようになった。その結果、市内の道路が大渋滞し、交通事業者によるバスや列車などの運行計画の立案が全く機能しなくなっていたという。
そこで日立は2022年7月、複数の交通機関を手ぶらで自由に乗り降りできるシステムを構築。地下鉄やバスの駅などに7000個を超えるセンサーを設置。そのセンサーがスマートフォンとつながり、利用者の移動経路を完全にとらえて自動的に運賃を精算することが可能となった。
その結果、利用者は市内の公共交通機関をより気軽に使うようになり、交通事業者は、人々の移動のプロファイルを把握することで、運行計画を立てやすくなったという。日立は今後、利用者が自分たちの移動が地球環境や地域社会に与える影響を把握できるシステムにしていく構えだ。「環境に配慮した交通手段を自ら選ぶことができるような、そんなデジタルインフラにしていきたい」(小島氏)
中小企業も環境投資しやすいデジタルインフラを整備
もう1つのプロジェクトは、環境投資を加速させるデジタルインフラ「サステナブルファイナンスプラットフォーム」の開発だ。環境投資の資金調達手段の1つに「グリーンボンド」がある。グリーンボンドとは、企業や地方自治体などが、国内外の地球温暖化をはじめとする環境問題の解決を目指す事業に要する資金を調達するために、発行する債権のこと。
グリーンボンドを発行するためには、投資がもたらす環境改善効果の報告とその監査が求められる。しかし、実際のCO2削減効果の測定は容易ではなく、一般的に報告書は基場で計算した理論値を基に作成されているという。
そこで日立は、発電施設にセンサーと通信機能を持つIoT機器を取り付けて、データの記録には情報の改ざんができないブロックチェーン技術を活用。これにより、削減効果の正確な測定と信頼できるレポーティングを可能にした。
小島氏は、「サステナブルファイナンスプラットフォームが普及していけば、小さな事業者でも環境投資のための資金調達を行いやすくなる。このようなデジタルインフラを医療、教育、交通などさまざまな分野に応用していきたい。社会課題の解決に取り組む事業者とそれを応援したい個人をつなぎ、資金、人、そして幸せの循環が実現する社会を支えるデジタルインフラづくりに取り組んでいきたい」と展望を示した。
日立のDNA「和と誠の心」で挑戦
小島氏は講演終盤、日立の創業当時を振り返った。日立の創業者である小平浪平氏が創業を決意した1910年当時、日本の産業機械はほとんどが海外からの輸入によって賄われていたという。このような状況に対して小平氏は、日本の発展のためには国産の技術、国産の機械が必要であると考え、「優れた自主技術製品の開発を通じて社会に貢献する」という志を立てて、日立製作所を創業した。
小島氏は、「創業当時から、技術力あるいは人手不足から数々のトラブルに見舞われたが、その都度『和と誠の心』で困難を克服し、開拓者精神を発揮しながら、その時代の社会課題の解決に取り組んできた。日立のDNAとも言えるこの誠開拓者精神を受け継いで、新しい時代の社会課題の解決に取り組んでいきたい」と講演を締めくくった。