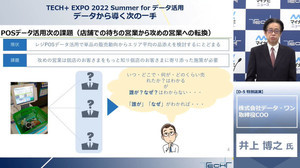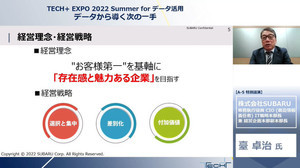金融庁から変わっていかなければ、金融業界は変わらない——こうした考えの下、金融庁では、行政手続きの電子化など、自組織においてもDX(デジタルトランスフォーメーション)を進める。8月23日に開催された「TECH+セミナー 金融DX Day 2022 Aug. DX推進から金融業界を変革するⅡ」で、金融庁 総合政策局 秘書課 情報企画調整官の稲田拓司氏が、金融庁の取り組みについて、最新の進捗状況を踏まえて紹介した。
まずは身の回りのデジタイゼーションを着実に進める
経済産業省の「DXレポート2」では、デジタイゼーション(=アナログ・物理データのデジタルデータ化)、デジタライゼーション(=個別の業務・製造プロセスのデジタル化)、DX(=組織横断/全体の業務・製造プロセスのデジタル化、顧客起点の価値創出のための事業やビジネスモデルの変革)の違いが説明されている。
金融庁での定義はこれとは微妙に異なり、デジタイゼーションからDXまでのデジタル化の流れを表す包括的な表現として、デジタライゼーションという言葉が用いられている。いずれにしても、最終的に新たな価値を生み出すことがDXの本質であり、デジタル化はあくまでも手段という位置付けだ。
DXを推し進めるにあたっては、ある程度失敗を許容することが重要だが、政府機関である金融庁においては「どんどん失敗をして良いわけではない難しさもある」と稲田氏は吐露する。ただし「世の中を変えたいという意識はみなさんと一緒」だという。そのため、金融庁はまず身の回りからデジタイゼーションを進めてデータ利活用の範囲を広げていくというスモールスタート戦略でDXに取り組んでいる。
大きく世の中を変えるには金融・非金融が一体となるべき
強いリーダーシップ、押印対面廃止、旧姓使用、ワンストップ、行政手続きのオンライン化、英語化、電子納付、職員の働き方改革、COVID-19対応、データ戦略——これらは、金融庁に寄せられた改革要請だ。さまざまな項目があるが、稲田氏によるとこうした状況はデジタル化を進める上で「追い風」だという。
「なぜこうしたことにこれまで取り組んでこなかったのか自問自答すると、前例踏襲主義で新しいことをしようとしてこなかったためだと言えます。外圧があるからこそ、急速にデジタル化に向けて動き出せています」(稲田氏)
金融業界のデジタル化はさまざまな当事者が関わるため、どこか1つの組織の努力だけでは進んでいかない。金融庁は、まず自らの取り組みによって金融業界全体のDXの口火を切りたいという考えだ。金融機関と金融庁の行政手続きが電子化されることで、金融機関における業務の電子化はより進む。また、日銀・取引所、業界団体などへの報告・様式が一元化されれば、業務効率化も期待できる。
さらに、非金融サービスが台頭してきている中、稲田氏は金融業界と非金融業界が一体化することの重要性についても指摘する。
「金融サービスと非金融サービスは、それぞれ補完し合うことが大切です。非金融は革新的なプレイヤーなので、世の中を飛躍的に便利にさせる効果があります。経済面で見ても有効であるため、圧力で押しつぶしてはなりません。一方で、金融機関も持続することが必要です。金融・非金融併せてビジネスモデルが大きく変わる世の中を目指していきます」(稲田氏)