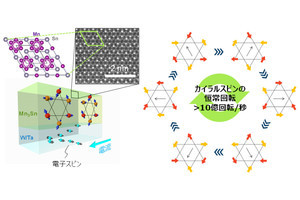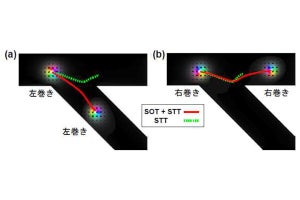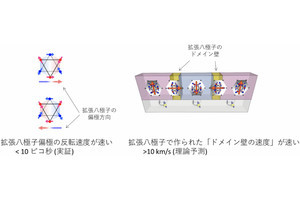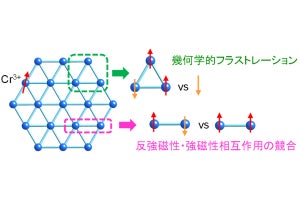東北大学は5月19日、スピントロニクスの原理を活用してWi-Fiの2.4GHz帯の電磁波を効率的に送受信する技術を開発したこと、ならびに、それを環境発電技術へと発展させ、直列接続した8個のスピントロニクス素子を用いて、電磁波を直流電圧信号に変換してコンデンサを5秒間充電し、LEDを1分間光らせ続けることに成功したと発表した。
同成果は、東北大 電気通信研究所の深見俊輔教授、同・大野英男教授(現・東北大学総長)らは、シンガポール国立大学のHyunsoo Yang教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。
Society 5.0社会では、社会に張り巡らされたセンサの数は1兆個にもなると言われている。しかし、そうした膨大なセンサを設置する際に問題となるのが、バッテリー交換にかかるコストだ。そのため、そうした負担をなくすことを目指し、これまで使われず捨てられてきた微小なエネルギーを活用する環境発電(エナジーハーベスティング)技術の発展が求められており、そうして捨てられてきた微小なエネルギーの1つにWi-Fiの電波がある。
今回、研究チームはスピントロニクス素子「磁気トンネル接合」を用いて、2.4GHzの電波から発電を行える技術を開発することに成功した。また、この技術を用いて、直列接続された8個の磁気トンネル接合素子、コンデンサ、昇圧コンバータ、1.6Vで発光するLEDからなる簡易デモシステムを構築、環境発電の原理実証実験を実施したという。具体的には、磁気トンネル接合の2.4GHzの電波からの発電によりコンデンサが3~4秒で充電され、この充電を開放することで1分間に渡ってLEDが光り続けることができることが確認されたという。
磁気トンネル接合は、スピントロニクスの原理を利用する機能性素子の代表例で、すでに磁界センサや不揮発性メモリとして実用化されているが、これまで研究が行われてきた高周波応用に向けた磁気トンネル接合素子は、単体ではWi-Fiの周波数帯で高強度の信号を生成する性能が不十分だったとのことで、今回の研究では、今回の用途に特化して特性を制御した磁気トンネル接合とその接続技術を開発したとする。
また、開発された磁気トンネル接合を直列に接続した場合と、並列に接続した場合のそれぞれについて、交流(AC)を入力したときに整流効果で出力される直流(DC)、およびDCを入力したときに発振により出力されるACが詳細に調べられたところ、並列接続はDCからACを生成するのに適しており、一方で直列接続はACからDCを生成するのに適していることなどが判明したという。
さらに直列接続の場合に2.4GHzの高周波電流を入力した際に発生するDC電圧は入力電力あたり2万200mV/mWとなることを確認。これは現行のショットキーダイオードの特性を凌ぐ値だとする。
今回の成果について研究チームでは、身の回りで「捨てられ続けている」電力であるWi-Fiの電波を効率利用してIoT情報端末を駆動する技術の確立に向けた重要な一歩と位置付けられるとする。また、磁気トンネル接合は不揮発性メモリの記憶素子として量産技術が確立されていることから、今回の素子も比較的容易に大量生産へと結びつけられることが考えられるともしている。