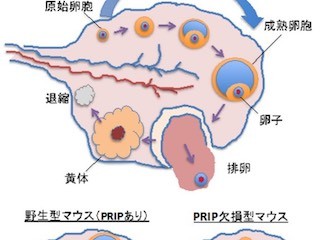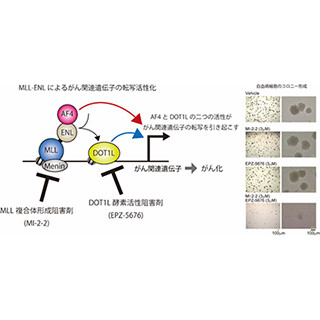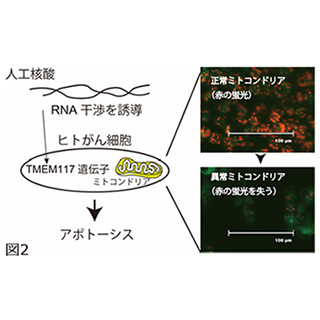九州大学は、同大学大学院医学研究院 中村雅史教授、同大学病院 仲田興平助教、大学院3年生 遠藤翔らの研究グループが、膵がん細胞の転移、浸潤に影響を与えている膵星細胞の活性化にオートファジーが関与していることを発見し、膵星細胞のオートファジーを抑制することが、新たな膵がん治療法となる可能性を見出したことを発表した。この研究成果は、米国科学雑誌「Gastroenterology」2017年5月号に掲載された。
膵がんの5年生存率は9.2%と、ほかのがんと比較しても極めて予後が不良な疾患であり、その予後の改善は社会的急務となっている。膵がんの予後が不良な理由として、早い段階から周りの組織に浸潤や転移をする事が挙げられ、発見時に手術適応とならない症例の割合が高いのが現状である。
膵がん組織には、がん細胞のほかに、線維芽細胞を中心とした"間質"と呼ばれる構造が存在し、この間質に存在する細胞ががんの浸潤や転移を促すサイトカインを分泌し、膵がん細胞の転移や浸潤を促すと考えられている。
同研究グループは、膵がんで癌間質相互作用の中心を担っている細胞が"膵星細胞"が膵がんの悪性化に重要であると考え、そのメカニズムとしてオートファジーに着目した。膵星細胞に対してオートファジー関連遺伝子であるAtg7やAtg5遺伝子の発現を抑制したところ、膵星細胞の活性化が抑制され、さらに膵星細胞から分泌される IL-6;Inerleukin-6やコラーゲンの産生が抑制されたという。
膵がん細胞株の浸潤能は膵星細胞と共に培養することで亢進するが、今回Atg7を 抑制した膵星細胞と共培養を行ったところ、Atg7を抑制していない膵星細胞と共培養した場合に比べて膵がん細胞の浸潤が抑制されたということだ。
また、膵星細胞と膵がん細胞株をマウスの膵に共移植をすると、肝転移や腹膜播種が見られるが、Atg7を抑制した膵星細胞を共移植すると、Atg7を抑制していない膵星細胞を共移植した場合に比べて膵がん細胞の肝転移や腹膜播種が抑制されたという。
さらに、オートファジー抑制剤であるクロロキン(CQ)を投与した場合にも同じ結果が確認され、クロロキンを投与したマウスではクロロキン非投与マウスに比べて肝転移や腹膜播種が抑制される事が確認された。
これらの結果は、膵癌間質に存在する膵星細胞のオートファジーを抑制することにより、膵がんの浸潤、転移が抑制される可能性を示唆しており、今後オートファジー抑制剤が新たな膵がん治療薬開発のカギとなる可能性が考えられる。 その結果、切除不能膵癌が切除可能な状況まで縮小したり、切除後の再発率が抑制されたりすることにより、難治がんである膵がんの予後が改善することが期待できると説明している。