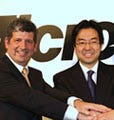|
|
マイクロソフト 業務執行役員 マイクロソフトビジネスソリューションズ事業統括本部 統括本部長御代茂樹氏 |
マイクロソフトは、CRM(Customer Relationship Management)アプリケーションの新版「Microsoft Dynamics CRM 4.0」(以下Dynamics CRM 4.0)日本語版の提供を3月3日から開始する。「Dynamics CRM 4.0」は、社内設置型に加えSaaS(Software as a Service)型も用意するとともにライセンス体系を改め、導入する企業の規模、事業戦略に合わせ最適な形態を選べるようにしている。従来製品が主な顧客と位置づけていた中堅に加え、大手から中小までを狙い、さらに裾野を拡大することを図っている。また、パートナー経由の事業推進やBPO(business process outsourcing)との融合で、パートナーの事業機会拡大とエンドユーザー企業の事業効率化に結び付けたい考えだ。
「Dynamics CRM 4.0」で同社のCRMにいよいよSaaS形態を導入するわけだが、大きな特徴はこれまでの社内設置型、SaaS型のいずれも同一の製品とソースコードを用いるため、SaaS型で開発した機能や蓄積したデータを社内設置型に移行しやすくなっている点だ。同社では、「一般にSaaS型から社内設置型に移行しようとすれば、一旦SaaS型で自社システム用にカスタマイズした機能を開発し直したり、蓄積されたデータを移行するために多大な労力が必要になったりするが、「Dynamics CRM 4.0」はビジネスを止めず、移行にかかる費用を低く抑えることができるという。
今回の製品の鍵となるのは「選択肢」だ。新たに追加されたSaaS型は、ユーザー企業の外部からアプリケーション/機能をサービスとして供給するため、初期導入費用が抑えられ、開発コストや運用管理コストなどは基本的に不要となり、中小企業にとっては利用しやすくなる。一方、他社のサービスも含め、一度SaaS型を導入した企業が業務の拡大、あるいはIT戦略の上からの判断で社内設置型に変更することを望んだ場合、SaaS型しかないサービスではこうした要望に応えることができない。
ここで重要となるのはライセンス体系を刷新し、利用形態に応じた最適な形を選べるようにしたことだ。新しいライセンス体系は以下の通りとなる。
サーバライセンスでは、単一サーバ上で複数企業が利用可能となるマルチテナント機能の提供に伴い、小規模利用を対象とした「Workgroup Server」、1サーバ上に単一企業を割り当てるシングルテナントでの利用を対象とした「Professional Server」、グループ企業との共同利用など、1サーバ上に複数企業を割り当てるマルチテナント利用を対象とした「Enterprise Server」の3種類を用意した。
クライアントアクセスライセンス(CAL)では、従来の利用ユーザー数がベースとなる「User CAL」と、利用クライアントデバイス数をベースとする「Device CAL」、「参照機能限定ユーザーを対象とした「Limited CAL」を用意し、これらを組み合わせて購入することも可能だ。たとえば、24時間稼動のコールセンターなどのシフト制勤務スタッフの場合「Device CAL」が、レポート参照だけの利用で済むマネージャ層には「Limited CAL」が適していることになり、従来のライセンス体系より低額で利用できる。
「Dynamics CRM 4.0」は60以上の機能強化をしているが、大規模企業に求められる拡張性と小規模な企業に求められるSaaS型利用を可能にするための機能拡張を行っている。
たとえば、グローバルに事業展開する企業の利便性向上のため、多言語、多通貨に対応、同一サーバ上の「Dynamics CRM」を複数の国で利用できるようにした。また、「マルチテナント」形式の採用で、同一サーバ上に複数の企業システムを設置することが可能となり、複数企業に対するSaaS型サービスの提供、また設置型の下でのグループ企業展開などを実現させた。そのほか、「Microsoft SQL Server」のデータベース ミラーリング、クラスタリングに対応、可用性の高いシステム構築が可能になっている。
同社 業務執行役員 マイクロソフトビジネスソリューションズ事業統括本部 統括本部長御代茂樹氏は「早期導入、低コストなどホスティング(SaaS)型には、さまざまメリットがあるが、それらの点だけで一概にホスティング型が良いとは限らない。1ユーザーあたり月額1万円でも、500ユーザーとなると月500万円、年間で6,000万円、これで5-6年使う総額を考えれば、どこかで社内設置型にした方が良いということもある。ホスティング型と社内設置型には、それぞれメリット、デメリットがある。企業のビジネスの進化やIT戦略に合わせたものを提供していくべきではないか」と話す。