借地を検討していて借地料の算出方法を詳しく知りたい、借地料をどうやって決めるのかわからないなど、疑問を持っていませんか。土地を貸してその対価として支払ってもらう借地料には、いくつか決め方の基準があります。さらに算出方法も多数あり、借地にしてみようと決断する前に知っておいて損はありません。
そこでこの記事では、さまざまな角度から借地料について解説します。具体的には、借地料の決め方の基準や計算方法の詳細、借地料にかかる税金、借地のメリットなどを取り上げるほか、借地にするときのポイントや借地権の種類についても紹介していきます。
本記事を読んでいただければ、借地料の算出方法や税金・見直し時期だけではなく「借地」そのものについても理解を深められるでしょう。
借地料とは

借地料とは、土地の貸し出しで借り主が地主に対して支払う土地使用料のことです。あらゆる土地には所有者がおり、所有者が土地の使用権を持っています。地主である土地の所有者は、使用しない土地を借地として人に貸し出して土地を活用することができます。
土地の貸し出しを行う際は土地を借りて使用する権利として、借り主に対し借地権というものが発生します。土地を借りる人は借地権者となり、地主は借地権設定を行うため「借地料=土地の権利の使用料」とも言い換えられるでしょう。また借地料ではなく「地代」といわれることも一般的です。
借地料の決め方の基準
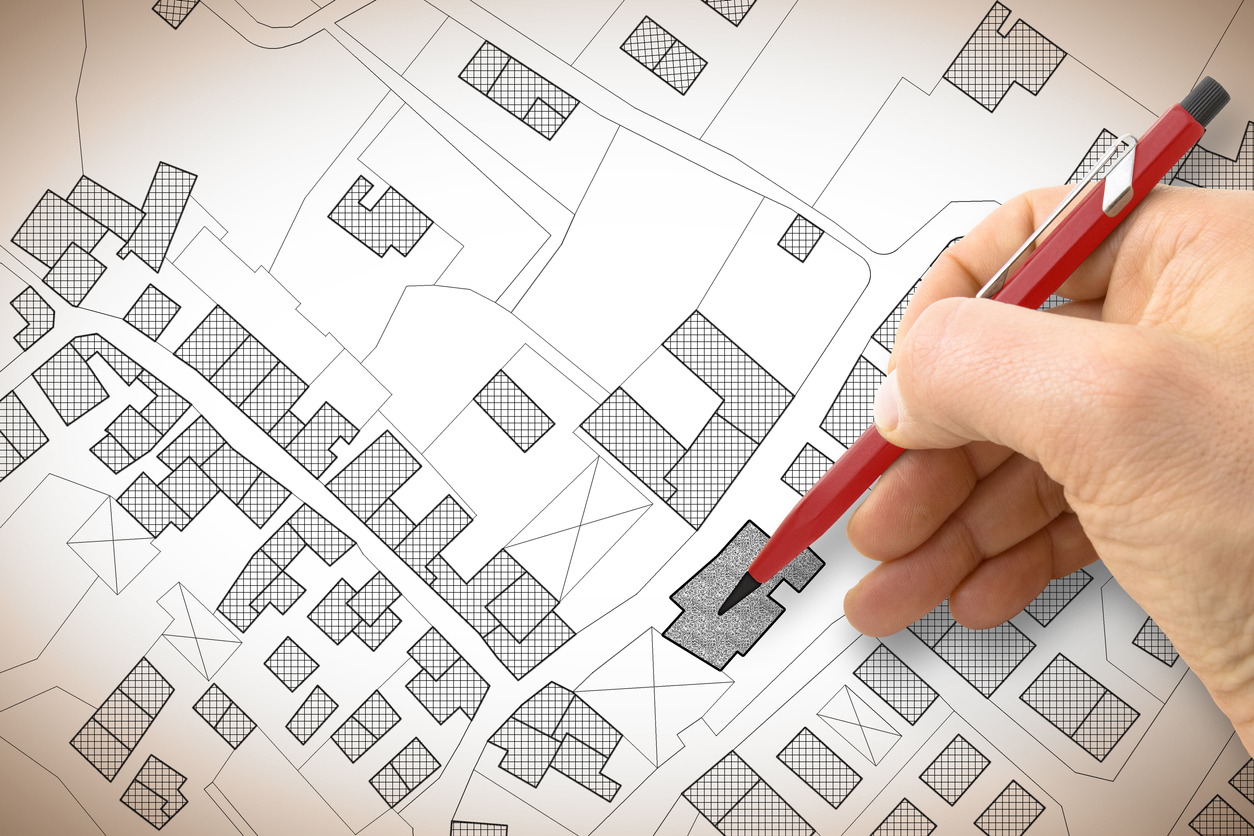
借地料は借地のエリアの相場、もしくは土地の利用方法から決めます。ここでは、借地料の決め方の基準についてまとめました。
相場から決める
借地料を借地のあるエリアの相場から決めることができます。都市部のような土地価格の高いエリアにあれば、借地料はおのずと高くなります。
逆に、地方などの土地価格の低いエリアにある場合、借地料は低くなる傾向にあるでしょう。つまり借地料の額は一定ではなく、主に都市部か地方かによって大きく異なります。
利用方法で決める
土地の利用方法で借地料を決めるケースもあります。利用方法の種類は主に次の3つです。
- 建物を建て利用
- 建物を建てずに利用
- 簡易設備を建設して利用
また、住宅用や商業用ビル・オフィス、資材置き場などの利用法によっても借地料は変わります。利用法が商業用ビル・オフィスであれば高い収益を生み出せるため、借地料は高くなる傾向にあるでしょう。
借地料の計算方法

借地料の計算方法は多数あり、借地の用途や立地などの条件によって使い分ける必要があります。計算方法の種類は以下の通りです。
- 路線価から計算
- 積算法
- 収益分析法
- 公租公課倍率法
- 賃貸事例比較法
各計算方法の詳細を見ていきましょう。
路線価から計算する
国税庁が発表している路線価から借地料を計算できます。路線価とは、国税庁が7月上旬に発表する税金を計算するときの算定基準になる土地価格のことです。路線価の評価の方法は、最初に1月1日時点での全国約41万ヶ所の道路を調査します。その後、不動産鑑定士の鑑定評価価額などを参考にしたうえで、その道路に接している土地価格を算出するのが流れです。
こうした路線価を使った借地料の計算方法の手順は以下の通りです。
- 路線価をもとに更地価格を求める
- 更地価格の目安は路線価に0.8を掛けた金額
- 更地価格の1.5~3%程度が目安となる年間借地料
路線価は、地代や利便性が高いエリアほど高くなることが一般的です。また、国税庁のホームページから確認できるため、信頼できる情報をもとに計算したい人に向いている計算方法といえます。
積算法
積算法は土地の更地価格に期待利回り(更地価格分の収益を何年間で得たいのか)を掛けて、必要経費をプラスする計算方法です。期待利回りは2%程度にすることが一般的です。
必要経費の種類は以下の通りです。
- 固定資産税
- 都市計画税
- 管理費 など
利回りや必要経費を把握できるのであれば、積算法によって借地料を導き出しましょう。
収益分析法
収益分析法は、貸す土地の上に建っている店舗や工場より得られる売上や純利益を調べて、土地がどれくらい貢献したのか算定する方法です。
収益分析法の場合は、厳密に土地貢献度を計算することは困難なため、専門家に依頼して計算してもらうことが一般的です。事業目的で土地を利用する借地人に貸し出したい場合は、収益分析法で計算しましょう。
公租公課倍率法
公租公課倍率法は、固定資産税と都市計画税を使って計算する方法で、固定資産税と都市計画税に一定の倍率を掛けるだけで計算できます。
首都圏の倍率の目安は次の通りです。
- 住宅地で約3〜5倍
- 商業地で約5〜8倍
自治体から送られてくる固定資産税の納税通知書で、公租公課の金額をチェックできるため計算しやすいでしょう。
賃貸事例比較法
賃貸事例比較法はその名の通り、周辺の賃貸事例によって計算する方法です。
- 土地の形状や面積
- 立地
- 契約期間
- 借地権の種類 など
上記の条件が似ている土地を参考にして借地料を決定します。そのため、近隣エリアの取引事例が多い場合におすすめです。
借地料にかかる税金

借地料にはいくつかの税金がかかりますが、場合によっては消費税もかかります。ここでは借地料にかかる税金の詳細をまとめました。
かかる税金の種類
借地料に必要な税金の種類は次の4つです。
- 所得税
- 住民税
- 固定資産税
- 都市計画税
土地を貸して収益を得た場合は、所得税と住民税が課せられます。売上から諸経費と固定資産税・都市計画税を差し引いた収入が課税の対象で、税額は確定申告によって決定されます。所得が赤字だった場合は、ほかの所得の金額と差し引いて計算する損益通算が可能です。
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点で所有している不動産の評価額に応じて課せられます。以下が、固定資産税評価額に対しての税額のパーセンテージです。
- 固定資産税:1.4%
- 都市計画税:0.3%
基本的に、この4種類の税金は必要だと認識しておきましょう。なお、会社勤めで給与所得を得ながら土地を貸して収入を得る際は、土地からの所得が20万円を超えていれば確定申告しなければなりません。
消費税がかかるケース
基本的に、土地の貸し出しでは消費税はかかりません。しかし、以下のケースでは消費税が課せられます。
- 貸付期間が1ヶ月未満
- 事務所などの建物を貸すときの家賃
- 駐車場などの施設利用に伴い使う土地
家賃と駐車場代が分けられていない状態であれば、家賃収入となり消費税はかかりません。しかし、住宅とは離れた場所に住民用の駐車場がある場合は、課税対象になる可能性もあります。こうした消費税がかかるケースも認識しておきましょう。
借地のメリット

借地を所有していると以下のようなメリットを得られます。
- 利益が得られる
- 土地管理の必要がない
- 税金対策になる
この章では、借地のメリットを具体的に解説していきます。
利益が得られる
借地のメリットは、土地を持っていれば初期投資がほとんど不要で利益を得られることです。土地を所有している場合は、アパートやマンションを建てて家賃収入を得たり、駐車場やトランクルームを経営したりする方法があります。ただしどれも初期コストがかかり、マンション経営などの活用方法は高額になってしまいます。
また、空室リスクや利用者がいないなどの可能性もあり、確実に収入を得られるとは限りません。さらに立地や条件によっては、長期的に見て出費が増えてしまう恐れもあるでしょう。
しかし借地であれば、こうしたデメリットはありません。土地の状態や地盤に問題がないかを確認するだけで、コストをかけずに比較的早く利益を得られます。
土地管理の必要がない
借地にした場合は、土地管理の必要がなくなることもメリットです。空き地のままだと草刈りや掃除などの手間がかかります。また、将来的に土地を売ったり活用したりすることを考えている場合は、放置しておくと年々価値が下落し、使用再開のための手間やコストがかかることも少なくありません。
遠方に土地がある場合も、管理することは困難でしょう。さらに、管理会社に委託して管理してもらうことも可能ですが、どうしても費用がかかってしまいます。しかし借地で土地を貸していれば、草刈りなどは借り主が行ってくれるので、管理も任せられて借地料も得られることがメリットです。
税金対策になる
土地を所有しているだけで各種税金の支払いがありますが、借地にしておくと相続の際に相続税の控除が発生します。相続税の控除額の算式は次の通りです。
法定相続人の数が1人でも6,000万円の控除を受けられるため、税金対策として非常に役立つでしょう。さらに、借主が土地に建物を建てた際は、以下のように2種類の税金が減額されることもメリットです。
- 固定資産税:最大6分の1減額
- 都市計画税:最大3分の1減額
こうした減額処置や控除があるからこそ、土地活用をせずに借地にしているケースも多いです。
借地のデメリット

借地は利益が得られたり土地管理が不要になったりするメリットだけでなく、以下のようなデメリットもあります。
- 苦情対策が必要
- 土地を貸している間は使えない
- 相続の問題がでてくる
各デメリットについても把握して、借地にするべきかあらためて検討しましょう。
苦情対策が必要
土地を借りている人の活用方法次第では、近隣住民から苦情が入ることもあり、本来地主は土地に手出しはできませんが、介入しなければならないケースもあります。なぜなら、土地を貸している側にも苦情が入ってくる可能性があるからです。
クレーム対応だけではなく、土地活用の方法や契約内容の見直しを行う必要も出てくるでしょう。さらに、借地料関連で土地を借りている人とのトラブルに発展する可能性もあり、「土地を貸しているだけ」と気楽な立場というわけにはいきません。土地の所有権がある以上は、責任を問われるポジションと認識しておきましょう。
どのように対応してよいのかわからない場合や対応しきれない場合は、すぐに弁護士へ相談することをおすすめします。相談だけであれば無料の場合も少なくありません。相続税関係に詳しい弁護士を選び、アドバイスを求めて対応しましょう。
土地を貸している間は使えない
一度借地に設定してしまうと、地主である土地の所有者であっても勝手に使えません。このことも大きなデメリットになるでしょう。
契約期間中は土地を借りている人のみが自由に使え、借主から契約中断の申し出がないのに自分の都合で契約を打ち切ることは不可能です。借地権は、10年・30年などの数十年単位の長期契約となることが多く、あとから土地を使いたくなっても、借主からの契約中断の申し出を待たなければなりません。
相続の問題がでてくる
借地には相続税対策できるメリットがあるものの、相続関連の問題をすべて払拭できるというわけではありません。まず、土地の相続税の負担は大きく、控除があっても支払えるとは限りません。土地を売ることで相続税を相殺することもできますが、借地人が既に居住用の建物を建ててしまっている場合など、借地の使用状況によっては売却も難しくなるでしょう。
さらに相続後も借地の契約は継続され、不当な解除は契約違反で立退料が高額になるリスクもあります。こうした問題が出てきてしまうため、貸し出す前に相続税などをシミュレーションしておくことが重要です。
借地権の種類

第三者が土地を借りるための権利である借地権には、大きく分けて「普通借地権」と「定期借地権」という2種類があり、それぞれの権利もさらに細かく分類されます。ここでは、借地権の種類の詳細を見ていきましょう。
普通借地権
普通借地権とは、次のような特徴を持つ権利です。
- 平成4年8月制定の借地借家法で定めている
- 契約更新を前提としている
- 正当事由がなければ地主は契約更新する必要あり
- 存続期間は30年、更新後20年、それ以降10年
- 契約満了時に建物が残っていた場合、地主は建物の買取を求められる場合がある
なお、現在の借地借家法ができる前の旧借地権は、存続期間内であれば建物が朽廃しても借地権は消えず、借り主側が強い権利と解釈できるものでした。しかし今の普通借地権の場合は、地主側の都合で解約できるという規定があります。
定期借地権
定期借地権は、契約満了とともに借地関係を終える種類です。さらに定期借地権は以下の3つに分けられています。
- 一般定期借地権
- 建物譲渡特約付借地権
- 事業用定期借地権
それぞれの特徴を見ていきましょう。
一般定期借地権
一般定期借地権の特徴は、以下の通りです。
- 借地権を存続できる期間は50年以上になっている
- 借地料を払い続ければ自由に土地を使える
- 建物の用途は限定されない
- 契約の更新はなく、契約満了したときは更地にして土地を返す
建物の用途に縛りがなく存続期間が長いため、ディベロッパーが分譲マンションを建設することも少なくありません。
建物譲渡特約付借地権
建物譲渡特約付借地権には、以下のような特徴があります。
- 借地権の存続期間は30年以上になっている
- 地主は契約期間が満了したあとに建物を買い取る
- 地主に建物を譲渡すれば借地権は消える
また建物を購入できない場合は、借地権を存続する仕組みになっています。
事業用定期借地権
事業用定期借地権の特徴は、次の通りです。
- 事業用建物の所有を目的とした借地権
- 10年以上~50年未満の期間を定める
- コンビニやファミレスなどで活用される
- 賃貸マンションのような居住用建物は対象にならない
- 契約の際は必ず公正証書を作成しなければならない
- 契約満了に伴い借地関係は終了する
- 建物を取り壊し土地を更地にして地主に返還する
コンビニやファミレスなどを作る場合は、一般的に10年に設定します。短期間での契約を実現できるため、将来的に土地を有効活用したい場合におすすめです。
借地権割合についてもっと知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみてください。

借地にするときのポイント

借地にする際は、土地の使用を限定される用途地域というものをチェックする必要があります。また、どうしても借り手を見つけられそうにない場合は、土地を売却することもおすすめです。この章では、借地を考えるときのポイントを紹介します。
用途地域の確認をする
借地にするときは、事前に行政指定の用途のみでしか土地を使用できない用途地域をチェックしておきましょう。どんな建物が建てられるか、どんな風に使えるかがわかる用途地域は以下の方法で確認可能です。
- 行政の用途地域図を検索
- 自治体の窓口で都市計画図を閲覧
また、あらゆるエリアにおいて用途が決定しているわけではありません。次のように地域によって、用途地域の定めの有無が異なります。
| 区域の種類 | 用途地域の定めの有無 | 計画内容 |
| 準都市計画区域外 | – | 居住地ではなく都市計画外 |
| 準都市計画区域 | 定めることも可能 | 無秩序開発を防ぐエリア |
| 都市計画地域(非線引き区域) | 定めることも可能 | 市街化する予定はあるものの、一旦現状維持 |
| 都市計画地域(市街化調整区域) | × | 市街化計画の予定なし |
| 都市計画地域(市街化区域) | 〇 | 市街化済み、あるいは市街化する予定 |
後々「思った通りに土地を使えない」とならないように、必ず用途地域の確認を行ってから借地にしましょう。
借り手がつかなければ売却も
借地にしても土地を借りる人が見つからない場合は、売却することも検討しましょう。売却してしまえば、一度に大きな額を手に入れられます。所有している土地を高くスムーズに売却するコツは、以下の表を参考にしてください。
| 土地を高く売るためのポイント | |
| 売却の準備 |
|
| 不動産会社選び |
|
| 売却活動 |
|
仲介業者に依頼しても土地を売れそうにない場合は、不動産会社に買い取ってもらうことも可能です。そうすれば、確実に売れるだけでなく、仲介手数料が無料になるメリットもあります。しかし買取という手法には、実勢価格の6~7割になるケースがほとんどというデメリットもあります。
したがって「たとえ販売価格が安くても早く売りたい」「立地や状態的に買い手を見つけられそうにない」という場合は、売却だけではなく買取も検討してみましょう。
(※1)不動産一括査定サイトは、無料で不動産の査定価格をチェックできるサービスです。ネット環境であればいつでも査定依頼でき、一軒ずつ不動産会社を回る必要がありません。無料で利用できる理由は、提携している業者が費用を支払っているからです。利用時の注意点として、業者からしつこく営業をかけられてしまうリスクがあげられます。あまりにもしつこい場合は、専門機関に相談しましょう。
(※2)一般媒介契約は複数の不動産業者と結べます。専属専任媒介契約と専任媒介契約は1社としか結べない契約で、契約期間の上限は3ヶ月、レインズへの登録・業務状況の報告義務も発生します。どの契約がベストかは状況次第です。
もっと詳しく土地売却について知りたい方は、下記の記事をチェックしてください。


おすすめの一括査定サイトは「すまいステップ」

- 初めてで不安だから実績のあるエース級の担当者に出会いたい
- 厳選された優良不動産会社のみに査定を依頼したい
- 悪徳業者が徹底的に排除された査定サイトを使いたい
\ 厳選した優良会社に査定依頼 /
すまいステップで一括査定する

借地料見直しのタイミング

借地料を見直すタイミングは、固定資産税や土地価格が上がったときです。この章では、なぜこれらのタイミングがよいのか、それぞれについて詳しく解説していきます。
固定資産税が上がったとき
固定資産税や都市計画税は地主が負担することになるため、これらの税金が上がったときであれば「税額が上がったため」という理由で借地料を交渉しやすくなります。
- 土地の評価額がアップした
- 固定資産税・都市計画税の税率アップ
上記のいずれかの理由により、固定資産税や都市計画税はおのずと上がります。経費をできるだけ抑えるためにも、固定資産税が上がったときは借地料を見直しましょう。
土地の価格が上がったとき
土地価格が上昇した場合も借地料を見直すチャンスです。貸している土地の借地料が、極端に相場よりも安かった場合は交渉してみましょう。
土地の価格が上がる要因は、以下の通りです。
| 価格が上がる要因 | 詳細 |
| 交通アクセス |
|
| 周辺環境 |
|
| 形状 |
|
土地価格が下落した際は、借主から見直しを打診される可能性も否定できません。そのため、常に借地料の相場は把握しておくことをおすすめします。
まとめ

借地料とは、土地の借り主が地主に対して支払う土地使用料で「借地料=土地の権利の使用料」といっても過言ではありません。借地料を算出する方法は、期待利回りを掛ける積算法や土地貢献度を計算する収益分析などさまざまな種類があり、それぞれ向いているケースが異なります。計算が苦手な人は、専門家に依頼して算出してもらいましょう。
また、土地を借りるための権利である借地権には、普通借地権と定期借地権の2種類あるため、それぞれについても理解を深めておきましょう。借地の算出方法や税金、借地料の見直し時期などをよく検討しながら、賢くスムーズに運用しませんか。
※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/
・https://www.rosenka.nta.go.jp/
・https://www.retpc.jp/chosa/reins/
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
・https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。


