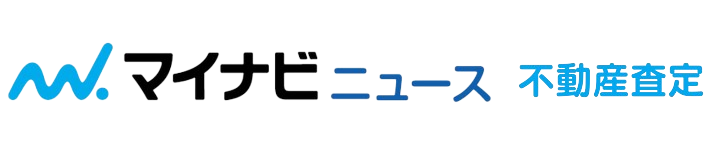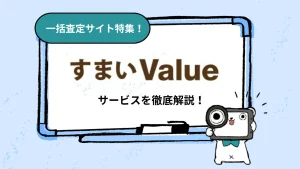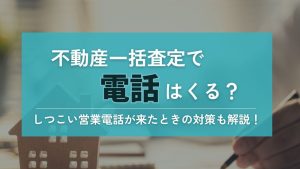活用せずに何年も放置している土地を遊休地と呼びます。遊休地を所有しているけど、「活用した方がよいのか」「どんな活用方法がおすすめなのか」わからない人も多いのではないでしょうか。
本記事では、遊休地におすすめの活用法や遊休地の活用方法を選ぶときのチェックポイントを解説しています。
遊休地に関する基礎知識やおすすめの活用法9選を解説します。また、活用の流れや注意点、活用が難しい場合の対処法にも触れますので、これから土地活用したいと考えている人はぜひお役立てください。
遊休地の活用前に知っておきたい基礎知識
遊休地の活用方法を知る前に、遊休地の性質を知っておくことが大切です。遊休地の基礎知識について確認していきましょう。
遊休地とは
活用されることなく放置されている土地のことを遊休地と呼びます。活用方法が思いつかない、親から使っていない農地を相続した場合など、遊休地となってしまう理由はさまざまです。
また、土地の所有者となってから2年以上使用していない土地も遊休地と呼ばれます。都道府県知事が利用を促すために通知を出した遊休地は、6週間以内に活用するか売却するかを決めて届け出なければなりません。所有者が従わない場合は、公共団体への売却が検討されます。
遊休地の種類
土地は自治体によって、建てられる建物の大きさや種類が制限されています。遊休地の種類は、以下の通りです。
- 宅地
- 農地
- 商業地・工業地
一口に遊休地と言っても、所有する土地によって選択できる活用方法が異なります。遊休地の種類ごとにできる活用法を確認しましょう。
宅地
宅地は活用方法の選択肢が幅広い土地です。次のような施設または建物の建設が認められます。
- 駐車場
- アパート
- マンション
- 幼稚園
- 公衆浴場
- 診療所
- 老人ホーム
ただし、地域によっては建物の高さや面積に制限があるため、事前の確認は必要です。
農地
農地は基本的に、農業以外に活用することが認められません。宅地や商業のために活用したい場合は、自治体に農地転用を申請して認可される必要があります。
ただし、農業として活用するなら問題はありません。所有者本人が農業をしていなくても、近隣の農家へ貸し出せば収入につながります。そのほか、農地を借りたい人を複数人募って貸し出す市民農園も選択肢の1つです。
農地を活用するための方法は、以下の記事で詳しく扱っていますので参考にしてみてください。

商業地と工業地
商業地や工業地は、アパートやマンションといった住宅系の経営はできませんが、施設が発する音や光の量が制限されにくく、幅広く活用できる土地です。次のような活用方法があります。
- ボーリング場
- カラオケボックス
- パチンコ店
- 自動車教習所
- 車庫
- 倉庫業向けの倉庫
- 自動車修理工場
- オフィスビル
このほか、商業地ではホテルや旅館、飲食店の建設もできます。
遊休地を活用した方がよい理由
遊休地を放置してしまうと、雑草が生えたり不法投棄されたりして、近隣の住民への迷惑になってしまうことがあります。クレームにつながるほか、土地の所有者に管理責任が問われるかもしれません。
また、活用しない土地に対して固定資産税や都市計画税を支払い続けるというのも、経済的負担を考えればもったいない話です。できれば活用して、近隣の住民とのトラブルを回避しつつ収入につなげましょう。
なお、固定資産税については次の記事で詳しく解説しています。

遊休地におすすめの活用法9選

まずはおすすめの活用法ごとの、適している土地、必要な広さ、初期費用、メリット・デメリットを一覧で紹介します。
| 活用法 | 適している立地 | 必要な広さ | 初期費用 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場経営 | ・商業地の近く ・駅の近く | 1台当たり4坪 | 200~500万円 | ・転用しやすい ・土地の形状に左右されない | ・土地の利用効率が低い ・税負担が大きい |
| 太陽光発電 | ・日当たりが良い ・電柱が近くにある | 50坪以上 | 300万円~ | ・リスクが少ない ・ランニングコストがかからない | ・発電量が安定しない ・節税効果がない |
| 事業用定期借地 | ・長期間使わない ・商業地の近くにある | 100坪以上 | 不要 | ・安定した収入が得られる ・相続税評価がを減額できる | ・中途解約ができない ・借主の事業破綻リスクがある |
| 等価交換 | ・交通のアクセスが良い | 100坪以上 | 不要 | ・遺産分割がしやすい ・譲渡税の優遇措置がある | ・交換成立まで時間がかかる ・土地の権利が失われる |
| 土地信託 | ・地域に需要がある | 100坪以上 | 不要 | ・経営の手間がない ・大規模事業に挑戦できる | ・信託会社の失敗リスクがある ・必ず配当金がある |
| トランクルーム経営 | ・狭小地 ・不整形地 | 20~30坪 | 100万円~ | ・経営リスクが低い ・土地の形に左右されない | ・金融機関の融資を受けにくい ・利益を得るまで時間がかかる |
| 貸し農園 | 農地 | 一区画10坪~ | 0円~ | ・事業リスクが低い ・初期投資ゼロ | ・借主を見つけるのが難しい ・収益性が低い |
| 賃貸経営 | ・賃貸ニーズがある ・駅から徒歩10分圏内 | 50~60坪 | 約4,600~8,500万円 | ・家賃収入が得られる ・生命保険の代わりになる | ・空室リスク ・災害リスク |
| 店舗経営 | ・交通量が多い | 30坪以上 | 約1,000万円 | ・収入が安定している ・住宅に不向きな土地でも活用できる | ・撤退リスクがある ・節税効果がない |
それぞれの活用法を初心者向け、初期投資の少なさ、収益性の高さに分けて詳しく見ていきましょう。
初心者向けの活用方法5選
まずは、大幅な収入こそみこめないものの、経営リスクが少なく初心者向けな活用方法を5つ紹介します。
駐車場経営
初期費用を抑えつつ安定的に収入を得られる活用方法として人気なのは、駐車場経営です。自分で経営する場合は、整地を行う費用がかかります。しかし、賃料はすべて自分の収入になるため、需要によってはより大きな利益を手元に残すことができるでしょう。
駐車場経営をしたいが、初期費用をできるだけ抑えたいという場合には、駐車場経営をしている法人に貸し出すこともできます。遊休地を所有する側が整地をしたり、必要な設備を導入する資金を準備したりする必要はありません。駐車場経営のプロが集客も担ってくれるため、運営方法に不安があるという人におすすめです。
遊休地の周辺が住宅街やオフィス街であった場合は、月極駐車場を経営するほうが向いています。一方、商業施設が多く立ち並ぶエリアであれば、コインパーキングのほうが向いているでしょう。自分の所有する遊休地周辺をよく分析し、どのようなタイプの駐車場を運営するのかを見極めることは、駐車場経営において欠かせません。
駐車場経営が向いている人
駐車場経営が向いているのは、次のような人です。
- 初期投資を少なく抑えたい
- 狭い土地を所有している
- 短期間で活用を始めたい
以下の記事で紹介する「駐車場経営に必要な知識」を取り入れて、上手な経営に役立てましょう。

太陽光発電
太陽光の発電所として活用することもできますが、その際には以下のリスクも考えておく必要があります。
- 設備設置費や廃棄費用の負担
- 税負担
- 売電価格の値下がりリスク
太陽光には高額な初期費用がかかり、廃棄のために資金を積み立てておく必要もあります。また、一般家庭とは違って発電面積が多いため、所得税や固定資産税が課せられるという点も忘れてはなりません。売電価格の下落も予想しておく必要があります。ランニングコストや、将来的に土地の転用がしやすいかどうかも、注意深く考慮して選択するようにしましょう。
太陽光発電が向いている人
太陽光発電が向いているのは、次のような人です。
- 土地の周囲に高い建物がない
- 投資を行うのが初めて
- 管理に手間をかけたくない
太陽光発電について、さらに詳しく知りたい方は下記の記事をあわせて読んでみてください。

事業用定期借地
コンビニやその他フランチャイズといったロードサイド店舗の経営者に、土地を貸し出す方法があります。店舗を建築するのは事業者側となるため、自分で建築費を準備する必要がありません。また、店舗が倒産しても所有者が負債を抱えずに済むという利点もあります。
貸出を行うときには、以下2つの方法から選べます。
- 普通借地
- 定期借地
普通借地は、借り手から契約を解除したいと申し出があるまで、貸出を行う方法です。一方定期借地は、あらかじめ貸出を行う期間を決めておき、その期日が来たら返却してもらう方法です。
定期借地を行うと、遊休地の活用方法を変更したい場合や、土地を売却したいというときに、貸主の都合に合わせたタイミングで返却してもらえます。そのため、多くの土地所有者に人気のある貸し出し方法です。長期的な活用方法ではなく、一時的に貸し出しを行いたいと考えているなら、定期借地を利用して貸し出しを行いましょう。
定期借地が向いている人
定期借地が向いているのは、次のような人です。
- 長期間または一定期間使う予定がない土地を所有している
- 土地が商業地に近いエリアにある
- 商業施設が建設できるくらいの広さがある
以下の記事では、土地貸し出しを行うときに役立つ「賃料の決め方」について解説しています。合わせて読んでおくのもおすすめです。
等価交換
土地を貸し出す代わりに、ディベロッパーに建物の建設や、管理の負担をしてもらうことで活用する方法です。等価交換とも呼ばれるこの方法は、土地を出資しているという形で遊休地を活用するため、初期投資として資金を準備する必要がありません。活用して得た利益を、ディベロッパーと分け合うことになります。以下は、この方法を使ってよく行われる活用パターンです。
- 賃貸物件を建築して賃料から、配当金をもらう
- 建築した物件を売却した利益から、配当金をもらう
賃貸物件として運用していく場合は、賃料の一部を利益として配当してもらい、一部屋を自身の住まいとして使用することも可能です。土地所有者は建物を建設する際の費用や、建築会社との面倒なやり取りなどを行うこともないため、活用を始める前のストレスも軽減できるでしょう。
この活用方法を特におすすめしたいのは、立地のよい遊休地です。対価交換を行うディベロッパーは、大通りに面している土地や、商業施設の多い立地であることに価値を見出します。所有する遊休地がそのような立地にあるなら、ぜひこの方法を試してみましょう。
等価交換が向いている人
等価交換が向いているのは、次のような人です。
- 初期投資をかけずに土地を活用したい
- 土地の権利の一部を手放しても構わない
- 低リスクで土地活用を始めたい
土地信託
土地信託とは、信託会社に土地を預けて運用してもらい、その利益を配当金という形で受け取る活用方法です。土地の所有権を失わずに遊休地を活用できるため、安心して土地を預けられるでしょう。
また土地信託を利用すると、相続税の節税効果も得られます。信託会社は、その土地に建物を建てることで運用を始めることが多いため、更地にしておくよりも固定資産の評価額が下がりやすく、相続税の節税につながります。
ただし、土地の上に立っている建物の固定資産税が発生する場合は、土地所有者が税負担する必要があります。とはいえ、土地信託の経費として固定資産税を計上するなら、全体的な出費を抑えることもできるでしょう。
土地信託が向いている人
土地信託が向いているのは、次のような人です。
- 広大な土地を所有している
- できるだけ初期費用をかけたくない
- 税金を節約したいと考えている
以下の記事では、土地信託を行う際に頼りにしたい、土地コンサルタントについて紹介しています。土地活用を始める前に、ぜひ読んでおきましょう。
初期投資が少額な活用方法2選
次に紹介したいのは、投資コストがゼロではないものの少額で、経営のリスクが高すぎない方法を2つ紹介します。恵まれた立地状況で経営が軌道にのれば、毎月安定した収入を狙えます。
トランクルーム経営
トランクルームの経営とは、コンテナや建物の空き部屋を倉庫として活用する方法です。遊休地の場合は、いくつかのコンテナを設置して、荷物保管場所を貸し出した賃料で利益を生み出すことができます。
この方法で遊休地を活用する利点は、他の活用方法へ転用しやすいということです。トランクルームの経営を取り止めて、建物の建設や売却をしたいときには、コンテナを除去するだけで済みます。建物を壊すための費用がかからないため、転用時に費用を節約することにもつながるでしょう。
トランクルーム経営が向いている人
トランクルーム経営が向いているのは、次のような人です。
- 初期費用を抑えたいと考えている
- 住環境に適していないエリアにある
- いずれ転用する予定がある
以下の記事では、トランクルーム経営を行うときにかかる費用や、上手な活用方法について詳しく紹介しています。合わせて読んでおくのもおすすめです。


貸し農園
農地を所有していて転用できない場合は、農地のままの状態で貸し農園として活用することができます。農地を貸すだけなので初期投資を行う必要はありません。ローンの返済もないため事業リスクを低くすることが可能です。
ただし、貸そうと思っても借主を見つけるのが難しいため、収益の安定性は低くなります。リスクが低い分リターンも低いので、収益性を求める人には向いていません。
貸し農園が向いている人
- 転用許可の下りない農地を所有している
- 初期投資をゼロに抑えたい
- 事業リスクを背負いたくない
収益性の高い活用方法2選
3つめは、投資額が大きく経営リスクも高めながら、成功すれば大幅な年収アップも狙える方法を2つ紹介します。
賃貸経営
マンションやアパートを建設して、賃貸運営するという方法です。常に満室になるような立地であれば、安定かつ高額の収入を得られます。しかし、空き室リスクを考えなければなりません。
空き家が生じてしまうと維持費だけがかさみ、利益は得られないという事態に陥ります。その結果、建築費のために借り入れたローンの支払いが滞り、経営破綻してしまうというケースも少なくありません。また、築年数が経ってくると、以下の負担が生じます。
- 家賃の値下げをしなければならない
- 改修する必要が出てくる
これらの負担を軽減するために、空き家リスクを回避する方法をインプットしておくことは大切です。そうすることで、その後にかかる修繕費の費用や賃料値下がりを、乗り越える知恵が得られます。
賃貸経営が向いている人
賃貸経営が向いているのは、次のような人です。
- 賃貸ニーズのある土地を所有している
- 駅までの距離が近い
- 不労所得を得たい
店舗経営
商業施設を委託せずに自力で運営し、利益を大きくしたいと考える場合は、経営努力をし続けられるかどうかを考えておかなければなりません。
長期的な経営には、マネジメント力が必要です。しっかりと計画を立てておかないと、経営破綻するリスクや本業に影響が出る可能性もあるでしょう。もし自力で運営したいと思う場合には、以下の対策を行いましょう。
- 事前に商業施設運営の知識を蓄えておく
- 経営コンサルタントの力を借りる
これらの点を活用すると、不測の事態が生じたときにも賢く対処することができます。
店舗経営が向いている人
店舗経営が向いているのは、次のような人です。
- ビジネス計画を立てることができる
- 交通量が多いエリアに土地を所有している
- 40坪以上の土地を所有している
店舗経営について、さらに詳しく知りたい方は下記の記事をあわせて読んでみてください。
遊休地の活用方法を選ぶためのチェックポイント

遊休地の活用法を選ぶときにチェックしておきたいポイントは、以下の通りです。
- 広さはどのくらいあるのか
- 賃貸ニーズはあるか
- どの用途地域に定められているか
所有する遊休地がどのような活用方法に向いているかを確認しましょう。
広さはどのくらいあるか
遊休地の活用方法を決めるためには、土地がどの程度の広さなのかを確認することが大切です。ホテルを建設したくても、40坪程度の土地にはホテルを建てることができません。ホテルのように大規模な建築物を建てるためには、最低でも300坪以上の広さが必要となります。
60坪~100坪程度の広めの土地であればアパートやマンションなどの賃貸物件向きです。40坪以下の狭い土地でも、コインランドリーやトランクルームとして活用することができます。土地の広さ的にどのような建物を建てることができるのかを確認してから活用方法を決めましょう。
次の記事では、土地の広さごとにおすすめの土地活用法を解説していますので、併せてチェックしてみてください。

賃貸ニーズはあるか
賃貸物件を建てたい場合は、賃貸ニーズの有無を確認することが成功の鍵となります。交通アクセスが悪く、人の少ないエリアにマンションやアパートを建てても入居者は集まりません。賃貸物件が建築できる広さの土地を持っていても、空室が埋まらなければ投資が無駄になってしまいます。
周辺に学校や公園などの公共施設が充実しているエリアや、人口が増加傾向にあるエリアは空室リスクが低いです。遊休地の賃貸ニーズを調べるために、管理会社に相談したり、自分の足を運んで周辺を見て回りましょう。賃貸ニーズの有無を把握して空室リスクを回避しましょう。
どの用途地域に定められているか
土地には宅地、農地、商業地、工業地といった区分があるというのは先述の通りですが、実際はより細かく13種類に区分された「用途地域」が自治体によって定められています。このような区分がなされる理由は、計画的な市街地を形成するためです。
たとえば、区分の1つである「第一種低層住居専用地域」では、建てられる建物の高さが10~12mに制限されており、店舗の場合は50平米までしか認められていません。このような地域では、一般的なコンビニを建てることは難しいでしょう。
一方、「第二種中高層住居専用地域」では1500平米の店舗も建てられるため、コンビニはもちろんスーパーなどのある程度大型な施設も建てられます。
遊休地を活用するときの注意点

土地活用を始めても必ず成功するという保証はありません。ここでは、遊休地の活用で失敗しないための注意点を2つ紹介します。
迅速な判断が肝心
遊休地の活用や売却を先送りにしていると、土地の価格が値下がりして活用しづらい土地になったり、価格競争が高まって、売却しづらくなったりする可能性があります。特に生産緑地として自治体に指定されている土地は、素早い決断がおすすめです。
生産緑地に指定されると所有者の死亡または指定から30年を経過するまでは農業をやめることが認められません。しかし、この制度が実施されたのは1992年で、2022年には多くの生産緑地の指定が解除され、転用可能になります。
そうなれば「宅地として転売したい」「商業施設を建設して活用したい」というニーズが高まり、土地の供給が増えることから、需要と供給のバランスに影響することで土地の価格が値下がりしかねません。
できるだけ早い段階で活用や売却を進めることで、価格変動に振り回されずに済むでしょう。
ローンは賢く組み立てる
投資が必要な活用方法の場合、自己資金から捻出するだけでなくローンを組むという方法もあります。しかし、リスクを考慮せずに高額なローンを組むと、返済が滞って破産する恐れがあります。
副業としての遊休地活用であれば、期待ほどのリターンを得られなくても、給与や事業収入によって毎月返済できる額のローンを組むようにするのがおすすめです。
以下の記事では遊休地活用で、投資用ローンを上手に組む方法について解説しています。あらかじめ読んでおくのもおすすめです。

遊休地活用の流れ

遊休地の活用は以下のような流れで進めていくのが一般的です。
- 土地活用の相談を行う
- 周辺環境・市場の調査
- 土地活用プランを決める
- 建物の施工会社と契約を結ぶ
- 建物の建築が開始される
- 引き渡し後に建物管理を開始する
建物の管理は管理会社に費用を支払えば委託することもできます。特に初心者は何をすればいいのかわからない状態からのスタートになるので、土地活用ことは土地活用のプロに任せるのが安心です。
土地活用の方法に迷っているなら「HOME4U土地活用」がおすすめ

- どの土地活用方法を選べば良いのか迷っている
- 土地活用の相談をどこにしたら良いのかわからない
- 初期費用や将来得られる収益のバランスを見ながら検討したい
遊休地が活用できない場合の対処法

遊休地の活用が難しい場合は、売却や買取を検討するのもおすすめです。遊休地を売却するときの手順や節税方法、買取のメリットを見ていきましょう。
売却する
遊休地を売却するときの基本的な手順は次の通りです。
- 土地の性質や区画を調査
- 売却相場を調べる
- 不動産会社と媒介契約
- 購入希望者を探す
- 買い手が見つかれば、売買契約
- 支払い完了と所有権移転後に引き渡し
遊休地売買で損をしないために大切なポイントは、土地の相場を把握しておくことと、信頼できる不動産会社を見つけることです。相場の把握は、一括査定サイトを利用すると簡単にすることができます。
遊休地を売却したいなら一括査定サイト「イエウール」がおすすめ

遊休地の売却を検討している人にマイナビニュース不動産査定ガイド運営がおすすめしたい一括査定サービスが「イエウール」です。イエウールがおすすめな理由について、以下にまとめています。
- 月間ユーザー数No.1で安心(2020年7月時点)
- 提携している不動産会社の数も業界No.1(2020年7月時点)
- 全国エリアをカバーしているので地方の不動産も売却しやすい
- 田んぼや畑など農地の売却にも対応している
- 悪徳業者が排除される仕組みがあるので安心して利用できる
※2020年7月「不動産の一括査定サイトに関するランキング調査」より(株)東京商工リサーチ調べ
その他の一括査定サイトや選び方について詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

売却するときは確定申告で節税
土地売却時には、大きく分けて所得税、住民税、印紙税の3つの税金がかかります。
上記のうち、特に多くかかるのが所得税です。売却で得た利益を確定申告しておくと、節税対策にもつながるので、売却時には必ず行いましょう。特に次のようなケースでは、税控除を受けられる可能性があります。
- 公共事業のために売却
- 居住用の土地と一続きになっている土地を売却
- 特定住宅地の造成目的で売却
- 農地保有合理化のために売却
不動産会社に買い取ってもらう
不動産会社に仲介を依頼して売却活動をおこなっても、なかなか買主が現れない場合は、不動産会社による「買取」を検討しましょう。
買い取った不動産会社は、建物を建てたり整地するなどして付加価値を高めてから転売します。不動産会社にとっては投資コストがかかるため、買取の金額は市場価格よりも安くなりがちですが、売却活動や商談が長引かず遊休地をすぐに現金化できるというメリットがあります。
ただし買取を依頼するときには、トラブルになりえる点を知って事前に対策しておくことが重要です。
まとめ

遊休地を活用せずに放置してしまうと、周辺住民に迷惑をかけたり、税金の支払いによる経済的な負担が続いたりするので損をしてしまいます。
遊休地を上手に利用できれば資産を増やすことができるので、今回おすすめした活用法の収益性や初期投資、リスクなどを比較して良さそうと思えるものにチャレンジしてみましょう。
遊休地の活用方法を決める前に、土地の広さや賃貸ニーズ、用途地域をチェックすることが大切です。遊休地の特徴を見極めて、土地に適した活用方法を選びましょう。
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。