住宅を購入するときに、ほとんどの人は住宅ローンの利用を検討します。しかし借入額が大きくなるほど、この先何年も返済を続けることができるのかと不安に感じる人も多いです。きちんと返済を続けるためには、自分に合った借入金額と月々の返済金額を知ることが重要でしょう。
この記事では3,000万円の住宅ローンを組むためには、年収がどれくらい必要なのかを解説します。そして、無理なく返済を続けるためのポイントについても紹介します。これから住宅ローンの利用を検討している人は、ぜひ参考にしてください。
※LIFULL HOME'S 住まいの窓口来場者(390組)を対象とした調査(集計期間:2019年4月~2020年3月)より
3,000万円の住宅ローンを組める年収
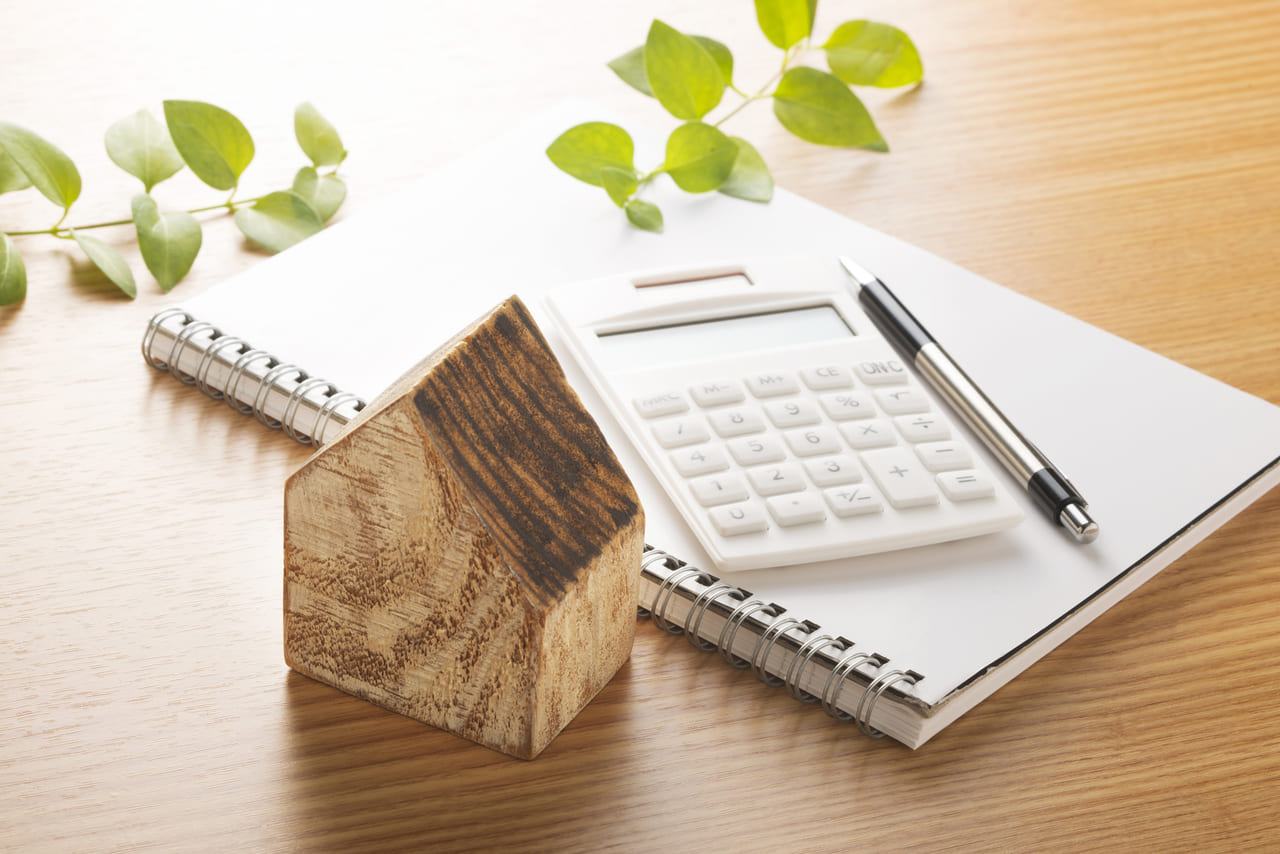
住宅ローンを提供している金融機関では、返済負担率を25~35%以下としているところがほとんどですが、これは銀行の審査基準です。実際に3,000万円の住宅ローンを利用する場合で、無理なく返済し続けるために必要な年収は600万円以上といわれています。
住宅ローンが組める額は年収25~35%が目安
ほとんどの金融機関が、住宅ローンの返済負担率は年収の25~35%以下を審査基準としています。年収の中で、住宅ローン返済額の占める割合が返済負担率です。金融機関は債務者の滞納リスクを避けるために、返済負担率の審査基準を設けていますが、これは金融機関ごとに異なります。
全国の金融機関が住宅金融支援機構と提携する住宅ローンのフラット35では、年収が400万円未満の場合の返済負担率は30%以下、400万円以上では35%以下が基準です。ただし、金融機関が定めている返済負担率は緩めに設定されており、あくまでも住宅ローン審査に通る目安の一つです。
2,000万円の住宅ローンが組める年収について詳しく知りたい人は、こちらの記事もおすすめです。

住宅ローン返済に余裕を持たせるなら年収20%
住宅ローンの返済に余裕を持たせるためには、返済負担率は年収の20%以下にするのがおすすめです。一般的に返済負担率が年収の25~35%以下であれば、ほとんどの金融機関の審査は通ります。ただし返済負担率が35%に近づくほど、負担は大きくなるでしょう。
また病気や事故などで予期せぬ出費があった際に困らないためにも、住宅ローンを利用する際は、無理なく返済を続けられるように設定する必要があります。
住宅ローンの返済比率の目安について、詳しく解説したこちらの記事もおすすめです。

住宅ローン3,000万円が組めるのは年収600万円以上
3,000万円の住宅ローンを組んで、無理なく返済するためには年収が600万円以上あることが目安です。以下の条件で、借入可能額を計算してみましょう。
- 返済期間:35年
- 返済方法:元利均等返済
- 固定金利:1.5%
- 返済負担率:20%
年収600万円の借入可能額は3,266万円ですが、年収500万円では2,721万円になります。このことから、3,000万円の住宅ローンで余裕のある返済をするためには、年収は600万円以上は必要だとわかります。
そして、同じ条件で3,000万円を借入した場合の毎月の返済額は約92,000円です。一般的に年収の約8割が手取りとされていることから、年収600万円の手取りは480万円程度です。それをボーナスがないと仮定して12ヶ月で割ると、1ヶ月約40万円の手取りになりますが、手取り40万円から92,000円を返済にあてることになります。
“参考:住宅保証機構株式会社「住宅ローンシミュレーション」”
年収600万円で組める住宅ローンについて詳しく知りたい人は、こちらの記事も参考にしてください。

住宅ローン3,000万円をシミュレーション

住宅ローンを利用する際はシミュレーションすることで、年収に合わせた借入可能額や月々の返済額を事前に把握できます。ここからは固定金利でのシミュレーションを年収ごとに紹介します。
固定金利の返済をシミュレーション
下記のような条件で、住宅ローンを組んだ場合のシミュレーションをします。
- 返済期間:35年
- 頭金:なし
- ボーナス返済:なし
- 返済方法:元利均等返済
- 金利:固定金利
金利には固定金利と変動金利がありますが、変動金利は返済期間中に定期的に金利の見直しを行うため、シミュレーションは困難です。そのため、ここでは固定金利として1.0%と1.5%の場合を記載します。
年収が300~700万円、返済負担率が20%・25%・35%の場合のそれぞれの借入可能額と返済額は下記の通りです。
【固定金利:1.0%の場合】
| 年収額 | 返済負担率20% | 返済負担率25% | 返済負担率35% |
| 300万円 |
|
|
|
| 400万円 |
|
|
|
| 500万円 |
|
|
|
| 600万円 |
|
|
|
| 700万円 |
|
|
|
【固定金利:1.5%の場合】
| 年収額 | 返済負担率20% | 返済負担率25% | 返済負担率35% |
| 300万円 |
|
|
|
| 400万円 |
|
|
|
| 500万円 |
|
|
|
| 600万円 |
|
|
|
| 700万円 |
|
|
|
“参考:住宅保証機構株式会社「住宅ローンシミュレーション」”
返済シミュレーションと住宅ローンの適正年収について、詳しく解説した記事も合わせてご覧ください。

住宅ローンの契約の流れや書類作成もシミュレーションしたい方は、こちらの記事がおすすめです。

シミュレーターを使用すると便利
自分の借入可能額と返済額をより具体的に調べるためには、シミュレーターの利用がおすすめです。シミュレーターは金融機関の公式サイトなどで提供されていて、誰でも自由に使えます。
住宅ローンの返済額などは自分で計算することは難しく、特に元利均等返済方式の住宅ローンは、元金と利息の割合が変わっていくため、簡単には算出できません。
シミュレーターでは年収や借入額、金利や返済期間などを入力すると、借入可能額や毎月の返済額が計算されます。サイトによっては、ボーナス時の返済額や繰り上げ返済なども入力できるので、より具体的に返済計画が立てられて便利です。
住宅ローンの審査で年収以外に確認されること

住宅ローンの審査において、年収以外では次のようなことがチェックされます。
- 住宅ローン完済時の年齢
- 勤続年数
- 健康状態
それぞれ詳しくみていきましょう。
住宅ローン完済時の年齢
住宅ローンの審査では、契約するときの債務者の年齢と完済時の年齢が重視され、特に完済時に80歳未満であることを審査基準としている金融機関がほとんどです。ただし実際は、完済時の年齢が定年後の65歳以上になると返済を続けることは厳しくなります。そのため返済期間が35年の場合で、審査に通りやすいのは30~34歳以下です。
また契約するときの年齢が60歳以上でも、住宅ローンの審査は厳しくなるといわれており、たくさんの頭金の準備や返済期間を短くするなどの対応が求められます。
年齢や人生設計から住宅ローンを検討する場合は、以下の記事もおすすめです。

勤続年数
住宅ローンの返済には安定した収入が必要なので、ほとんどの金融機関が勤続年数をチェックしますが、就業歴が1~3年以上を審査基準にする場合が多いです。また未来の収入が安定していることも評価の対象になります。
そのため雇用形態については、パートや契約社員よりも正社員のほうが審査に通りやすいです。そして自営業よりもサラリーマンや公務員などが審査に有利に働く傾向があります。
健康状態
ほとんどの金融機関で、住宅ローンを利用するための条件に団体信用生命保険への加入があります。健康状態が悪ければ団体信用生命保険には入れません。
住宅ローンを利用する際に問題になる病気の種類や進行の程度は、金融機関によって異なります。一般的に、団体信用生命保険の加入でチェックされることが多い病気には、次のようなものがあります。
- がん
- 心疾患
- 精神疾患
また病歴や治療中の病気がある場合には告知義務が課せられ、正確に告知せずに団体信用生命保険に加入した場合は、保険金が支払われない可能性があるため気をつけましょう。
住宅ローンの審査基準と審査のポイントについて詳しく知りたい人は、以下の記事もおすすめです。


住宅ローン返済がきつい!とならないためのポイント

住宅ローンの返済負担を少なくするためには、次のような対策を行うことがポイントです。
- 住宅ローンについて知識を深める
- 頭金とは別に生活予備費を用意する
- 将来の生活プランを想定する
- 住宅ローン返済以外にかかる費用を把握する
さらに住宅取得後の減税対策として、住宅ローン控除を利用するのもおすすめです。
住宅ローンについて知識を深める
住宅ローンを契約する際に、自分に合った選択ができれば返済の負担は最小限にできます。
- 金利の種類
- ボーナス支払い
- 繰り上げ返済
これらについての知識を深めることが重要です。
金利の種類
住宅ローンの金利には、固定金利と変動金利があります。固定金利は決められた期間内の金利が固定されるローンです。返済期間中ずっと金利が変わらない「全期間固定金利型」と、金利が変わらない期間を設定する「固定金利期間選択型」があります。通常、金利は経済の影響を受けやすいものですが、固定金利は市場金利が上がっても変わりません。ただし、変動金利よりも高めに設定されています。
変動金利は返済期間の途中で金利の見直しがあるローンです。金利が上がると返済額が増え、金利が下がると返済額は減ります。ほとんどの金融機関で1年間に2回金利が見直されますが、実際に月々の返済額が変わるのは5年に1回です。変動金利は固定金利よりも金利が低めですが、市場金利に準じて金利が上がった場合は返済額が増えてしまいます。
また、返済方法には「元利均等返済方式」と「元金均返済等方式」があります。元利均等返済方式は元金と利息の割合を調整し、毎月の返済額を一定にするもので、返済計画が立てやすいのが特徴です。
一方、元金均等返済方式は、返済額のうち元金を一定額に固定し、利息を足して返済していきます。早いペースで元金を減らせますが、ローン開始当初の返済負担が大きいのが特徴です。
もし金利に着目するなら、おすすめ低金利住宅ローンをまとめたこちらの記事もご覧ください。

ボーナス支払い
ボーナス払いとは、月々の返済に加えてボーナスが出るタイミングでまとまった額を返済することで、通常年に2回行います。ボーナス支払いを行うと月々の返済額を少なくできますが、ボーナスは必ず支給されるとは限りません。もしも勤務している会社の業績悪化からボーナスカットになった場合は、貯蓄などで支払いを補う必要があります。
またボーナス支払いを行うと金融機関に支払う利息が増えますが、ボーナス支払いによって月々の返済額を減らすと、元金を減らすペースが遅くなります。利息分は元金に応じて計算されるため、元金の減少が遅いと支払う利息分もなかなか減りません。そのため、ボーナス支払いなしの場合と比べると、支払利息が多くなる点には要注意です。
繰り上げ返済
繰り上げ返済とは、通常の返済とは別にまとまった額を返済し、元金を少なくすることです。繰り上げ返済には、期間短縮型と返済額軽減型の2種類があります。期間短縮型の場合は住宅ローンの支払期間を短くしますが、毎月の返済額は変わらないため、できるだけ早くローン返済を終わらせたい人に向いています。
返済額軽減型では毎月の返済額を減らしますが返済期間は変わらないので、子供の進学などで出費が増えたために、月々の返済負担を少なくしたい人におすすめです。
どちらも契約から早い時期に行うほど、金融機関に支払う利息分を減らせます。ただし、期間短縮型のほうが利息を減らす効果は大きいです。
頭金とは別に生活予備費を用意する
住宅ローンを組む際は、生活予備費として手元の資金をある程度残しておく必要があります。住宅を購入するときには印紙税などの諸費用がかかります。さらに会社の倒産やリストラ、家族の病気・事故などのトラブルに対処するための資金も必要です。生活予備費は会社員の場合は生活費の3~6ヶ月分、自営業の場合では6~9ヶ月分が目安です。
できるだけ借入額を少なくし、返済による負担を小さくすることが重要ですが、リスクを想定してもしもの場合に困ることがないようにしましょう。
将来の生活プランを想定する
住宅ローンを組むときは、現在だけでなく将来の生活状況も予想することが大切です。共稼ぎの場合は、出産・子育てや親の介護で、どちらかが離職すれば収入は減少します。また進学による教育費や仕送りなどで、出費が増えるタイミングも考慮が必要です。
返済期間中の生活の変化を想定し、どんな場合でも無理なく返済できるようにしましょう。
住宅ローンについて専門家に相談したいという方は、こちらの記事もご覧ください。

住宅ローン返済以外にかかる費用を把握する
住宅を購入すると、ローンの返済以外にも必要なお金があります。その費用についてきちんと把握して、返済負担が大きくなることを防ぎましょう。
住宅の購入時にかかる必要経費
住宅の購入時に必要になる主な費用は次の通りです。
- 融資事務手数料
- 火災保険料・地震保険料
- ローン保証料
- 各種税金
融資事務手数料は住宅ローンを利用する際に、金融機関に支払う手数料です。固定額か借入額の数%など、金融機関によって金額が大きく異なるため、事前の確認が必要です。火災保険料・地震保険料は、住宅の構造や面積、保証内容などによって金額が異なり、支払い方法は10年分を一括で前払いする方法のほかに、毎年払いなどがあります。
ローン保証料は、連帯保証人をつける代わりに保証会社と契約を結ぶための費用で、35年返済で借入金額1,000万円あたり約20万円が目安です。ローン保証料が必要ない住宅ローンもありますが、その場合は融資事務手数料に保証料分が含まれることが多いです。
また住宅購入時には、印紙税や不動産取得税が課せられます。印紙税は契約書などに課税される税金で、売買契約書やローン契約書に必要です。
これらの購入時にかかる経費は住宅の種類によって異なりますが、おおよその目安は以下を参照してください。
| 戸建て | マンション | |||
| 注文住宅 | 建売住宅 | 中古住宅 | 新築 | 中古 |
| 物件価格の3~6% | 物件価格の6~9% | 物件価格の6~9% | 物件価格の3~6% | 物件価格の6~9% |
なお、これらの経費は通常自己資金で用意します。
住宅の維持にかかる費用
住宅の購入後は、維持するための費用もかかります。戸建ての場合は外装塗装費や水回りの修繕費、シロアリの駆除費などが必要になり、30年で約300万~500万円が目安です。
マンションの場合は修繕積立金や管理費を支払います。
- 修繕積立金:毎月5,000~20,000円程度
- 管理費:毎月10,000~20,000円程度
修繕積立金は5~10年単位で値上げされる場合が多いです。購入時だけでなく、将来の修繕積立金についても確認しましょう。
毎年かかる固定資産税・都市計画税
固定資産税は土地・家屋の所有者に課せられる税金で、都市計画税は市街化区域内に土地・家屋を所有している人が支払う税金です。これらは住宅を所有したら毎年支払わなければなりません。
各税額の計算方法は次の通りです。
※この1.4%の税率は自治体によって異なる場合があります
※都市計画税の税率は0.3%までと定められています
なお税額の算出に使われる固定資産税評価額は、3年に一度見直しが行われます。
住宅ローン控除を利用する
住宅ローン控除は条件を満たすことで、所得税と住民税から一定額が控除される国の制度です。住宅ローンを使ってマイホームの取得や増改築を行った人などが対象ですが、正式には住宅借入金等特別控除といいます。
1年あたり最大40万円の控除を最長10年間受けられるため、ぜひ活用したい制度です。
住宅ローン控除について詳しく知りたい人は、こちらの記事もおすすめです。

住宅ローン控除の利用条件
住宅ローン控除の適用には一定の条件を満たす必要があり、この条件は新築住宅と中古住宅の場合で異なります。
【新築住宅の場合】
- 住宅ローン控除の適用を受ける本人が、引き渡し日から6ヶ月以内に居住して住み続けていること
- 住宅ローン控除の適用を受ける年の合計所得が3,000万円以下であること
- 住宅の床面積が50平方メートル以上あり、さらに本人の居住用の床面積が2分の1以上あること
- 住宅ローンの返済期間が10年以上であること
- 居住した年とその年の前2年、後3年の計6年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用がないこと
【中古住宅の場合】
- 新築住宅の適用条件を満たしていること
- 建築後に住居用とされたものであること
- 一定の住宅性能を満たし、さらに耐震基準を満たしていること
- 築20年以下の中古住宅であること、または耐火建築物の場合は25年以下であること
- 既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
購入した住宅がこれらの条件に当てはまるかチェックしてみましょう。
“参考:国税庁「No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」「No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」”
住宅ローン控除の申請方法
住宅ローン控除を適用するためには入居した翌年の確定申告が必要で、管轄の税務署に必要書類を提出して行います。税務署で確定申告書を受け取り、不動産売買契約書や借入金の年末残高証明書などを参考に記入します。記入方法がよくわからない場合は、税務署や市区町村の相談窓口に問い合わせましょう。
また、サラリーマンなどの給与所得者は最初の年に確定申告すれば、2年目以降の申請は不要です。翌年以降は年末調整によって控除が受けられます。
住宅ローンについて専門家に相談するなら「HOME’S 住まいの窓口」がおすすめ

住宅ローンや家づくりに関して専門家に相談をするなら、LIFULL HOME’S 住まいの窓口を利用するのがおすすめです。このサービスは日本最大級の不動産・住宅情報サイトのLIFULL HOME’Sが運営する、 住まい選び・家づくりの無料相談窓口です。
LIFULL HOME'S 住まいの窓口では、主に以下の6つのサービスが受けられます。お金まわりの相談(FPの紹介)はもちろん、住まい選びや家づくりに関する相談にも幅広く対応しています。
- 自分に合う不動産会社のご紹介
- お金のアドバイス(FPの無料紹介も可能)
- 住まい選びのアドバイス
- 家づくりの進めかたのアドバイス
- 不動産会社とのスケジュール調整やお断りの代行
- 無料講座でお悩み解消
不動産会社やハウスメーカー・建築会社の選び方など、素人では判断しづらいことも、忖度のない中立な立場でアドバイスをしてもらえるので、初めて不動産を購入する人は一度利用を検討してみるとよいでしょう。特定の会社を強引に進めたり、営業電話がかかってきたりすることもないので安心して利用できます。
相談は、以下リンク先のサイトから、近くの店舗もしくはオンラインのいずれかで予約して受けられます。
まとめ

住宅ローンを組むときは、返済のシミュレーションが重要です。月々の返済額を算出して、住宅購入後の生活にかかる費用を把握しなければなりません。また住宅ローンの返済金額は、生活状況の変化によって収入が減少したり予期せぬ出費が発生したりする可能性を考え、余裕を持たせる必要があります。
さらに契約する際に金利の種類や返済方法など、最適な選択ができるように住宅ローンについて詳しく理解することもポイントです。自分にぴったりの返済計画で、住宅ローンを無理なく活用しましょう。
住宅ローンで人気の金融機関や選び方のポイントについて知りたい方は、以下の記事もご覧ください。


※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/
・https://www.rosenka.nta.go.jp/
・https://www.retpc.jp/chosa/reins/
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
・https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。


