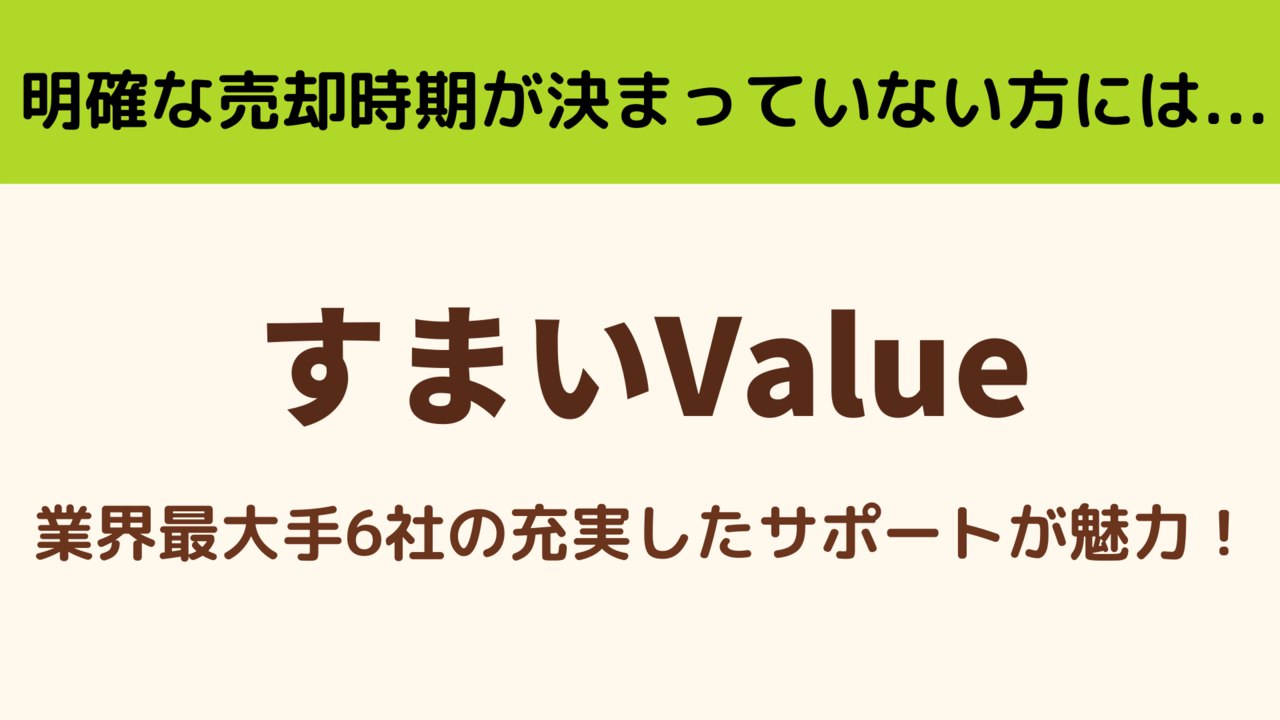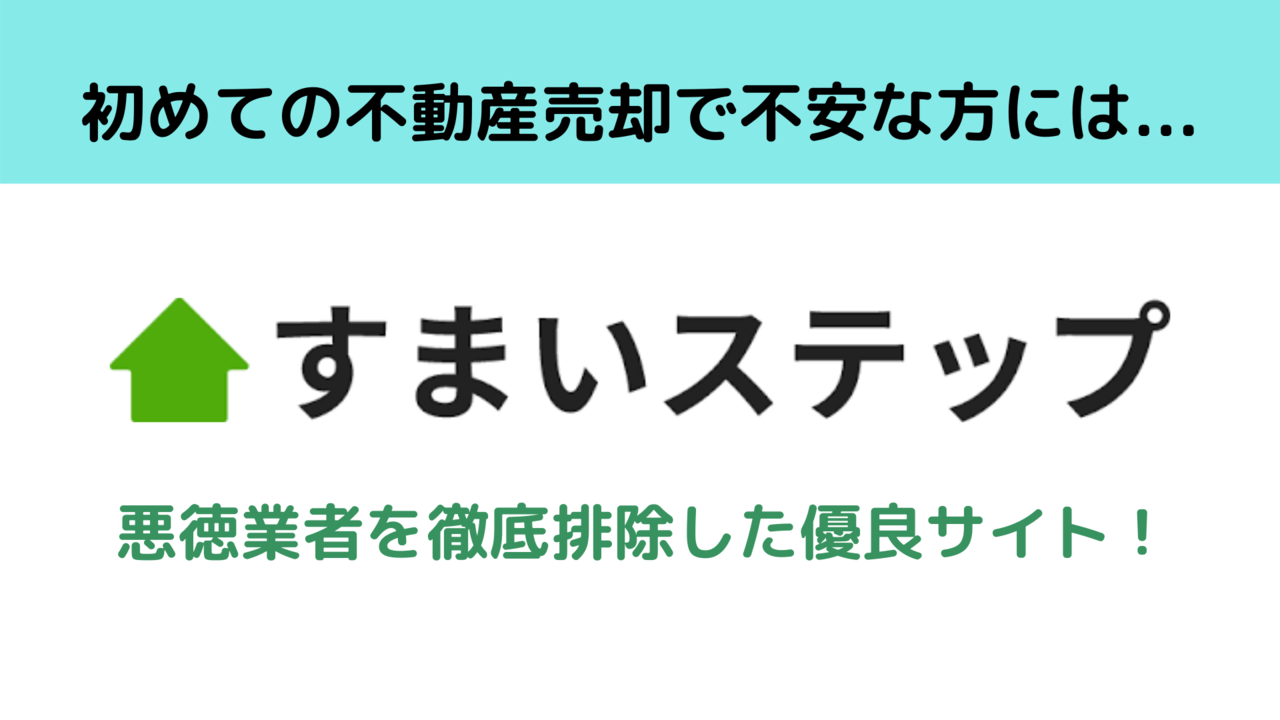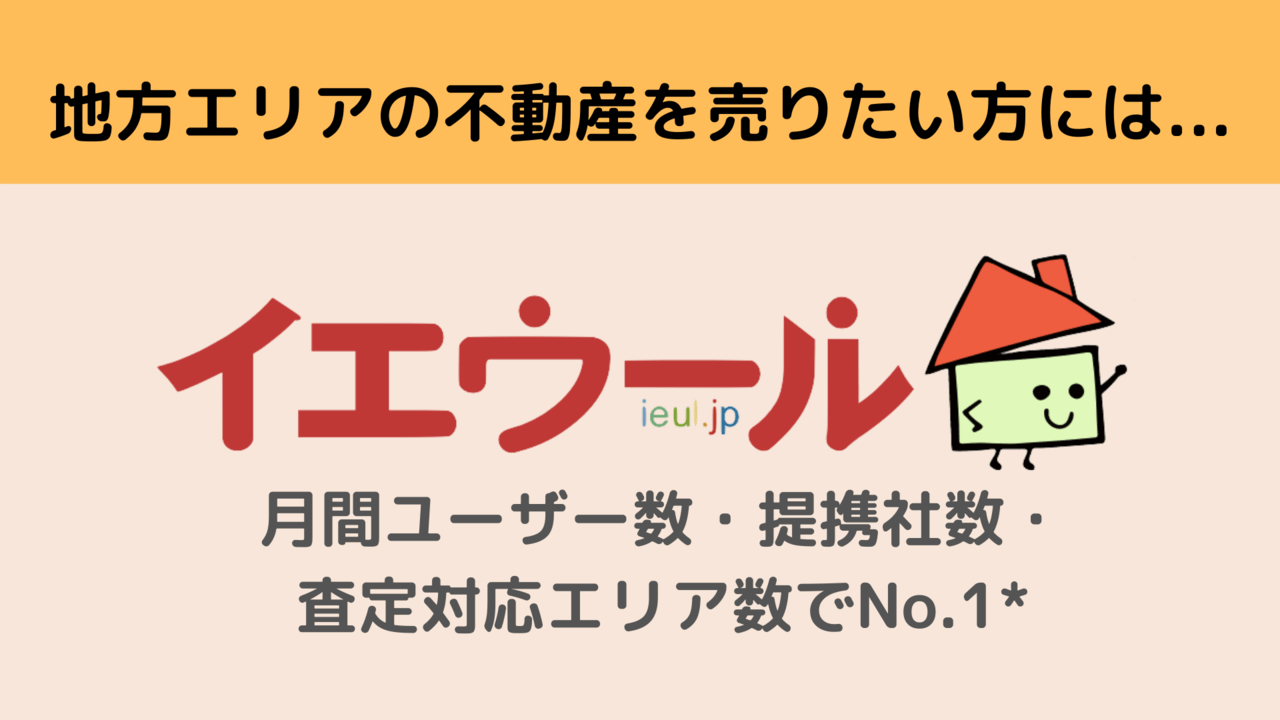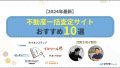不動産売却を検討していて、媒介契約の中でも一番聞き馴染みのある「一般媒介契約」を締結しようと考えている人は多いのでないでしょうか。
一般媒介契約は、複数の不動産業者に依頼でき、不動産会社同士を競争させることが可能な契約です。必然的に販売活動をする不動産業者の数も多くなるので、それだけ買い主が見つかる可能性が高まります。
しかし、「一般媒介契約書とはどのようなものなのか」についてしっかりと理解できていないと、不動産会社が作成した一般媒介契約書に問題点がないかどうかを判断できません。
そこで今回は、一般媒介契約という契約形態を含め、一般媒介契約書の内容に照準を絞り詳しく解説していきます。契約書の内容だけではなく、契約時に必要な書類や契約前に確認する事項に関しても合わせて見ていきましょう。
- 多くの不動産会社では、標準媒介契約約款を雛形に媒介契約書を作成しています。標準媒介契約約款とは、不動産売買で保護者が不当な不利益を被らないように作成されたものです。
- 契約作成に必要な書類は身分証明書、登記済権利証または登記識別情報通知書です。他にも認印は必要ですが、実印や印鑑証明書は必要ありません。
- 契約前は、標準媒介契約約款に基づいているか、宣伝活動の充実度、契約形態の違い、不動産会社ごとに異なる売り主の責任・義務などについて確認しておくようにしましょう。
【あなたに合うのはどれ?】おすすめ不動産一括査定サービス
まずは不動産がいくらで売れるか手っ取り早く知りたい方は、不動産一括査定サービスがおすすめです。不動産会社まで足を運ぶことなく、複数の会社にネットでまとめて査定を依頼できます。 ここでは、編集部おすすめの3タイプの不動産一括査定サービスをご紹介します。それぞれのサービスに特徴があるので、自分の状況に合うものを選ぶと良いでしょう。”*(2020年7月時点)出典:東京商工リサーチ「不動産の一括査定サイトに関するランキング調査」”
次の記事では、より多くのサービスを含めたランキングや「おすすめのサービスTOP3」「査定結果の満足度TOP3」「親族・友達におすすめしたいTOP3」などカテゴリ別のランキングを作っております。さらに詳しく知りたい方は読んでみてください。
媒介契約に関する基礎知識

不動産を売却する場合、不動産会社を決定したら、次にその会社と媒介契約を結ぶ流れとなります。
媒介契約とは、不動産の売買や賃貸借の取引を行うにあたり、宅地建物取引業者(不動産業者)にその取引が成立するよう仲介してもらうときに結ぶ契約です。
この章では、媒介契約の概要について再確認していきましょう。
媒介契約を結ぶ理由
媒介契約を結ぶ目的は、不動産会社側が売り主に対して確実に仲介手数料の請求を行えるようにするためです。なお、不動産会社が仲介手数料の支払いを売り主から受領するには、次の4つの条件が必要となります。
- 宅地建物取引業の免許業者であること
- 不動産会社と売り主との間で媒介契約が成立していること
- 不動産会社が媒介業務を行ったこと
- その媒介業務により売買契約が成立したこと
不動産会社の利益は主に売買契約成立後に受け取る仲介手数料です。この利益を売り主から確実に得るために、売買が成立したときの仲介手数料を媒介契約書に取り決めて、売り主との媒介契約を締結します。
媒介契約は3種類ある
媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」という3タイプの契約があります。それぞれの契約の特徴を次の表にまとめたので、一覧してみてください。
| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
|---|---|---|---|
| 複数の会社との契約 | × | × | 〇 |
| 自分で見つけた買い主との直接取引 | × | 〇 | 〇 |
| レインズ(※)への登録 | 5日以内 | 7日以内 | 任意(登録義務なし) |
| 業務報告義務 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | 任意(登録義務なし) |
| 契約有効期間 | 最大3ヶ月 | 最大3ヶ月 | 規定なし(3ヶ月が目安) |
(※)レインズ:不動産情報の登録と提供を行うコンピュータ・ネットワークシステムのことです。国土交通大臣の指定を受けた4つの公益法人(指定流通機構)が運営しています。
3種類の媒介契約の特徴を比較すると、最も縛りが厳しい契約が専属専任媒介契約で、反対に最も縛りが緩いのが一般媒介契約なのだということがわかります。
一般媒介契約書の内容とは

一般媒介契約書は、多くの不動産会社が国土交通省の標準媒介契約約款を元に作成しています。
また、国土交通省が、媒介契約における一般的な契約条項を普及させる試みを継続的に図っているため、不動産売買取引における不当な不利益発生のトラブルはひと昔前よりも随分と減りました。
そのため、現在不動産会社より提示される一般媒介契約書の内容で、売り主側が極端に損をすることはほとんどないので安心してください。
国土交通省の標準媒介契約約款を使用している
国土交通省は宅地建物取引業法の解釈や運用に関するガイドラインとして、 媒介契約書に「標準媒介契約約款」を使用することを義務づけています。
この標準媒介契約約款は、不動産売買における保護者が不当に不利益を被るのを避けるために作成されました。
媒介契約内容の具体的な規定が設けられているのは一般媒介契約だけに限らず、専任媒介契約と専属専任媒介契約においても同様です。
なお、多くの不動産会社はこの標準媒介契約約款を雛形に媒介契約書を作成しているのですが、契約書の内容は媒介契約の種類や不動産会社により異なります。
契約期間は3ヶ月を超えない範囲が基本
先述の「媒介契約に関する基礎知識/媒介契約は3種類ある」にも記載しましたが、専任媒介契約と専属専任媒介契約には最大3ヶ月の契約有効期間が設けられています。
一方、一般媒介契約には有効期間の規定がされていません。ただし、次の条項を参照してみてください。
- 第8条(有効期間)
- 一般媒介契約の有効期間は、3ヶ月を超えない範囲で甲乙協議のうえ定めます。
こちらは「全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)」の条項雛形を元に作成された一般媒介契約書の一部です。
条項には「3ヶ月を超えない範囲で」と曖昧に記載されていますが、専任媒介契約と専属専任媒介契約と同様、一般媒介契約に関しても契約有効期間は3ヶ月となるのが基本です。
一般媒介契約書の作成に必要なもの

一般媒介契約書の作成には、必要なものがたくさんあると思っていませんか。
実は、一般媒介契約を締結するために最低限必要なのは、身分証明書と登記済権利書、認印の3点のみです。実印や印鑑証明書などは必要ありません。
ただし、のちに不動産売買契約を交わす際には実印や印鑑証明書などたくさんのものが必要になるので、媒介契約時に前もって印鑑証明書を入手しておいても損はないです。
身分証明書や登記済権利書
一般媒介契約を作成する際に必要なものを次にまとめました。
- 運転免許証もしくはパスポートなどの身分証明書
- 登記済権利証もしくは登記識別情報通知書
これら身分証明書や登記済権利書は、所有者本人であることを証明するために必要です。ただし、どちらの書類に関してもコピーを取ったりして保存することなく、媒介契約時に提示するだけです。
なお、登記の名義を複数人で共有している場合は、所有者全員の合意がないと不動産を売却できません。
そのため、一般媒介契約を締結するとき、原則的には共有者全員の身分証明書が必要になります。しかし実務においては、所有者を代表する人の身分証明書があればさほど問題はありません。
ただし、一般媒介契約のときはよくても、売買契約や決済時には共有者全員分の身分証明書と委任状が必須書類となります。
次に、あったほうがよいものをリストにしたので目を通してみてください。
- 間取り図(※)
- 固定資産税・都市計画税の税額が分かる書類
- ローン残高がわかる書類
- 管理費・修繕積立金の金額が分かる書類(マンションの場合)
- 管理規約・使用細則(マンションの場合)
(※)販売図面(チラシ)を作成するのに役立ちます。マンションの場合は、不動産会社に図面のストックがあることが多いので問い合わせてみてください。
これらの書類は見当たらなければ不動産会社が何とかしてくれるので、「あれば提示する」という認識で十分です。
実印は必要なし
一般媒介契約書には、売り主の実印も印鑑証明書もいりません。仲介を依頼する不動産会社と結ぶ一般媒介契約では、不動産会社側からも印鑑証明書の提示がないうえ、会社の実印を使用することもないのです。
媒介契約を締結する際には契約書に記名と押印をするのですが、その場合の印鑑は認印で大丈夫です。ただし、シャチハタはNGになるので三文判を用意しましょう。
なお印鑑証明書に関しては、物件の購入申し込みがあってからの取得でも十分に間に合います。
一般媒介契約書のチェックポイント

一般媒介契約書を締結する前にチェックしておきたいポイントとして、大きく次の7点があげられます。
- 標準媒介契約約款に基づいているか
- 宣伝活動の内容は充実しているか
- どのような契約形態になっているか
- 仲介手数料を支払う時期
- レインズへの登録の有無
- 売り主の責任や義務
- 反社会勢力との関係はないか
特に「仲介手数料を支払う時期」や「売り主の責任や義務」という項目は、金銭の支払いに関わる重要な事項なので細心の注意を払うようにしてください。
それでは、それぞれのチェックポイントを詳しく見ていきましょう。
標準媒介契約約款に基づいているか
一般媒介契約書のチェックポイントとして最初に行うべきことは、実際に標準約款と比較し漏れなどがないかを確認することです。
先述の「一般媒介契約書の内容は」の章でも記載しましたが、国土交通省では媒介契約を締結する際、不動産会社に対して標準媒介契約約款をもとに行うよう義務づけています。
標準約款に基づいている場合には、一般媒介契約書の1ページ目にその旨が記載されているので、まずはその記載部分をチェックしましょう。
それから内容を照らし合わせた結果、もしも標準約款に基づいていない場合はその理由を不動産会社に尋ねてください。
なお、標準約款に記載されていない内容であっても、「売り主が追記したい条件があるのであれば媒介契約書にその旨を記載するように」と国土交通省は推奨しています。
そのため、希望する条件がある場合には、積極的に不動産会社に依頼するようにしましょう。
宣伝活動の内容は充実しているか
契約締結前に確認しているはずの不動産会社の宣伝活動において、「どのような媒体を使用して宣伝を行うのか」との確認を再度行ってください。
行われると思っていた宣伝活動が行われないと、高く売却できない可能性があるからです。
また、一般媒介契約では、契約を締結していない不動産会社での売買が、営業経費を払うことにより可能となっています。
不動産会社を通さず自身で購入希望者を見つけて売買を成立させることもできるので、その旨の記載があるかどうかもチェックしておくとよいです。
どのような契約形態になっているか
一般媒介契約には「明示型」および「非明示型」の2種類があります。標準媒介契約約款には「明示型にすること」との規定があるのですが、売り主が希望するのであれば非明示型にすることが可能です。
そのため、一般媒介契約書を作成するときには、明示型・非明示型のどちらを希望するかを不動産会社に伝えるようにしてください。
ちなみに明示型の一般媒介契約を結んだ場合には、複数の不動産会社に仲介依頼をした際、すべての不動産会社に対して、依頼している他の不動産会社の名称を通知しなければなりません。
一方、非明示型の場合は通知が不要です。
仲介手数料を支払う時期
仲介手数料を支払う時期は、通常であれば物件を引き渡す直前なのが一般的です。つまり、買い主より売却金を全額受領したと同時に支払います。
しかし、不動産会社によっては売買契約締結後のタイミングで請求してくる場合もあります。
売買契約の段階では、まだ買い主から手付金しか支払ってもらえていないケースが多く、買い主のローンの審査が通るかどうかさえもわかりません。そのため、仲介手数料支払い時期の確認は必ず行いましょう。
レインズへの登録の有無
先述の「媒介契約に関する基礎知識/媒介契約は3種類ある」でも解説しましたが、レインズとは国土交通大臣より指定を受けた不動産流通機構が運営する、コンピューターネットワークシステムのことです。
不動産取引の適正化と円滑化を目的とし、不動産情報の登録と提供を行っています。
なお、一般媒介契約の場合ならレインズに登録する義務がありません。
ただし、レインズは不動産業者のみが登録・利用できる不動産ネットワークで、登録すれば全国の不動産売買物件の情報を閲覧することが可能になります。
レインズ経由の紹介は非常に有効なので、最低1社には登録してもらうようにしてください。
売り主の責任や義務
一般媒介契約書には、売り主自身の責任や義務を規定している項目がいくつかあります。
一番多いのは「情報共有をきちんと行わなければならない(※1)」という項目で、連絡を怠ると違約金につながる可能性が高いです。
代表的な項目を次にまとめたので、契約書の作成時には内容をしっかりチェックするようにしてください。
- 依頼する他の不動産業者の名称と所在地を隠さずに伝える(※2)
- 他の不動産業者で売買契約がまとまった際、通知する義務がある
- 不動産会社から紹介された人との直接取引は禁止(※3)
(※1)明示型の一般媒介契約の場合です。
(※2)追加で依頼先が増えた場合には、これまでの依頼先にも共有する義務が発生します。
(※3)2年以内にこれを行うと、仲介手数料相当額を支払わなければいけません。
反社会勢力との関係はないか
平成23年6月より、反社会勢力を排除するよう示唆した条項を、媒介契約書全般に組み込むことが普及してきています。不動産売買において、暴力団などの反社会勢力を排除するのが目的です。
もしも不動産会社が反社会勢力と関係があった場合には、とんでもないトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。そのため、「反社会勢力を排除する」という条項を、契約内容に入れておくようにしましょう。
一般媒介契約書に関するQ&A

ここでは、一般媒介契約書に関するQ&Aを3点紹介していきます。まずは一般媒介契約書はどのタイミングで作成するのか、そして一般媒介契約書の作成時に印紙代等の費用はかかるのかについて理解を深めましょう。
また、証明捺印を取り交わした一般媒介契約書を作成した場合、その契約を中途解約できるのかという質問に関しても記載しているので、ぜひ参考にしてください。
一般媒介契約書はいつ作成する?
媒介契約は、不動産会社に仲介業務を正式に依頼するタイミングで締結するのが原則です。売り主が仲介業務を依頼する業者を決めたときに、双方が契約書に署名捺印して媒介契約書を完成させます。
なお、媒介契約書を作成するタイミングは、一般媒介契約の場合だけに限らず、専属専任媒介契約と専任媒介契約を結ぶ場合も同様です。
一般媒介契約書に印紙は必要?
媒介契約は公的な手続きなので「印紙が必要になるのでは」と心配する人は多いです。しかし実際には、一般媒介契約書に収入印紙は必要ありません。一般媒介契約書は非課税の対象となります。
なお、収入印紙が必要になるのは売買契約を締結するときです。
署名捺印済みの一般媒介契約書は取り消せる?
意外ですが、一般媒介契約の解約は随時可能です。
手続きや書類の再作成などは特に必要なく、電話で解約したい旨を伝えるだけで解約が完了します。解約によって、費用や違約金などの罰金を請求されることもほとんどありません。
ただし、一般媒介契約書内に広告や宣伝費などが明記されていたり、解約についての特約を設けていたりする業者も中にはいます。
そのため、例外的なケースではあるものの「中途で解約すると、それまでに行った営業活動の費用を請求される可能性もある」と覚えておくとよいです。
なお、もしも中途解約で罰金が発生してしまいそうな場合は、契約有効期間の終了を待ち、更新せずに解約すれば、何の問題もありません。
まとめ

複数社と契約が可能な一般媒介契約は不動産会社同士を競争させられるため、「好条件の不動産であれば一般媒介契約を結ぶのが効果的」とおすすめする意見がネット上で多数見られます。
ただし、一般媒介契約書の内容は、不動産会社によって宣伝活動の内容の充実度や契約形態などに差異があります。
売り主の責任や義務について定めた項目の中で情報共有が必要な場合があり、連絡を怠ると違約金が発生するケースまであるのです。
そのため、契約後に「別の不動産会社に依頼するべきだった」と後悔することのないよう、必ず契約書の内容をしっかりと確認してから契約を締結するようにしましょう。
※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/
・https://www.rosenka.nta.go.jp/
・https://www.retpc.jp/chosa/reins/
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
・https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。