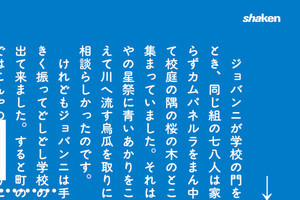| フォントを語る上で避けては通れない「写研」と「モリサワ」。両社の共同開発により、写研書体のOpenTypeフォント化が進められています。リリース予定の2024年が、邦文写植機発明100周年にあたることを背景として、写研の創業者・石井茂吉とモリサワの創業者・森澤信夫が歩んできた歴史を、フォントやデザインに造詣の深い雪朱里さんが紐解いていきます。(編集部) |
印刷界の一大事件
1925年(大正14)10月、『印刷雑誌』巻頭に「邦文写真植字機殆ど完成」という記事が掲載された。[注1]
記事は告げる。
〈たしかに一大事件〉〈吾等は此所に、はからずも、我印刷界の一大事件を報道することを喜ぶものである。一大事件とは何ぞ、全く写真だけで、金属活字なしに日本文字を植える機械が、殆んど完成に近く、試験用の機械も既に組み立てられ、立派な成績をあげて居ることである。〉[注2]
――当時日本は、活字組版による活版印刷の全盛期だった。書籍や新聞などの紙面を構成する膨大な文字は、原稿にしたがって1本1本の金属活字を「文選工」と呼ばれる職人が棚から手で拾い、それをやはり手で1ページごとに組みあげて、印刷のための版(ハンコ)をつくった。
金属活字はモノであるから、電子的に拡大縮小することは、もちろんできない。印刷物をつくるには、書体ごと、大きさごとに、すべての文字が金属活字というモノとして用意されている必要があった。
そもそもこのころ、金属活字自体が、種字彫刻師が書体ごと・大きさごとに、原寸、左右逆字で手彫りした種字から鋳型(母型)をつくり、鋳造されるものだった。活版印刷は、活字製造から印刷までの各工程において、熟練した職人たちの手に支えられていた。「邦文写真植字機」の誕生は、そうした日本の活字組版、ひいては書体と印刷をとりまく歴史を大きく変えるできごとであった。
前述の記事には、2人の男の写真が掲載されている。力強い視線でまっすぐ前を見つめる男・石井茂吉(1887-1963)と、好奇心に目を輝かせる若き男・森澤信夫(1901-2000)だ。当時、茂吉は38歳、信夫は24歳。2人は14歳離れていた。
日本語組版を鉛活字の重さから解き放ち、多彩な書体デザイン文化を花ひらかせることにつながった「邦文写植機」は、この男たちによって生みだされた。のちに写植機メーカーの両巨頭となる「写研」と「モリサワ」それぞれの創業者となる2人は、ともに邦文写植機の開発に取り組んだ盟友なのだ。しかし彼らはやがて、別々の道を歩むことになる。
石井茂吉と森澤信夫。2人はいかにして出会い、邦文写植機を世に生み出し、そしてなぜ、袂を分かつことになったのか。
――2021年はじめに発表されたニュースは、フォント界に激震を走らせた。
〈モリサワ、写研とOpenTypeフォントを共同開発〉(2021年1月18日)
〈株式会社写研 株式会社モリサワとOpenTypeフォントの共同開発で合意〉(2021年3月8日)[注3]
2024年、邦文写植機発明100周年にあたる年に、写研書体が初めてデジタルフォントとしてリリースされる。[注4]それも、長く別の道を歩んでいた写研とモリサワ、両社の共同開発によるOpenTypeフォントとして、というのだ。
これを機にあらためて紡がれるこの物語は、ともに「邦文写植機の開発」という大事業を成しえながら別の道を歩んでいた写研とモリサワの開発前史……、石井茂吉と森澤信夫、2人の男を主人公とした、「写植機誕生物語」である。
(つづく)
[注1] タイトルは「邦文写真植字機始ど完成」となっているが、「始ど」は「殆ど(ほとんど)」の誤植と思われる。
[注2]「邦文写真植字機始ど(ママ)完成」『印刷雑誌』大正14年10月号(印刷雑誌社、1925) p.2-7
[注3] 両サイトとも、2022年10月6日参照。
[注4] フォントのラインナップや提供形態、詳細時期は未定。
【おもな参考文献】
「邦文写真植字機始ど(ママ)完成」『印刷雑誌』大正14年10月号(印刷雑誌社、1925)
『石井茂吉と写真植字機』(写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969)
「文字に生きる」編集委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』(写研、1975)
『追想 石井茂吉』(写真植字機研究所 石井茂吉追想録編集委員会、1965)
【資料協力】
株式会社写研
※特記のない写真は筆者撮影