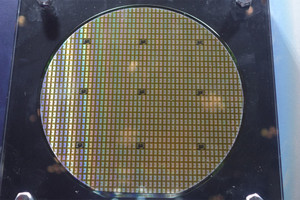科学技術振興機構(JST)、大阪大学発のベンチャーであるロータス・サーマル・ソリューション、山口東京理科大学(山口理科大)の3者は9月21日、パワー半導体において面積当たりの消費電力が増加して素子の耐熱限界が近づいている状況に対応可能な高効率な沸騰冷却器を開発したことを発表した。
また今回の成果に対してJSTは、研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)企業主導フェーズ NexTEP-Bタイプの開発課題「自発的冷却促進機構を有する高性能車載用冷却器」において、目指していた成果が得られたと評価したことも併せて発表している。
さまざまな機器が駆動するための電力を管理するパワー半導体は近年、パッケージの小型化が進み、半導体の面積当たりの消費電力が増加している。例えば、Si半導体の発熱密度は200W/cm2程度だが、SiCパワー半導体では約500W/cm2まで高まっており、半導体素子の耐熱温度の限界を超えないために、集中する熱を素早く取り去る必要があるが、従来型の循環型水冷方式では難しくなってきており、新たな冷却技術の開発が求められていたという。
注目される技術の1つが、冷媒の蒸発潜熱を利用する沸騰冷却方式で、水冷方式に比べて高い冷却熱流束を持つことから、これまでも高い冷却効率が求められる用途で利用されてきた経緯がある。しかし、冷媒に熱を伝える面(伝熱面)に限界熱流束を超えた熱が流入すると、冷却能力が急激に失われてしまうという課題があった。
-

冷却方式と伝熱性能。冷却方式別の水冷媒による伝熱性能が示されている。沸騰冷却方式は、循環型水冷に比べ50倍以上の熱流束で冷却が可能だという。従来の水冷媒沸騰型に比べ、今回の新技術は2倍以上の冷却熱流束が得られるとした (出所:JSTプレスリリースPDF)
そこで今回、沸騰冷却方式の課題を解決し、車載用途を含めて広範囲に適用可能な、より大きな熱流束に対応できる冷却技術として実用化を目指した研究開発が進められた。
今回の新技術のベースとなったのが、山口理科大の結城教授らによる沸騰伝熱効果に関する研究成果だという。発熱体に接触する銅などの熱伝導体に、幅1mm程度の溝を一定間隔で彫り込んだもの(グルーブ)とレンコン状の多孔質金属である「ロータス金属」を組み合わせることで、膜沸騰が起こりにくい構造を実現したというものである。
-

(左)ロータス金属。レンコンのような一方向性の気孔を持つのが特徴。(右)今回の新技術の沸騰伝熱効果の模式図。ロータス金属とグルーブ(溝構造を持つ熱伝導率の良い金属板)を組み合わせることで、冷媒の沸騰に用いることで膜沸騰が生じにくい効果が実現する。冷却液がロータス金属上部から吸い込まれ、蒸気がグルーブの溝から排出される (出所:JSTプレスリリースPDF)
今回の研究から、グルーブとロータス金属の気孔の寸法に冷却性能を決める重要な要素があることが見出され、冷媒に応じて適切な溝の断面積と気孔径を求める手法が考案され、それを活用することで、水を冷媒に利用した場合、従来は限界熱流束200W/cm2程度であったものが、小型サイズ(冷却面:10mm×10mm)の冷却器で限界熱流束530W/cm2以上、大型サイズ(冷却面:65mm×65mm)の冷却器では限界熱流束270W/cm2が達成されたという。
また、フッ素系不活性液体冷媒を用いて試作された沸騰冷却器においても、今回開発された技術を適用することで、発生した蒸気と冷媒の流れを分離し、蒸気の速やかな排出と、冷媒の安定供給が両立できることが示されたとしている。
-

冷却面温度と冷却性能の関係。沸騰促進体を用いた実験により、水冷媒(赤丸)とフッ素系不活性液体冷媒(青三角)を用いた場合の冷却面温度と熱流束が求められた。(a)薄紫色部分:サーバーの冷却に用いる性能領域。(b)黄色部分:Si半導体用途で使う性能領域。(c)水色部分:SiCパワー半導体用途で使用が想定される性能領域 (出所:JSTプレスリリースPDF)
さらに、フッ素系不活性液体冷媒を用いてワークステーション向けCPUクーラーへの適用を検討。試作品において、既存製品と同等の冷却性能を半分の冷却器体積で実現できることも確認したという。
試作された沸騰冷却器は、Si半導体およびSiCパワー半導体によるインバーターの冷却が可能な性能を保持していることから、高発熱密度化する車載用のパワー半導体の熱集中問題を解消する技術として期待されると研究チームでは説明しているほか、従来のワークステーション向けCPUや大型サーバーの高効率な冷却技術としての活用も考えられるとしている。