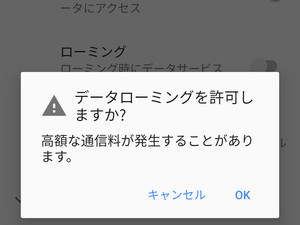蛇口から宿泊するホテルがある地下鉄7号線・皇崗村駅までは、現地コーディネーターが手配してくれたクルマで移動し、チェックイン後に周辺の店舗を物色開始。この皇岡村駅は2016年秋に開業したばかりの新しい駅ですが、周辺はある程度の年月を感じさせる建物が多く(とはいえ改革開放以降に建設された築30年以内のものばかり)、モバイル決済普及前からあること確実な佇まいの店舗が大半を占めます。
まずは便利店(コンビニエンスストア)から。冷蔵庫から取り出した価格4元のビールを店員さんが座る机の前に置くと、端末に金額が表示され、QRコードの読み取り装置にかざすよう手で促されます。アリペイでの支払いは初めてなのでモタついていると、なんだこの人はという表情の店員さんがアプリの「Pay」ボタンをタップしてくれました。アプリに表示されたQRコードを読み取り装置にかざせば、電子音とともに支払い完了です。
バーコードリーダーではなく据え置き型の読み取り装置を使うことを除けば、日本のコンビニで○○ペイを使うときと変わりませんが、店員側に「当然QRコード」という態度が見えるところが大きな違いでしょうか。日本は利用する決済方法を口頭で伝えないと、暗黙の了解で現金支払いになりますが、こちらでは黙っていればQRコードです。
日本の下町にあるような果物屋も覗いてみましたが、やはり支払い方法はQRコード一択の模様。柱にQRコードが印刷された紙が雑に貼られており、買い物客はそれをスマートフォンでスキャンし、なにやら(おそらく暗証番号を)入力しています。数分店先をうろつき様子を伺いましたが、現金で買い物する客は1人もいません。
飲食店も同じ。ファストフード店の店頭にはQRコード読み取り装置が設置されているだけで、レジスターは見当たりません。着席式の店舗でも、食事を終えるタイミングでQRコードが印刷されたレシートが渡されるので、それをアプリでスキャンすればOK。現金を受け渡しするカウンターすらありません。当地では財布を持ち歩かない人も少なくない(実際、複数人に確認)のですから、むしろ自然な成り行きです。
ところで、深センでは飲食店の店先で「街電」や「来電」と書かれた装置をよく見かけました。これは、どこで借りても返してもいいモバイルバッテリー共有サービスの装置で、LightningやType-Cなど各種端子に対応しています。決済は完全にスマートフォン任せ(装置のQRコードを読み取るだけ)だから管理コストも抑えられるという、QRコード決済にとてもよく馴染むサービスではないでしょうか。