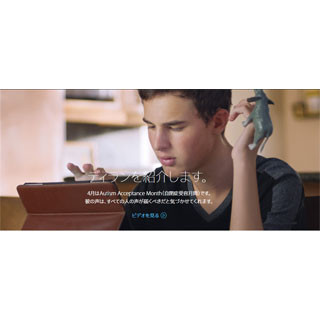続いて、医学部眼科学講座の助教である猪俣武範氏が開発に携わった、ドライアイや眼精疲労といった目の症状をドライアイ指数という形でチェックできるアプリ「ドライアイリズム」を紹介。眼科アプリのリリースは世界で恐らく初となるようだ。
このアプリは、前述のドライアイや眼精疲労といった症状と生活習慣の関連性を明らかにすることを目的に開発された。日本では2,200万人、世界に10億人いると推測されているドライアイは、最も一般的な眼科疾患である。だが、多くの人が未だに診断に至っておらず、眼精疲労、眼痛、頭痛、自覚視力の低下、肩こりなど、QOL(生活の質)を下げる原因となっているとのことである。普段からの症状の変動について、可能な限り正確な情報を収集できれば、予防や回復を早めたりすることができるはずだと猪俣氏は力説。そうした想いからアプリの開発に至ったと経緯を説明してくれた。開発はUI/UXデザインカンパニーである、株式会社オハコが協力。ユーザーエクスペリエンスの向上を目指し、アプリにはゲーム的な要素が取り入れられている。
アプリでは、まばたき回数の測定、実用視力の測定、世界的に使われている「OSDI」というドライアイ質問紙票を入力することで、ドライアイ指数が計測される。また、日々のストレス、睡眠時間、VDT(Visual Display Terminals:コンピュータのディスプレイなど表示機器を指す)作業時間、便の回数、水分摂取量などを記録し、ドライアイとの相関性を確認することができるようになっている。さらに歩行数との相関性、GPSを使ってどんなところで生活している人がドライアイになりやすいのか、どんな気象条件におかれるとなりやすいのかといったことを調査していくという。藤林氏と同じく、猪俣氏もResearchKitにおける双方向性に着目してるとのことで、利用者に対するフィードバックを提供できるのを利点として挙げていた。
自覚症状、黒目の傷の量、涙の量などの診断基準があるが、3つ以上基準を満たすとドライアイ、2つだとドライアイの疑いあり、0または1つは問題ナシとなるそうだが、臨床の現場でドライアイですか? と訊くと、殆どのケースで「違う」と返答されると猪俣氏は言う。だが、診てみると黒目の傷の量が多かったり、目が乾いていたりするそうだ。そこで、疲れやすいですか? とか痛いですか? と訊き方を変えると、ああ、そうですと答える傾向があるらしい。こういった人々のことを猪俣氏は「隠れドライアイ」と呼んでいるとのことだが、「ドライアイリズム」を使ってもらうことで、自分がドライアイであることが分ってもらえて、それで目薬を差してもらえれば仕事の効率が上がるかもしれないと、熱っぽく語る。
ただ、もちろんiPhoneは医療器具ではないし、アプリが行うのは「診断」ではないことに留意頂きたい。あくまで、ドライアイの指数を計測しているのであって、サジェスチョンとして、疑いがあります、なので病院に行ってみてくださいという流れにしてあると猪俣氏からクギを刺された。
その計測に関してなのだが、まばたきの回数はiOSのCIDetectorという機能を利用している。これはSDKとしてAPIも提供されていて一定の時間内に何回瞬きしたかをカウントできるのだ。カメラアプリの「Snow」などでも使われているのではないかと推測される。デベロッパーによっては、こういった解析エンジンを自前で組み込むこともあるそうだが、iOSでは、Appleが最初から用意しているので組み込みやすく開発しやすいと、オハコのUXデザイナー・野浪義也氏とエンジニア・李根一氏は指摘する。
オハコに協力を仰いだ部分は、UI/UXの見た目と使いやすさ。とにかく被験者に使ってもらわなければサンプルを集めることはできないから、前述の通り、アプリにはゲーム性を取り入れた。アプリ内で「まばたきを我慢する」のと「30秒間でまばたきの回数をカウントする」というのを被験者にトライしてもらうようになっているのだ。ドライアイが進むと、長い時間まばたきをせずにはいられなくなり、そこで反射が起き、瞼を閉じてしまう、だから極端に我慢できる時間が短い人、回数が多い人はドライアイの可能性アリですよという、目安になりうるのである。流れとしては、最初に回数のカウント、続いて、何秒、我慢できるかのチャレンジという風になっている。テスト回数も、最初は朝1回、夜1回と考えていたそうだが、1日2回を1週間やらないだろうという結論に至り、連続して楽しんで続けてもらうということを優先して、リリースしたバージョンに落ち着いた。
臨床研究で何が大変かというと、被験者に毎日、病院に来てもらわなければならないこと、参加者が限られること、費用がもの凄くかかることを猪俣氏は挙げる。しかし、ResearchKitを活用すれば、参加者は実質、無限大、費用も抑えられ、頻回にデータを集められる。「ドライアイリズム」のテストも本当は1週間続けてほしいとのことだが、それを通院に置き換えるとかなり厳しいものとなってしまうだろう。ResearchKitのおかげで、既存の研究では難しかった、新しい研究ができるようになるのである。
今後の医療の分野においてもいわゆるIoTは重要になってくるだろうと猪俣氏は続ける。インターネットと医療というテーマは以前から思案していたという印象を受ける。また、今回はサンプルの収集は日本国内のみで行うということだが、住んでる地域、天候などの環境などがドライアイの要因となるのではないかという予測の元に、将来的にはワールドワイドな調査ができればと、猪俣氏は今後の展望についても語ってくれた。ドライアイの発症率は、予測でしかなく、各大陸ごとのデータでもよく分からないという状況があるが、ResearchKitを使った調査は、そこに風穴を開けるかもしれないのである。
繰り返しになるが、iPhoneは現状、認可を受けた医療器具ではない。しかしながら、医療の現場をサポートするデバイスとしては大きな可能性を秘めているのだ。