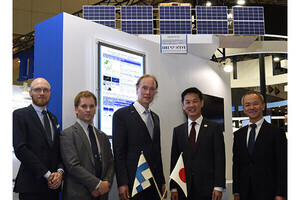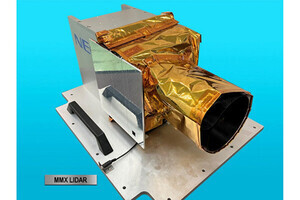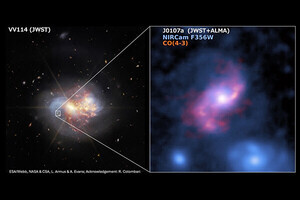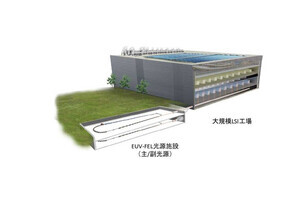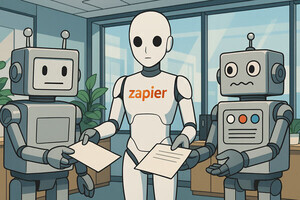2025年3月5日、GINZA SIXにあるTHE GRAND GINZA MULTIPLE HALLにて「Intel Commercial Client 内覧会」が開催された。今後の主力となる「インテル® Core™ Ultra プロセッサー(シリーズ2)」および「Intel vPro® プラットフォーム」のコンセプトや製品情報をはじめ、これらのソリューションが今後どのように活用されていくのかについて、導入事例の紹介や、ベンダー自らが発表するというイベントだった。早速その内容をダイジェストでご紹介していこうと思う。
インテルが目指す、AI PCが創る未来像
このイベントはタイトルにもあるように、パートナーやベンダー向けの情報共有を狙いとした内覧会だ。しかし、インテルの目指す未来像などを含む販売向けの内容が充実しているだけでなく、我々エンドユーザーが製品を選定するうえで有益な情報も目立っていた。
冒頭、壇上に上がったのはインテル株式会社 執行役員 マーケティング本部長の上野 晶子氏だ。
「ここ最近はPC市場がコモディティ化し、値段が安いというだけで選ばれがちな時代を過ごしてきました。しかし、AI PCというカテゴリーの登場により、多様な付加価値をお客様に提供することでPC業界全体が大きく成長できるのではないかと私は考えています」(上野氏)
同時に日本にとっても大きなビジネスチャンスだと語る上野氏。データ利活用ができる企業、すなわちAIを使いこなせる企業こそが、今後大きく伸びてくるという見方もある中、上野氏は、「データをクラウドに投入し、特定の企業だけが大きくなる。そのようなビジネス構造にしてはならないと考えます。AIをローカルで動かし、活用していけるAI PCの到来によって、これまでの日本のビジネス構造も大きく変えていけるのではないかと思っています」とその考えを語る。
そうした期待のなか上野氏は、ゼロベースからAI企業が立ち上がってくるのが、この2025年ではないかと希望を述べ、逆に「そのような企業を後押しするためにもAI PCを、エンドユーザーがなるべく多く利用できるような施策を考えていきたいと考えています」と今後の施策の方針を話してくれた。
その後AI PCの定義や、それを活かすためのプラットフォームを提供する企業やソリューションについても触れた上野氏は、グローバルだけでなく国内ISVとの協業についても説明。その事例として株式会社K-kaleidoが提供する「AI Edge Hub」や、株式会社SI&Cが開発する「インテルAI PCスタンドアロン型生成AI ソリューション」について説明した。
また、続けてIntel vPro® プラットフォームについても言及する。
「Intel vPro® プラットフォームについては20年以上続けているソリューションです。これまでは比較的大規模な企業様にご導入いただくことが多かったのですが、これからは中小企業のみなさまに対しても展開していきたいと考えています」(上野氏)
そのためにはIntel vPro® プラットフォームのベネフィットを、中小企業の方にも理解してもらわないといけないとし、「これには私たちだけでなく、パートナーの皆様のご協力あってのことだと思います。まだまだ伸びしろのあるテクノロジーですので、引き続きよろしくお願いします」とパートナー企業への協力を呼びかけ、上野氏は壇上を後にした。
優れたAI PCは優れたPCである
続いての登壇したのはインテル株式会社 IA 技術本部 部長の太田 仁彦氏だ。会場のスライドに示された「優れたAI PCは優れたPCから始まる」という言葉になぞらえ、「私もまさにこの通りだと思います」と語る太田氏。まずはインテル® Core™ Ultra プロセッサー(シリーズ2)のラインナップを改めて紹介しつつ、同氏は製品を評価していく。
「本当に長いバッテリーライフを実現しています。ただし、バッテリーライフが長くてもパフォーマンスが低ければ意味がありませんので、そこも評価ポイントになります。またAIのニーズが高まるなか優れた処理能力をお届けすると共に、あらゆる過去のアプリケーションを含めてきちんと互換性を持って動作するという部分も必要です」(太田氏)
同氏はそれらを証明するために、以前のPCのバッテリーライフと最新モデルとのベンチマーク結果を発表する。
同時に100ページ以上のPowerPoint資料をPDF化するといったパフォーマンステストでも新旧を比較した。その結果、AI PCでは太田氏がテスト環境を説明している間に処理が完了したが、旧世代のPCは未だ変換作業も半ばという状況が見て取れた。太田氏は「これらの性能差が、みなさんの生産性に大きな影響を及ぼすことについてを、イメージしていただければと思います」と話す。ビジネスPCにおいて、デスクトップではなくモバイルPCが主流となった昨今では、生産性の観点でユーザーから性能を求められる情報システム部門の担当者も多いだろう。インテル® Core™ Ultra プロセッサー(シリーズ2)が、業務で使用する殆どのアプリケーションとの互換性の担保と併せて、性能でも大幅な向上を見せている点は、情シスにとって見逃せないポイントだ。
また、今後AI機能があらゆるアプリケーションに実装され、大きく広がっていくのが2025年以降であるとし、99%以上の互換性を保つための努力として、より多くのソフトウェア会社と協力していると発表。現在では150例以上のISVと協業しており、動作検証をおこなっているそうだ。
最後にセキュリティレポートについて話す太田氏は、「私たちは脆弱性の問題を自ら発見し修正しています。さらにそういった情報はオープンにしており、早期解決に尽力しています」と、セキュリティへの取り組みに自信をのぞかせる。
そして例に挙げられたのが、2024年7月に発生した、あらゆる端末上でブルースクリーンが出るというトラブルが起こった話であり、アメリカではいわゆるブルーフライデーなどと呼ばれている事例だ。業界を問わずに発生したこの現象に頭を悩ませた情報システム部門の担当者も多いだろう。
この問題が起こったとき、インテルのIntel vPro® プラットフォームのチームがすぐに集結。数時間のうちに問題箇所を特定し、対策の手順書を作成したそうだ。当時の対応について太田氏はこう振り返る。
「とても単純な手順書でIntel vPro® プラットフォームからリモートで問題のあるPCへ接続し、手順通りにこのように作業すれば良いですよ、といったPDFを配布しました。問題が起こった各企業の皆様は数時間後には解消しました」(太田氏)
一方、Intel vPro® プラットフォームを持たない企業では、IT管理者が直接対応をするしかなく、問題解決には時間が掛かったのだという。企業においてさまざまな仕組みがIT化している現在、こうしたIntel vPro® プラットフォームの存在は企業の事業継続の観点において大きな安心材料となるだろう。
こうしてIntel vPro® プラットフォームの強い有効性を示すエピソードを紹介し、太田氏は講演を終了した。
【情シス必見!!】パートナー企業や導入企業もイベントに参加
最新情報や導入事例をご紹介!
当日はエコシステムパートナーやIntel vPro® プラットフォーム導入企業による登壇もあり、会場を盛り上げた。どの企業の発表も有意義な内容だったが、誌面の都合によりご紹介にとどめるしかないのでご了承願いたい。
株式会社カタオカ
Intel vPro® プラットフォームの導入により、リモート管理体制を構築。ヘルプデスクやクライアントPC管理をデジタル化し、管理者負担を大幅に軽減することに成功した事例を紹介してくれた。中堅・中小企業におけるIntel vPro® プラットフォームの活用ということで、これまでにあまり例のなかった活用であり、多くの注目を集めるパートとなった。ぜひPC管理業務において管理者負担が課題となっている情シスの皆さんには、参考にしていただきたい事例だ。
NSW株式会社
Intel vPro® プラットフォーム、インテル® EMAを活用した、PCリモート対応強化基盤を提供するNSW社。リモート操作環境の構築はもちろん、事前のPoCについてもサービスとして提供される。これから導入したいと考える企業には最適なソリューションであるとともに、実際の導入イメージもわく内容であった。PCのリモート管理対応を検討している企業にとっては見逃せない情報だろう。
日本マイクロソフト株式会社
マイクロソフトのAI戦略と、Copilot+ PCについてのポイントを説明してくれた。Windowsに用意されているセキュリティ機能や、AI機能についても解説。マイクロソフトとしても、Copilot+ PCの時代がすぐそばまで来ていると今後への期待を語った。
株式会社アクセル
パチンコ・パチスロメーカー向けのサービス・ソリューションを提供しているアクセル。AIソリューションとして「DX insight」を提供。AIを活用し、企業のDXのすべてを一元化することが可能となる。インテルのテクノロジーを積極的に活用し、演算処理を高速化している。
トレンドマイクロ株式会社
パチンコ・パチスロメーカー向けのサービス・ソリューションを提供しているアクセル。AIソリューションとして「DX insight」を提供。AIを活用し、企業のDXのすべてを一元化することが可能となる。インテルのテクノロジーを積極的に活用し、演算処理を高速化している。
ブラックマジックデザイン株式会社
映像の世界ではワールドワイドなシェアを持つブラックマジックデザイン。同社の編集ソフトウェア「DaVinci Resolve」は無償版と有償版があり、有償版では数々のAI機能を利用できる。AI機能をはじめ、ソフトウェアは常にアップデートされ続けており、利用者は常に最新の状態で動画編集がおこなえる。
この6社の講演が終わったのち、インテルによる販売情報やマーケティングツールの説明があり、すべてのプログラムが終了。約2時間のイベントだったが、内容が非常に濃く、時間を感じさせない内覧会となった。
イベント直後の上野氏に直撃インタビュー!
それでは最後に内覧会が閉幕した直後に上野氏に会う機会があったので、その時の模様をお伝えしたいと思う。今回の内覧会を開いた背景や、AI PCのこれからなど、踏み込んだ話が伺えたのでぜひご一読願いたい。
―本日はお疲れさまでした。パートナー様やベンダー様には良いメッセージになりましたね。
上野氏:
ありがとうございます。インテル® Core™ Ultra プロセッサーも2世代目に突入するわけで、AI PCに加えてMicrosoft様のCopilot+ PCにもインテルのプロセッサーが入ってきます。さらには、AI機能についてもソフトウェアベンダー様を中心に2025年はたくさんのソフトウェアや機能が搭載されていきます。
私たちが強調したいのは、インテルだけでAI活用全体を盛り上げようというのではなく、あらゆるベンダーやパートナーが一緒になって歩んでいくことが大切であって、それができてはじめて本当の意味でのAI PC時代がやってくるのだと考えています。
―生成AIについて、クラウドベンダー一強ではだめだとおっしゃっていました。これにはどのような意味があるのでしょうか?
上野氏:
これからも様々なAIソリューションが出てくると思いますが、AI PCでそういったものを目に見える形で使うというイメージをみなさん持っていると思います。しかし、AI PCの醍醐味は何かというと、裏でAIが粛々と仕事をしてくれていることなのだと私は思っています。
例えばセキュリティソフトのAIは、バックグラウンドでユーザーの情報を守っています。知らないうちにAIがごく自然な形で、何も邪魔をせずにしっかりとした働きをしてくれるのが良いのです。
例をあげるとインテルが「Centrino」を出したときでしょうか。当時はWi-Fiを持っている人のほうが少なくて、サービス開始直後はとても珍しい仕様でした。しかし、今はPCを開けばWi-Fiに勝手につながるのが当たり前になり、誰もそれを特別なこととは思いません。
―なるほど、AIについても同じことが言えると。
上野氏:
そうですね、AIを立ち上げることが大事なのではなく、自然に使っていることが大切なのです。キラーアプリがどうだという話が良く出てきますが、どうぞ使ってくださいではなく、先ほど触れたセキュリティソフトや、グラフィック編集ソフトウェアのように、意識をせずにAIが使えることが普遍的であり、汎用的であるのがこれからのAI PCの世界だと思っています。
―先ほどもおっしゃっていましたが、パートナーやベンダーなどと一緒に考えていきたいというのはそういう思いから来ているのですね。
上野氏:
AI PCにしても、Copilot+ PCにしても、ようやくデバイスが揃いました。AI機能をバックグラウンドで走らせてくれるソフトウェアメーカーさんも出てきました。そして販売パートナーさんがそれらを供給し、AI PCにしろ、Intel vPro® プラットフォームにしろ、実際にお使いくださっている事例も増えてきました。それを発表させていただいたのが今日だったのです。三位一体といいますか、関連企業が集まってAI PCの世界を具現化し、汎用化していく。これをみなさんで考えていきたいのです。
―それは我々エンドユーザーにとっても、価値のあるサービスやデバイスが手に入れば大きなメリットを受けられますね。
上野氏:
その通りです。みなさんの生産性を大きく向上させたり、セキュリティを強固にしたりと、AI PCがあることで受けられる恩恵は今後ますます大きくなっていきます。AI PCはそれなりに高価にはなりますが、それだけの付加価値は十分にある存在だと思います。本日ご説明した通り、PCとしても非常に優秀なので、1年ごとに買い替えるということもなく、長く使えますから、3年後にPCでできることが、AI PCを手に入れるかそうでないかで大きく違ってくるでしょう。
AIが当たり前になる時代にふさわしいPCに搭載されているのが、インテル® Core™ Ultra プロセッサー(シリーズ2)であり、Intel vPro® プラットフォームだと考えています。PCのご購入をお考えのみなさまや、自社PCの刷新を考えている方は、ぜひAI PCを選んでいただきたいですね。
―ありがとうございました!