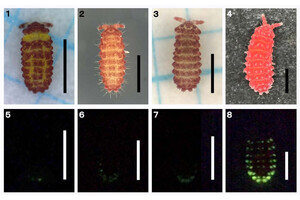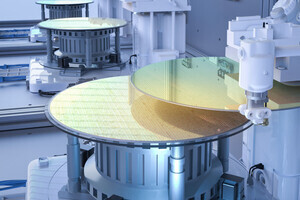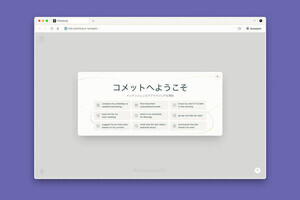10月30日に米国のジョー・バイデン大統領がAIの安全性の確保や技術革新を図るための大統領令に署名した。これは米国における初めてのAI(人工知能)を対象とした法的拘束力を持つ規制だ。ポイントは、それが大統領令で発令され、50以上の連邦政府機関に対して約150の要件を課す広範な令であることだ。
米国初のAIを対象とした法的拘束力を持つ規制が発令
岸田首相のフェイク動画がSNSで拡散された騒動が起こったこともあり、日本でもAI規制の議論が広がっているが、バイデン大統領がAIの安全性の確保や技術革新を図るための大統領令を発令した。
バイデン大統領が署名した大統領令14110号は111ページに及ぶ。それを読んでまず思ったのは米国らしい指針であること。AI規制ではあるが、バイデン大統領が「米国が責任あるAIイノベーションに向けて先導する」と強調しているように、AIのリスクと革新的な利点のバランスを図りながら、ルールづくりにおいても米国が主導的な役割を果たそうとしている。
また、高度な専門知識や技能を持つ移民を含む「AI人材」の採用活動を拡大する指令も含まれており、不謹慎と言われるかもしれないが、読みながら夏に観たマンハッタン計画を描いた映画「Oppenheimer」を思い出すこともあった。
8つの指針で責任ある安全なAIを実現するための原則や優先事項を示す
大統領令は、以下の8つの指針で責任ある安全なAIを実現するための原則や優先事項を示している。
-
安全性とセキュリティ
Dual-use foundationモデルの可能性があるAIシステムを開発、または開発する意図を示す企業に対し、国防生産法に従って、その活動とモデルに関する詳細な情報を継続的に連邦政府に提出することを求めている。これには、米国立標準技術研究所(NIST)のガイダンスに基づいて、関連するAIがレッドチームテストにおいてどのようなパフォーマンスを発揮したかの結果も含む。また、大規模なコンピューティング・クラスターの取得、開発、保有について、企業はその存在と場所、それぞれのクラスターで利用可能なコンピューティング・パワーの総量などを商務長官に報告するよう求めている。
Dual-use foundationモデルというのは、モデルが持つ二重の可能性を示す。例えば、GPT-4のような大規模言語モデルは、テキスト生成、翻訳、情報の要約、質問への回答など、多くの異なるタスクに使用される。一方で、誤った情報を広めたり、詐欺に使われる可能性もある。同じモデルが有用な応用だけでなく、誤用や悪用の可能性も含む。そうしたAIシステムの公開前の検証を義務付けることで、野放図なサービス開発競争に歯止めをかけ、安全、安心、信頼できるAIシステムを確立しようとしている。
国防生産法は、緊急時に政府が産業界を直接的に統制できる権限を付与する。戦争時やCOVID-19の流行拡大時のような国家の緊急時に使用されてきた法律である。同法に基づいた権限を明示していることから、AIの影響と対策の必要性をバイデン政権がいかに重視しているかが判る(具体的な条項は引用していない)。
米国民のプライバシー保護
AIがもたらすリスクを含め、米国人のプライバシーをよりよく保護するため、プライバシーを保護する技術の開発と使用を加速させる。米国人、特に子供を保護するための超党派のデータプライバシー法を速やかに可決するよう議会に要請。AIシステムで使用されるものを含むプライバシー保護技術の有効性を評価するためのガイドラインを作成する。公平性と公民権の推進
AIの無責任な使用は、司法や医療における差別や偏見、地域的な格差を生み、それらを深化させる可能性がある。連邦給付プログラムや住居問題、さまざまな契約において、差別や偏見の助長にAIアルゴリズムが使用されないようにする明確なガイダンスを提供する。医療、教育における活用
AIによって人々が必要としているものをより安く、より安定した供給の実現が期待されている。大統領令では、医療におけるAIの責任ある使用と、安価で生命を救う薬剤の開発促進を指示。また、教育の現場でAIを活用した教育ツールを導入する教育者を支援していくリソースの作成など、教育を変革するAIの可能性を探る。労働者の支援
雇用転換、労働基準、職場の公平性、安全衛生、データ収集に取り組むことで、AIの普及で労働者が被る不利益を減らし、利益を最大化するための原則とベストプラクティスを開発する。イノベーションと競争の促進
研究者や学生がAIデータにアクセスできるリソースの試験運用を通じ、米国全体の研究を促進する。医療や気候変動など重要分野における助成金を拡大、米国全体の研究を促進する。世界における米国のリーダーシップの推進
国務省と商務省が協力し、国際的な枠組みの構築に向けた取り組みを主導する。国際的なパートナーや標準化団体との重要なAI標準の開発と実装を加速し、技術の安全性、信頼性、相互運用性を確保する。政府による責任ある効果的なAI利用の確保
政府全体でAI専門家の迅速な採用を加速していくとともに、権利と安全の保護について明確な基準や各省庁がAIを利用する際の明確なガイダンスを発行する。
大統領令はAIに関する政策と優先事項を明確にするために継続的に取り組んできたことの集大成
このAI新規制のポイントは、これが大統領令で、このボリュームということだ。
大統領令は迅速に発布でき、大統領自身が考えている政策を速やかに実行に移せる即効性のある手段である。ただし、連邦法に比べて効果が限定的で、新しい大統領が就任すると、前任者による大統領令を変更、撤回、または新たな令を発行することができる。
つまり、このAI新規制は来年の大統領選の結果次第でまったく変わってしまう可能性もあるのだが、大統領令だから早く実施に移せる。そして、この大統領令は90日から1年の間に実施されるように作成している。例えば、NISTは令が署名された日付から270日以内にレッドチームテストの基準を設定することを含め、ガイドラインとベストプラクティスを確立しなければならない。
米国はEUに比べて連邦プライバシー法の成立に苦慮している。しかし、AI技術の進展により、プライバシー保護を含めた対策の必要性がさらに強くなっている。連邦法でのAI規制を待っていたら、成立がいつになるかわからない。連邦プライバシー法のようにずるずると引き延ばされてしまうかもしれない。だから、大統領令で発行されたことに意義があるのだ。
しかも、このボリュームである。大統領令は、バイデン政権がAIに関する政策と優先事項を明確にするために継続的に取り組んできたことの集大成といえる。AIの安全性の確保から開発促進、労働者支援、国際的な枠組みまで広範におよび、50以上の連邦政府機関に対し、約150の要件を課している。それらが一斉に令の実施に向けて動く。
各省庁は独自のAI最高責任者とAIガバナンス委員会を設置し、行政管理予算局(OMB)長官を長とする省庁間協議会に代表を出す。各省庁は具体的な指示を受ける一方で、「AIの効果的かつ適切な利用を強化し、AIのイノベーションを促進し、AIのリスクを管理する」ための大きな自由裁量権を持つことになる。
この幅の広さと、各省庁が独自のガイダンスを策定できる自由度の広さを懸念する声もある。例えば、FTC(米連邦取引委員会)は、リナ・カーン委員長の下、反トラスト法問題に積極的な姿勢を示しており、AIに関連して公正競争や消費者・労働者保護に取り組む権限を行使することが予想される。それがAIの枠を超えてIT産業に影響が広がる可能性がある。
EUはAI法で、主にAI技術がもたらすリスクの度合いに基づいた規制を目指している。それとは対照的に、米国はAIのリスクを理解し、正しく導くことを急務とするとともに、AIの潜在的な利益を責任を持って開発し、活用することにもほぼ同等の重点を置いている。
そして、大統領令は、米国をAIの世界的リーダーとして位置づけるための取り組みについても長い章を割いている。例えば、AIが生成したコンテンツがもたらすリスクへの対策となる要件として、商務省に、AIが生成したコンテンツを明確に表示するためのコンテンツ認証と電子透かしのガイダンスを策定するよう求め、さらに連邦政府機関がそれらのツールを使用することで「民間企業や世界中の政府の模範となる」とファクトシートに記している。
では、大統領令の発令でAIは安全・安心なものになるのだろうか?
社会的リスクの軽減、電子透かしのような分野での具体的な方向性を示したAI規制をこれほど早くスタートさせたことには多くが支持を表明している。だが、予想されるAIのリスクに対する有効性については疑問符をつける声が少なくない。次回はそうした声を紹介しながら、生成AI開発の今後について考える。