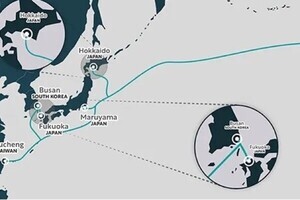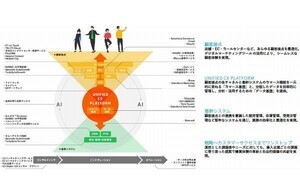6月米国消費者物価指数(CPI)は前年同月比+9.1%と市場予想の同+8.8%を上回り、前月の同+8.6%からさらにインフレが加速した。実際、生活していて出費の増加が止まらない。ガソリン価格の上昇が緩やかになってきたと思ったら食品、そして家賃と別のカテゴリーの上昇が加速している。普通のラーメンが円換算で1500円以上、人気店なら1杯2000円以上が当たり前なのが今の米国である。
しかし、そんな米国でも値上げに踏み切らない企業がある。倉庫型の会員制スーパーマーケットCostco(コストコ)だ。同社は、店内のフードコートで1/4lbのホットドッグと20ozのソーダのセットを1.50ドル(日本では180円)で販売している。30年以上も価格が据え置きされている人気メニューだ。それがどのくらい安いかというと、物価上昇に合わせて値上げを実施していたら、いま米国でCostcoのホットドッグは4.10ドル以上が適正と言われている。
だから、さすがに今回の物価上昇で値上げするだろう、値上げしても会員から文句は出てこないと言われていたが、Costcoはホットドッグの価格維持を宣言した。
Costcoのホットドッグは、1984年にホットドッグ大手Hebrew NationalがCostcoのサンディエゴ店の出入口に屋台を出したのが始まりだ。CostcoとHebrew Nationalの取り引きが拡大し、CostcoのフードコートにHebrew Nationalのホットドッグが採用された。それから1.50ドルという価格が堅持されている。2009年にHebrew Nationalが価格を引き上げた際に、CostcoはプライベートブランドKirklandでのホットドッグ製造に踏み切った。2013年にCoca-Colaが値上げした時にはソーダをPepsiに変更した。そうして原価や仕入れ費用を抑えてきたが、当然1.50ドルという価格は原価割れしている。
なぜ、そんなに1.50ドルにこだわっているのかというと、ホットドッグは人気メニューを超えた名物メニューだからだ。買い物のついでに激安で1食済ませられるから、他のスーパーではなくCostcoを利用する買い物客が少なくない。Costcoの会員になる大きな理由の1つになっている。
大量に仕入れた商品を安く販売しているCostcoは粗利率が11〜13%と低い。WalmartやTargetのような量販大手は20〜30%である。内容を見ると、物販の利益はさらに薄く、ホットドッグのように原価割れの商品も少なくない。では、同社が何で儲けているのかというと会費である。売上の大部分がそのまま利益になる会費が全体の利益の約7割を占めている。そのため、メンバーシップの更新率をなにより重視しており、会員の満足度の向上に努めて更新率90%+を保っている。だから、会員に愛されている名物メニューであるホットドッグを値上げしない。
「いやいや、ホットドッグを安くして、その分を会費の値上げで埋め合わせているんでしょ」と思うかもしれないが、Costcoは5〜6年サイクルの会費値上げを明言している。インフレになったからといって会費を引き上げることはない。
ただ、今年は前回2017年の値上げからちょうど5年が経過したタイミングで、春から夏に値上げが発表されると予想されていた。ところが、Costcoは会費の値上げもしばらく様子を見る考えを示した。
あらゆるものの価格が上昇して消費者は値上げにアレルギーともいえる感情を抱いており、今は値上げするタイミングではないという判断だ。値上げするなら消費者がある程度落ち着いてから。値上げは行うが、過去の値上げと同様にメンバーシップの更新率に影響しないように実施するという。更新率維持を優先する姿勢にブレがない。
Costcoというと安売りが強みと思われがちだが、同社の本当の強みは消費者の心理を読み取る力だ。Costcoの安さの理由の1つに販売商品数の少なさがある。倉庫型なのでたくさんの商品を販売しているように思われるが、1店舗で販売している品目数は約4,000点。大手スーパーマーケットの約30,000点に比べて圧倒的に少なく、コンビニ並みと言える。それだけ絞り込んで大量仕入れするから価格を引き下げられるのだが、販売品目数が少ないだけに売れ行きが鈍いといつまでも在庫が店舗に積み上がったままになる。いつ行っても同じ商品しかなかったら会員の足が遠のく悪循環になるから、需要を見極め、大量仕入れでも素早く売り切れる商品を仕入れるバイヤーの力が問われる。
ホットドッグを1.50ドルで販売しているが、Costcoのポリシーは"良い商品を安く"だ。低価格帯の商品の選択肢は少なく、一方で高額の家電製品も扱い、そして商品の回転を重視した品揃えで会員に次の来店までになくなってしまう可能性を意識させる。Costcoはディスカウントスーパーでありながら高額所得者の利用も多く、シリコンバレーのような賃料が米国で最も高い地域でもサンタクララ郡だけで9店舗と数多く展開している。そうした高い分析力を、会員の満足度を引き上げるサービスに結びつけて90%+の高いメンバーシップ更新率を実現しているのだ。
TargetやWalmartの決算が振るわず小売りが低迷し、今年の後半から来年にかけて米国のリセッション入りの可能性が指摘される中、Costcoはいまユニークな評価を獲得している。ちなみに同社の創業は1983年だ。経済の悪いニュースで「30年ぶり」という言葉をよく見かけるようになったが、1980年と81年に米国は消費者物価上昇率が10%を超え、そして1982年と83年に失業率が10%近くまで上昇した。そんな米国経済がどん底の時期に創業したのだが、不況時は新しいアイディアを試すのに悪い時期ではない。ビジネスの質が早期に試され、不況を乗りきって回復の風が吹き始めたら、長く続いた制約から解放された消費者は新しいアイディアや事業に対してよりオープンになる。そうしてCostcoは、入荷したパレットのまま商品を大型の倉庫に並べて販売するという新たな倉庫店スタイルを浸透させたのだ。