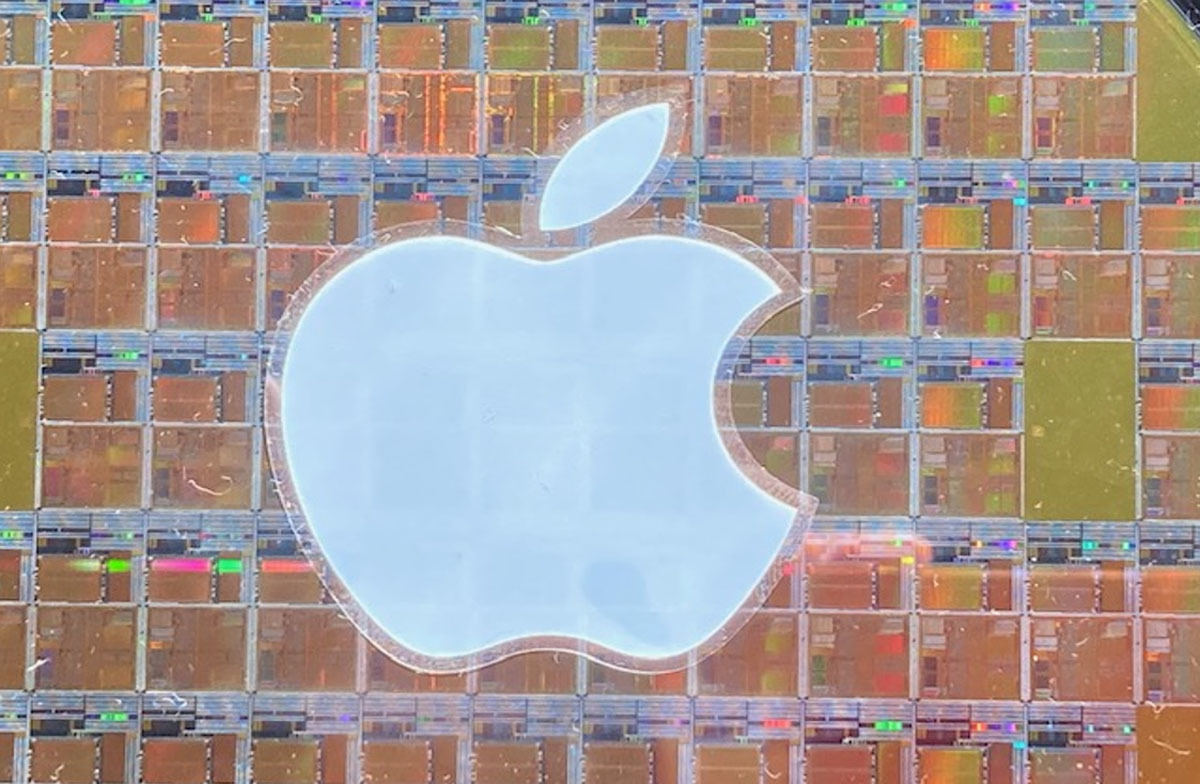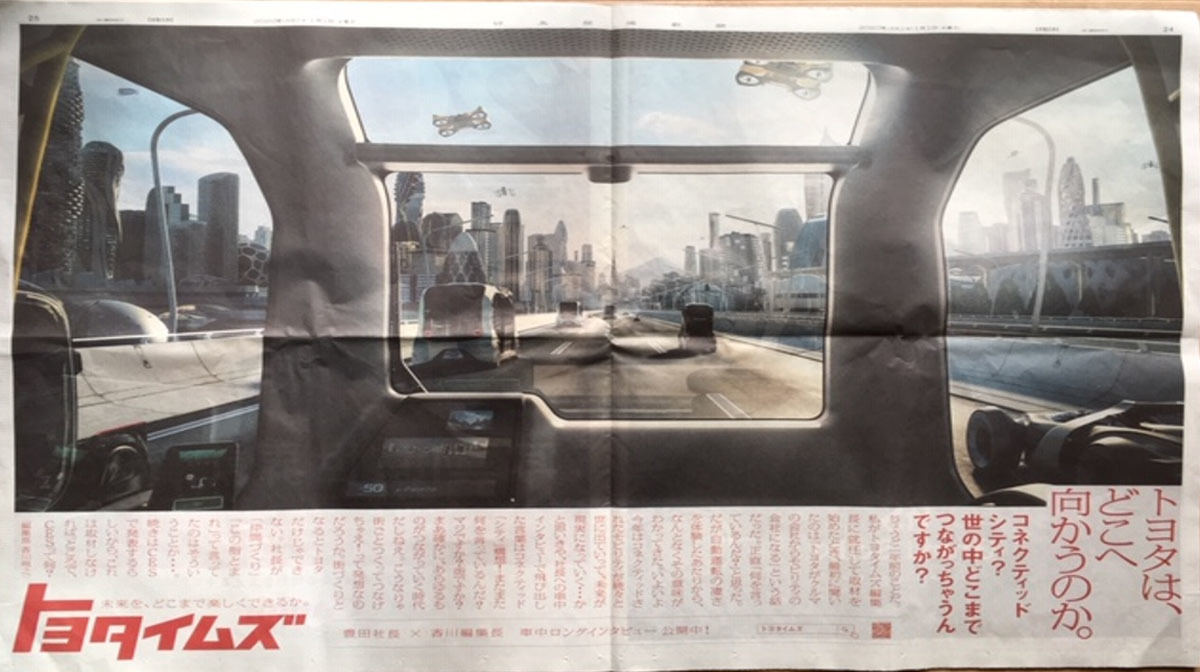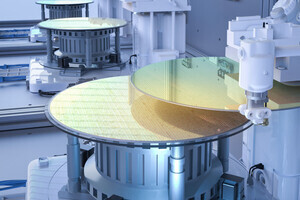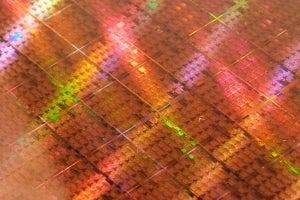2020年ももう終ろうという時期になってきたということで、半導体業界の今年一年を振り返ってみたいと思う。今年、2020年は驚異的なスピードで加速するイノベーションによって新旧役者交代の兆しを感じさせる年になった印象がある。
Intelの凋落(?)とAMDとNVIDIAの躍進
2020年は世界最大の半導体企業Intelにとって本厄年だったといえる。私もこのコラムで何度かIntelの変調について辛辣な調子で取り上げたが、胸の内では「とは言ってもIntel、そのうち驚異的な策を強引に打ち出してくるのだろう」と思っていた。
しかし、Intelのカムバックはとうとう感じられないまま年を越すことになりそうだ。今年の第2四半期の発表まではIntelに対する私の胸の内は変わらなかったが、第3四半期の発表を受けてIntelの変調について確信に至った。最も気になるのが下記の点である。
- 競合AMDがパートナーシップを組むTSMCの7nmの最先端プロセスに対抗するプロセス技術を明確に打ち出せていない。
- 利益率が最も高いデータセンター用のサーバーCPUのセグメントでの業績不振が明らかになってきている。これには競合のAMDによるシェア奪回がある。
- 外部委託生産の可能性に何度か言及しているが、まだ明確な方向性が打ち出されていない。「偏執狂だけが生き残る」と豪語したかつてのIntelらしからぬ曖昧さである。
一方、x86アーキテクチャーでの唯一の競合AMDはCPU/GPUともに次世代製品のリリースをスケジュール通りに繰り出し、その生産を盤石のTSMCがしっかり支えるという見事なパフォーマンスを示した。10月にはFPGAの大手Xilinxの買収も発表し、次の大きな一手を明確に打ち出している。
またGPUでAMDと市場を分け合うNVIDIAはAIや自動運転などの成長分野での存在感を益々大きくし、時価総額ではIntelを大きく上回る脅威となっている。さらにはx86アーキテクチャーの天敵ともいえるArmを巨額の買収で手の内にしている。シリコンバレーでは軒を連ねるこの3社の2020年は、躍進する大関(関脇?)AMD/NVIDIAと凋落傾向の横綱Intelという明暗分ける年となった。これが新旧役者交代の兆しなのかどうかは2021年に明らかとなる。
Apple Siliconが示唆するもの
Intelの凋落を感じさせるもう1つの“事件”がApple Siliconの登場である。Appleが満を持して発表したMac用CPU「M1」のデビューは業界で大きな衝撃を持って受け止められた。発表から間もなく報道されたそのパフォーマンス評価はこのCPUが「ただものではない」ことを十分に示すものであった。
“新しもの好き”の私の仲間内でもM1搭載の新しいMacを早速手に入れた人もあって、その総合パフォーマンスについて実際にいろいろと聞く機会があった。M1はその高速性能に加えて、省電力、コストとすべての分野で通常の新アーキテクチャーCPU登場の常識をほとんど覆した印象を持った。
米国のアナリストによる記事の中には、M1の登場をPowerPCベースの独自CPUにこだわった今は亡きスティーブ・ジョブズが、市場原理の制約からIntelのx86アーキテクチャーに頼らざるを得なかったAppleの積年の口惜しさを晴らすApple反逆の狼煙(のろし)、などとドラマチックに表現する記事も出てきて業界の注目は大いに盛り上がっている。
M1を含めて、Apple自社開発のCPUコアはArmである。Armは持ち前の省電力に加えて、マルチコア化でスケーラブルであるという優位性を持っていて、AppleはこれをスマートフォンからPCへと水平展開する。そのArmはNVIDIAが取り込むことになったので、Intelは半導体の競合であるNVIDIAからも脅威を受けることになる。AppleはCPUの他にGPUやモデムなども自社開発をしているという話もあって、2021年にはこれらの自社開発半導体を搭載した製品が発表される可能性もある。
2020年は、Appleに限らずGAFAをはじめとするプラットフォーマーたちが自社開発のAIアクセラレーターのチップを自社が運営するデータセンターに使用していることがもはや業界全体の周知の事実となった年でもあった。また、このトレンドを最先端のプロセスで支える台湾TSMCの存在がさらに大きくなった年でもあったといえる。
Toyota vs Tesla
2020年は相変わらず積極果敢なTeslaの話題が大きく取り上げられた。2012年に発売された高級セダンのモデルSの後、SUVモデル、低価格モデルからピックアップトラックへとEVの可能性を急速に拡大したTeslaの時価総額が、今年の夏ごろにトヨタを抜き去ったという話題で市場に大きな激震が走った。
株価に発行株式数を掛け算して得る時価総額は、市場がその会社の将来に対する期待値の総額に過ぎず、実際のビジネスの規模を表すものではもちろんない。自動車の販売台数でいえば2桁の違いで比較にならないが、世界の自動車業界に君臨する横綱ともいえるトヨタは急速に変化する市場環境に対して非常に思い切った対応をとっている。その一番の例がトヨタが静岡県裾野市で2021年2月に着工予定の実証都市「コネクティッド・シティ(ウーブン・シティ)」である。この壮大な構想についてはトヨタは2020年元旦の全国紙に30段の広告を掲載して高らかに宣言している。その計画は単なるマーケティングではなく実際に実証実験を始めるためのインフラストラクチャーを建設しようという壮大なプロジェクトである。トヨタは本気だ。
19世紀後半に商用化された化石燃料をエネルギー源とした内燃機関のもっとも身近なアプリケーションである自動車業界でトップに昇りつめたトヨタは、その地位に安直とせずにハイブリッド車の市場でもトップを走る。
しかし脱炭素の世界トレンドにあってはEVへの移行がその将来を分ける必須課題である。近い将来に来るであろうEVの世界では、トヨタが今までに想定しなかった異業種企業からの加速的な参入が考えられる。それに備えた実証実験での実績はトップ企業トヨタにとっては一刻を争う喫緊の課題である。
EVシフトはまさに「100年に一度のパラダイムシフト」であることは明らかだ。報道によれば「ウーブン・シティー」プロジェクトには世界の「トヨタ」の冠はまったく見られないという。世界的な規模で展開するトヨタの巨大な実ビジネスと将来に対する備えは完全に分離しないと、そのスピードが担保されない。その意味では世界のトヨタのCEOである豊田章男氏のトップダウンの姿勢は今後のトヨタの将来について希望を抱かせるものであるという印象がある。
2020年の私のコラムは今回で最後です。ご愛読いただいた皆様に感謝いたすとともに2021年に向けてのご健勝を祈念いたします。よいお年を!!