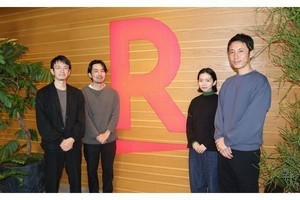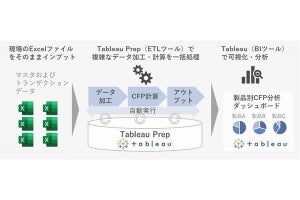「防衛費を増税で」「異次元の少子化対策」「リスキリング助成金」「賃金値上げ」など。岸田政権が推し進めるさまざまな施策は、その善し悪しや賛否はさておき、世界の中での日本が「今のままでは立ち行かない状況」であることを表しています。そうした変化の波は当然、企業にも押し寄せ、今後はさまざまな変革を余儀なくされていくでしょう。2023年の幕開けはそんな空気が漂っています。では、現場のリーダーとなる役職者は自らどんな“チェンジ”をしていくことが求められるのでしょうか。
→連載「あつみ先生が教える SDGs×ビジネス入門」の過去回はこちらを参照。
任せられた領域の未来を予測することの必要性
「バックキャスティング」という言葉をご存じでしょうか? 未来の目標から逆算して、現在なすべきことを考える方法を指す言葉で、SDGsで推奨されている考え方です。
この逆が「フォアキャスティング」。過去の実績やデータから実現可能と考えられるものを積み上げていくやり方で、従来、日本企業が得意としてきたやり方です。
しかし、世界中でさまざまな変化が起きている昨今では、自社が積み上げてきた経験やデータから予測できないことが発生するケースも少なくありません。例えば、ロシアによるウクライナ侵攻によるエネルギーの危機が現実に起きるとは、多くのビジネスパーソンは予測していなかったでしょう。もちろん、バックキャスティングで考えれば予想できた、というものでもありません。しかし、世界の情勢から今後の日本や自社のリスクとチャンスを予測することが、今まで以上に求められる状況となっていることは明白です。
そこで一層、知っていただきたいのがSDGsの知識。このSDGsをエコ活動だと捉える向きもありますが、それは一側面にすぎません。世界の社会課題を17のゴールにまとめたものがSDGsなので、SDGsを知ることは社会の潮流を読むことにつながるのです。
では、SDGsとバックキャスティング。我々は何から考えていけばよいのでしょうか。
例えば、最もビジネス界と関連性が強い目標の一つである目標13「気候変動に具体的な対策を」から考えてみましょう。この目標において、よく語られる重要指標が日本政府の掲げる「2030年までのCO2の45%削減」というものです。この指標が企業にどんな影響を与えるのか。当然ながら生産過程やサービス提供過程におけるCO2の削減は求められます。しかし、まず第一歩として、自社が現在どのくらいCO2を輩出しているのかを把握しないことには、45%がどの程度のものなのか、計画することすらできません。
この気候変動に対する対策は、プライム市場上場企業には開示が義務化されています。それなら中小企業は関係ないのか、と言うとそんなことはありません。プライム市場上場企業と取引関係にある中小企業もまた、同じように対策が求められます。自動車メーカーの例で言えば、2021年、ポルシェが自動車部品メーカーに再生可能エネルギー100%での製造を義務化すると発表しました。
SDGsを良く知らない状態だと、大企業と中小企業は別物と考えがちですが、そんなに甘くはない現実があります。なぜこうした連鎖が起きてくるのでしょうか?
サプライチェーンを遡って評価されるのがSDGsの特徴
SDGsの考え方の中に、「企業が提供する商品やサービスの全工程において責任を持つ」というものがあります。例えば、CO2の排出量も「サプライチェーン排出量」と呼ばれ、事業者自らだけでなく、原材料調達・製造・物流・販売・廃棄など事業活動に関係するあらゆるプロセスで発生する排出量について削減の努力をする必要があるのです。
先ほど触れたポルシェも、この考え方に基づき、自社の製品の再生可能エネルギー化を推進する上で、部品供給メーカーにも同じように再生エネルギー化100%を求める決定をしたわけです。
また、企業の責任は何もエネルギー問題だけに留まりません。例えば、目標8「働きがいも経済成長を」には「強制労働撲滅」というターゲット(目標)が含まれています。安価に調達できる原材料が現地で強制労働の上に生産されているとしたら。これもまた企業の責任として追及されることになるのです。
こうしたリスクを洗い出すためにもサプライチェーンを書き出して、リスクを洗い出しておくことをお勧めします。その際は、以下の工程でチェックすると良いでしょう
- 原材料、サプライヤー、調達、生産、物流、販売、消費、廃棄でどんな工程や企業が関わっているか洗い出す(ここが最も大掛かりになるため、難しければまずは自らの業務範囲に近い2から始めても良い)
- サプライチェーンで話題になっているSDGsの目標を見つける
例:食品メーカー|生産工程で出る廃棄物→目標12「つくる責任 つかう責任」 - その時に国や競合企業が設定している定量的な重要指標を探す
例:2030年までに2000年度比で食品ロスを半減 - 2の指標と比較したときに自社がどれくらい達成できているか
例:2000年比で15%の削減 - 2030年までに達成するためのロードマップ
例:3年(2026年)で30%、5年(2028年)で40%、7年(2030年)で50% - 4を達成するための具体的タスクの洗い出し
こうした事業計画を描いて、経営層を説得し、着実に実行していく。これは社風によっては非常に大変な道のりになることもありますが、今、社会から求められている仕事の進め方でもあります。
役職者に女性が増加する未来 -「ポジションが増える」とは限らない
一方、サービス以外の部分でも変化は起こることが予測されます。まず女性の管理職は大幅に増加するでしょう。内閣府男女共同参画局の調査によれば、日本はそもそも諸外国と比較したときに圧倒的に女性の管理職比率が低く、役員比率で言えば12.6%です。これはフランスの45.3%を筆頭にヨーロッパ諸国が30%以上、アメリカも29.7%と比較しても群を抜いて日本が低いことがわかります。
こうした中で、政府は2020年代の早期に30%を目指すのが望ましいとしており、今後は女性管理職の増加が加速することが予測されます。そこから企業内でどんな変化が起こるのでしょうか。ポジションがその分、増えれば問題ありませんが、従業員数が年々増える成長企業以外は、その可能性は薄いでしょう。既存の管理職においては流動性が高まり、競争率が高くなるのは必至。今の自分からさらに成果を上げていかないと、出世どころか現在のポジション維持すら難しくなる未来が予測されます。
管理職として求められる人材になるには?
こうした状況の中、管理職として求められる人材になるにはどうしたらよいのでしょうか?
例えば今、「DX人材」への需要が高まっています。経済産業省は、DXの定義を「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」としています。つまり、DX人材はそうしたことを推進できるITスキルと経験を持った人材のことを指すわけです。ITという言葉が日本で叫ばれ始めたのが2000年頃。そこから20年経って、デジタルを活かしたビジネス経験を積んできた人は今、DX人材と言われて売り手市場となっています。
同様に考えると、SDGsという言葉は、ようやく日本のビジネス界で注目され始めたところです。ここから10年後、SDGsにまつわる経験を積んだ人は「SX人材」として重宝されることでしょう。
まずはSDGsの基礎的な概念や企業事例を学び、その上で既存事業を改革したり、新規事業を創出したりする。そうした経験の有無は今後のキャリアにおいて大きな意味を持ちます。いち早くそうした可能性に賭け、今いる場所で、あるいは新天地でそうした経験を取りに行ってください。市場で求められるマネジメント人材になるために、一歩踏み出してみませんか?