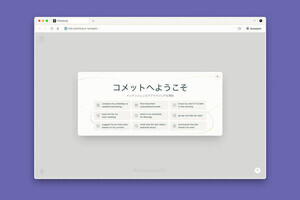「SDGs」や「環境問題」という言葉を耳にすることが多くなった現代。個人での取り組みもさることながら、企業や自治体をあげての持続可能な社会の実現に向けた取り組みも重要視されている。
本稿では、企業の取り組みの例として、サーキュラーエコノミー(循環型経済)の仕組みを取り入れたサステナブルな大会運営を実現するべく、「サーキュラリティ評価」を導入した「楽天・ジャパン・オープン・テニス・チャンピオンシップ2022」(楽天オープン2022)から、楽天の見据える「持続可能な社会」について紹介する。
楽天グループのグループパートナーシップ戦略部スポーツ&エンターテイメントパートナーシップ戦略課でマネージャーを務める新保和洋氏、同じくマネージャーの村上和貴氏、佐脇風里氏、レコテックのサーキュラリティデザイナーである大村拓輝氏の4名に話を聞いた。
-

左から、レコテック サーキュラリティデザイナー 大村拓輝氏、楽天グループ グループパートナーシップ戦略部スポーツ&エンターテイメントパートナーシップ戦略課 マネージャー 新保和洋氏、同 佐脇風里氏、同 マネージャー 村上和貴氏
3つの指標により、サーキュラリティ評価を算出
「楽天オープン2022」は、日本テニス協会が2022年10月に有明コロシアムおよび有明テニスの森公園コートで開催した大規模なテニスの国際大会だ。新型コロナウイルスの影響もあり、2022年度大会は3年ぶりの実施となった。
そんな楽天オープン2022に導入された「サーキュラリティ評価」とは、WBCSD(持続可能な開発のための世界経済人会議)および30のグローバル企業より策定された、企業の取り組みの「サーキュラリティ」(循環性)を測定・自己評価するフレームワークのことを指している。
この評価では、「マテリアル・サーキュラリティ率」や「CO2削減効果」などを数字で可視化できるほか、どのようなモノがどのような形でリサイクル・リユースされているかも測定することが可能となっている。 今回の大会内では、「ごみの廃棄量を削減し、CO2の排出量を減らす、廃棄物の再資源化」「プラスチックごみから再生された弁当袋の活用」「マテリアルフロー分析の導入」という3つの取り組みを行うことでサステナブルな大会を実現し、その指標としてサーキュラリティ評価が算出された。
「具体的な取り組みとしては、ごみ分別BOXである『ECO STATION by Rakuten』を会場内に設置し、イベントから発生する廃棄物を可燃・ペットボトル・ペットボトルキャップ・生ごみ・お弁当袋という5種類に分別し、可能な限り品目ごとのリサイクルループを構築して再資源化し、焼却処理量を削減することで、CO2排出量を減らす取り組みを行いました」(新保氏)
この分別によって、ペットボトルは、再びペットボトルへ生まれ変わり、ペットボトルキャップは再生樹脂としてテニス関連用品へ生まれ変わるほか、生ごみはメタン発酵施設へ運ばれ、電気と有機肥料にリサイクルされた。
また、キッチンカーで使用される弁当袋を都内商業施設や店舗から発生したプラスチックごみから再生されたPCR材(ポストコンシューマーリサイクル材)である「POOL樹脂」を活用してつくられたものを使用したり、レコテックから提供を受ける「POOLシステム」の導入により、大会期間中に廃棄される資源情報の一元管理を行ったりといった取り組みや循環がサーキュラリティ評価で可視化されているのだ。
「弊社(レコテック)調べによると、大規模なスポーツ大会において、サーキュラリティを評価した取り組みは国内では前例がありません。それどころか、世界全体を見ても最先端の取り組みです。その点において、楽天オープン2022におけるサーキュラリティ評価は、企業としての実績のみならず、日本という国全体にとっても大きな成果であったと考えています」(大村氏)
「楽天オープン2022」のサーキュラリティ評価の結果は?
上記のような取り組みを行い、サーキュラリティ評価を計測した「楽天オープン2022」だが、実際の結果はどのようになったのだろうか?
「マテリアル・サーキュラリティ率が48%で、その内のサーキュラーインフロー率は36%、サーキュラーアウトフロー率は60%という結果になりました。また、サーキュラーな取り組みによるCO2削減効果は、35,709 kg-CO2となりました」(大村氏)
サーキュラーインフロー率とは、天然資源を採掘した資源ではなく持続可能な方法で栽培、採取されたバイオマス資源や、新品ではなくリユース品やリサイクル素材で調達された資源といった、持続可能な資源をどれくらい使用して運営することができたかを示す指標。
一方で、サーキュラーアウトフロー率とは、発生した廃棄物をどれだけ回収し、リサイクルやリユースすることができたのかを示す指標となっている。そして、これらの各要素を考慮したものが「マテリアル・サーキュラリティ率」として表されている。
つまり、大会に使用された全体の資源の内サステナブルな資源は36%で、またその使用された全体の資源の内60%はリサイクルまたはリユースされたということになる。
また、大会で実施した取り組みにより、それらを行わなかった場合の想定と比較し、35,709 kg のCO2削減につながったことも測定の結果から分かっている。これは、テニスコート約156面分の森林が1年間に吸収するCO2量と同等の数値となるという。(森林1m2あたり年間0.88kgのCO2を吸収する前提で、ダブルスコート(約261m2)に換算して算出)
「この数字だけ聞くと多いと感じる方も少ないと感じる方もいるでしょう。しかし、今回の大会において結果は最重要項目ではありませんでした。しっかりとデータを取って、どのくらい環境に貢献できているのかを可視化できることを証明することで、今後の導入ハードルを下げるということが一番の目標でした」(村上氏)
サーキュラリティ評価を導入して見えてきた課題も多くあるそうで、今後はそれらの課題を解決する運用方法を模索しながら、さまざまなイベントでの導入を進めていきたい考えだという。
「課題として、特に浮き彫りになったのは『長期期間のイベントの運用方法』です。イベントスタッフはアルバイトの方にお願いすることがほとんどで、今回のように長期期間のイベントの場合、毎日同じスタッフがそろうことはありません。その際に新しいスタッフに毎回最初から計測方法をレクチャーする必要があることや、スタッフの意識の差で計測に微差が生まれてしまうことなど、新たな課題が発見できたので、今後の運用の仕組みを考え直すきっかけにもなりました」(大村氏)
25周年を迎えた楽天が考える「持続可能な未来」
「今回の楽天オープンのテーマは『スポーツの未来を共に創ろう』というものでした。これからのスポーツの未来を考えた時、アスリートとの活動を通じて環境問題を解決していくことが間違いなく必要だと確信していました」(村上氏)
また、国内初のサーキュラリティ評価という前例のないものを導入するにあたって、会社のサステナブルな取り組みへの考え方も後押ししてくれたという。
「弊社は2022年で25周年を迎えました。そしてその節目の年に改めて未来のことを考えるという意味でもSDGsやカーボンニュートラル実現のために、取り組みを強化する方針を4月に打ち出しました。それが『Go Green Together』という取り組みです」(新保氏)
「Go Green Together」は、楽天の考える持続可能な未来の形である「世界中の人々が夢を持って幸せに生きられる社会が何世代にもわたって続いていく明るい未来」を実現するために、楽天グループ内のさまざまな事業を横断する形で行われているプロジェクトだ。
この取り組みの中では、今回の楽天オープン2022のようなスポーツを通じた取り組みをはじめ、サステナブルな洋服を楽天ファッションでピックアップしたり、楽天トラベルを通じて旅行先でできるサステナブルな取り組みを紹介したりと、幅広いジャンルでのサステナブルな取り組みを推進している。
実際に、楽天オープン2022内でもサーキュラリティ評価に加えて、さまざまなサステナブルな取り組みが行われていた。
「楽天オープン2022では、『FOREST of WISH by Rakuten』というコンテンツも実施しました。このコンテンツは、大会出場者への応援や次の世代への想いなど、観客の皆さんから寄せられたメッセージがオンライン上や会場のプロジェクター上で木や動物たちへ生まれ変わるというものです。参加してくださる方々に今一度『未来』を考えてみてほしいという想いから始まった企画で、世界平和や環境問題の解決を願うコメントがたくさん寄せられました」(佐脇氏)
最後に今後の展望を新保氏に聞いた。
「一人ひとりが自分らしく活躍できるスポーツの環境を作っていきたいです。そのためには私たちだけでなく、選手や観客の皆様と共に未来を創っていくという意識をもう1度持ち直して、今後のイベントにつなげていきたいです。またサーキュラリティ評価を広めていくことも我々のミッションだと思っています。今回、前例ができたことで導入のハードルが少し下がったと思うので、今後もサーキュラリティ評価を多くの企業やイベントで使用してもらえるような事例を生み出していきたいです」(新保氏)