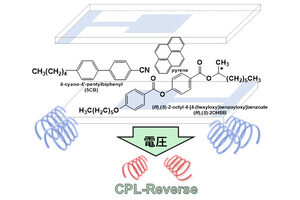これからの未来に向けて、ただのポーズ取りではなく、人類が本気で取り組まなければならないSDGs(持続可能な開発目標)。本連載では、国内における起業家やスタートアップを中心にビジネスの話に加え、今後の企業における事業展開にも重要性が帯びてくるSDGsに関する考え方を紹介します。→「SDGsビジネスに挑む起業家たち」の過去回はこちらを参照。
発芽大豆由来の植物肉「ミラクルミート」を開発・製造するDAIZ
牛・豚・鶏に次ぐ新しい肉のカテゴリ、次世代の食品として期待される植物肉(プラントベースミート)。食糧危機や地球温暖化など、世界規模の問題に対するアプローチ手段の1つとして注目され、各国で成長が著しい市場である。
国内でも植物肉開発・生産に取り組む企業は数あれど、今トップを独走しているのは熊本発のフードテックベンチャー、DAIZではないだろうか。
佐賀大学が開発に成功した高オレイン酸大豆を使い、これまでにない発芽大豆由来の植物肉「ミラクルミート」を開発・製造する同社は、植物性由来原料のパイオニア的企業として知られる、フランスのRoquetteと2023年1月、資本業務提携を締結したことも話題を集めた。
2021年5月には米ボストンに子会社としてDAIZ USAを設立、2022年4月にはタイにミラクルミートを輸出し、現地企業が商品化・販売開始するなど、海外進出を積極的に進めるDAIZ。Roquetteとの協業で、共同研究やミラクルミートの海外生産、植物性食品の海外供給を視野に入れ、国内のみならず世界規模でミラクルミートを普及させることを目指している。
「日本の国産大豆を使って美味しい食品を作り、国内はもちろん海外にも輸出し、世界各地で食べられるようにするのが私のミッションの1つ。現在、日本の企業は安価な輸入大豆を原料に大豆製品を作っていて、大豆の国内自給率は1桁に過ぎず、国内の大豆農家さんは苦しい状況です。ですが、日本の農業を元気にすることで土や水などの自然が守られ、環境が良くなり、ひいては人も健康になっていく。私たちの活動の根っこにあるのは国内農業への貢献です」
こう話すのは、DAIZを率いる代表取締役の井出剛さん。福岡生まれだが、熊本県水俣市と深い縁を持つ。水俣市といえば「公害の原点」と言われる水俣病が発生し、1,900人を超える人が亡くなった街だ。
井出さんは水俣病の研究者で、熊本県に医薬品の安全性研究所を設立した父の元で働いていた。その原体験がDAIZの事業にかける想いと結びつく。井出さんにDAIZの成り立ちから今、未来に至るまでのお話を伺った。
「落合式大豆」との衝撃の出会い
DAIZのコア技術である、独自の発芽手法「落合式ハイプレッシャー法(以下、落合式)」を考案したのは取締役・CTOの落合孝次さんだ。井出さんが落合さんと出会ったのは2013年のこと。
当時、井出さんはトヨタ自動車、カゴメ、三井物産の出資を受けて日本最大の有機栽培ベビーリーフ会社の果実堂を経営していたが、落合さんの発芽の知見を必要としていたため、滋賀県にあった研究所(落合さんが経営していたバイオベンチャーが入居)へ赴いたという。
そこでは大豆を13時間以内に発芽させ、同時に、酸素や二酸化炭素、温度、水分などの生育条件に対して独自のストレスを与えると、大豆の代謝が活性化し、うまみや栄養価、機能性が急激に高くなるといった研究が行われており、井出さんは驚愕した。
「この技術はもっと陽の目を見るべきだ」。そう考えた井出さんは落合さんを熊本に呼び寄せて果実堂内で新たに立ち上げた植物肉事業「発芽促進研究所」の所長として迎え入れる。研究所が本格始動し始めたのは2015年、果実堂から分社化してDAIZ(旧名:大豆エナジー)が誕生してからのことだった。
はじめのうちは、落合式で作る豆がとても美味しかったことから、サラダ用大豆としてコストコに販売(現在も継続販売中)しつつ、豆腐や豆乳などの製造を模索するが、この特殊技術を生かしきれない時期が3年ほど続いた。そんな中、2017年、落合さんが重篤ながんにかかっていることが発覚。ステージ4の重い状況だったが、1年休んで2018年に復職し、止まっていた大豆プロジェクトが再始動することになる。
世界の植物肉市場を変える、日本発の原材料メーカーに
大きな転機となったのは2019年、1960年代から植物肉を開発する不二製油グループ本社 代表取締役社長(2019年当時)の清水洋史さんが、京都大学の教授や自社の研究員を連れてDAIZを訪れたことだった。不二製油は日本において、パイオニア的に植物肉原材料の研究開発をしていた。
清水さんは井出さんに、欧米ではプラントベースフードが注目されるようになり、植物を原料とした肉が作られ始めていること、落合式発芽大豆は優良な原料になることなどを力説したという。
「日本人は昔から豆腐や味噌、醤油、納豆などの大豆製品と親しんできて、大豆という植物性たんぱく質を積極的にとりながら人口を増やしてきた国で、国内には大豆の研究者も大勢いる。アフリカ・アジアの人口増加や鳥インフルエンザ、豚コレラなどの流行やそれに伴う食糧危機が叫ばれる今、大豆を使って作る植物肉の需要は高まる、とも清水社長は話していました」(井出さん)
その後、井出さんは落合さんや社員とともに渡米。研究所や植物肉ベンチャー企業を訪問し、現場の実態に触れる。彼らが10年先を見越して研究開発を進めていることに大きな衝撃を受けたが、重要な気づきもあった。
現地で買い込んださまざまな植物肉の袋に記載された成分表の精査を進めると、そのすべてに使われていたのは脱脂大豆だったのだ。脱脂大豆の栄養価は高くはなく、味もいいとはいえないので調味料や添加物の力で美味しいように味付けされている。
「それに対し、私たちが原材料メーカーとなって、自分たちが作っている栄養価の高い大豆を欧米企業に提案すれば、彼らはより美味しい植物肉を作ることができます。世界の植物肉市場で原材料として我々の技術が貢献できるんじゃないかと、帰りの飛行機で落合と熱く語ったのを覚えています」(井出さん)
スタートアップだからこそ、業界のガリバーらと組む
帰国後の2020年1月から本格始動し、同月に冷凍食品大手のニチレイフーズと資本業務提携を締結。さらに同12月には味の素と資本業務提携を締結し、その前後にも多くの大企業から出資を受けたり、資本業務提携を行ったりしている。
丸紅、日清食品、丸井グループ、三菱ケミカルホールディングス、日清製粉グループ など、さまざまな業界の錚々たる顔ぶれが名を連ねているのが特徴だ。累計調達額は95億8,000万円にのぼる(2022年11月時点)。
特に食品業界のガリバー的存在と言っても過言ではない味の素と初期の段階から技術提携したことは、DAIZの技術が日本を代表する企業に高く評価されていることを世間に示した。その後も資本業務提携や出資のニュースが相次いでいる。
「このように多くの企業とコラボしてできたミラクルミートを売れば、提携先企業も潤っていきます。われわれはまだ人・物・金が乏しいスタートアップの段階ですから、それぞれ技術や強みを持つさまざまな企業と組みながら、自分たちにはない技術を補完し、落合式発芽大豆の魅力を高めていくことをひたすら戦略的に考えてきました」(井出さん)
2025年には熊本県益城町テクノリサーチパーク内に構えるDAIZの発芽・植物肉工場の近隣に、新工場の建設が予定されている。現工場では最大年間4,000トンのミラクルミートを製造できるが、新工場では同2万トンの生産能力を有し、国内外各社からの需要に応える体制を構築する。
世界の植物肉の4分の1でミラクルミートが使われる未来
冒頭のRoquetteを含め欧米企業とも協業しているが、今後は中国や東南アジア各国への進出強化も視野に入れているDAIZ。2022年4月からはタイのバンコクに本社を置く植物肉企業であるLottoFOODへミラクルミートを提供開始している。
今、アジアでは人口増や豚コレラ・鳥インフルエンザの流行に関わる肉不足、価格高騰などを背景に「植物肉を肉に混ぜて使いたい」とのニーズが生まれているという。
井出さん自身もミラクルミートを肉と混ぜて使うことを推奨している。2022年12月、国内で一般消費者向けに自社製品として販売開始した、ミラクルミートを原料とする大豆ミート「粒ベジ」でもそれを伝えている。
最後に、SDGsの期限となる2030年、井出さんがどんな未来を描いているか尋ねると、「2030年には世界中で植物肉が食べられているはずで、世界の植物肉市場の原材料の25%にミラクルミート、ひいては日本の国産大豆が使われている状況を目指している」と返ってきた。
「大豆という栄養価抜群な原料で、国内はもちろん、世界のたんぱく質不足解消に貢献したいです。前出のアジアもですが、アフリカでも人口爆発が続いていきます。欧米の子どもは成長期に栄養の高いものを食べられて、かたやアフリカの子どもは食べられなくて辛い思いをする……。そんなアンフェアな状況を変えるのにDAIZが役に立てればと思っています」(井出さん)
昨今、連日のように報道される、たんぱく質不足に関わるニュース。にわかに盛り上がり始めた「コオロギ」などの昆虫食もその1つだが、日本には大豆という良質な植物性たんぱく質が存在するのである。
「日本の農業を応援したい」「それにより環境を良くし、人の健康にも貢献したい」。井出さんの想いの基盤はそこにあり、落合式発芽大豆から作られるミラクルミートが普及する未来、国内農業も環境も人もより良い状態になっていると強く期待したい。