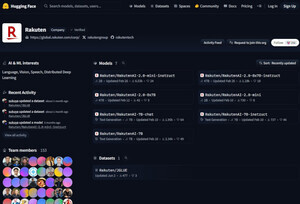昨年、米空母「ジョージ・ワシントン」(CVN-73)が、二度目の前方展開のために横須賀にやってきた。フネ自体は以前に横須賀に前方展開していたものと同じだが、その中身は同じではない。→連載「軍事とIT」のこれまでの回はこちらを参照。
-

たまたま先日、横須賀で撮影した「ジョージ・ワシントン」。この写真だと分かりにくいが、RIM-116 RAM (Rolling Airframe Missile)艦対空ミサイル用と思われるレーダーを3基、増設していた件が話題になった 撮影:井上孝司
RCOHのついでにいろいろやる
日本への2度目の前方展開より前に、ジョージ・ワシントンはヴァージニア州ニューポート・ニューズのハンティントン・インガルス社ニューポート・ニューズ造船所でRCOH(Refueling Complex Overhaul。直訳して、炉心交換・包括修理といわれる)を実施していた。
ニミッツ級空母は原子力空母であるから、動力の源となる原子炉を搭載している。その数は2基。その原子炉に組み込まれている燃料集合体を交換するのが、いわゆる炉芯交換の中核となる作業。
ただ、そんな大仕事をすることになれば、年単位の時間がかかる。その間、艦はドックに入ったままで動けないのだから、ついでにその他の部分も整備・補修を行ったり、搭載機器を新しいものに取り換えたり、という話になるのは当然の展開。「包括修理」(Complex Overhaul)の語がセットになるのは、そういう事情による。
だから、同じ艦でもRCOHを実施する前と後では艦容が違ってくることがよくある。ジョージ・ワシントンでも、レーダーの陣容はほとんど変わっていないようだが、アイランド(島型艦橋)の周囲を見ると、アンテナ類の配置が変わっていたり、以前にはあったアンテナが消えたりしている。
それは外から見える変化だが、内部もいろいろ手が入るのが恒例。例えば、艦内で使われているさまざまな情報システムを動かすためのコンピュータ機器やネットワーク。こういったものは陳腐化が速いから、新しいものに取り換えていかなければならない。
戦闘システムをごっそり更新する事例
「つかみ」の話題として、大物の米空母を使ったが、他の艦でも事情は似ている。例えば、海上自衛隊の「あたご」型ミサイル護衛艦。
外見こそ就役当時から大きく変わっていないものの、ミサイル防衛機能の追加に併せて、イージス戦闘システムをベースライン7からベースライン9に更新する大手術を受けた。そうなると、艦内に設置していたイージス・システム関連のコンピュータ機器は総取り換えである。
目立つ外観上の変化は、国産の対水上レーダーが降ろされて、代わりにアメリカ製のAN/SPQ-9Bが載ったことぐらい。しかし、中身も戦闘能力も別物といっていい変化をしている。
→第479回で取り上げたことがある、オーストラリア海軍のANZAC級フリゲートでは、ASMD(Anti-Ship Missile Defence)改修に際して国産のフェーズド・アレイ・レーダーを載せる大手術を実施した。だから艦容が一変した。それは見た目の話だが、中身の指揮管制システムにも当然ながら手が入っており、戦闘能力を高めている。
こんな調子だから、実は同じ艦を「定点観測」し続けることには重要な意味がある。おそらく業界関係者は、みんなやっていることだ。たぶん、日米の艦に対して中露の人間はそれをやっているし、逆もまた同様であろう。
外見に現れる変化もあれば、外見に現れない変化もあるが、なんにしても「竣工したときのままで一生を終える艦」は、そうそうない。機会を捉えては「何か変化した点はないか」と鵜の目鷹の目になるのは、相手の艦の能力を推し量る上で不可欠の作業となる。
同じクラスなのに違いがある!?
取り扱いや形態管理、教育訓練などの見地からすれば、同じクラスの艦は同じ構造、同じ配置、同じシステムになっていることが望ましい。そうすれば、別の同型艦に乗組員が転勤した場合でも、まごつくことなく、すぐに仕事ができる。
ところが、必ずしもそうならないことがあるのが艦艇の面白いところ。同型艦でもフネごとに、外見や搭載兵装が違っていることがある。甚だしきはミッドウェイ級空母みたいに、3隻すべて形態がバラバラ、飛行甲板の平面型までバラバラ、なんていう事例もあった。
そこまで極端でなくても、もっと細かい差異が生じることもある。例えば、米海軍のフォレスタル級空母は4隻あったが、最終形態で並べてみると、それぞれ電測兵装の配置が違っていた。搭載するレーダーの機種が同じでも、載っている場所が違うのである。
野次馬からすれば、相違点を知っておくことで、艦番号を見なくても個艦の識別ができるのでありがたい(何が?)。しかし、アンテナ類の配置が違えば電波干渉の影響も違ってくるはずで、それをいちいち計算して配置を決めるのは、なんとも手間のかかる話。同じ図面で同じように搭載する方が合理的であるはずなのだが。
ただ、改造する時期のずれや施工する造船所、あるいは工廠の違いなどといった要因から、改造工事の内容に際が生じる場面があるのは、致し方ない一面もある。今は電測兵装の話だけしているが、昔は「同型艦だけど機関が違う(ただし馬力だけは同じぐらいに揃える)」なんてことまであったのだ。
ちなみにジョージ・ワシントンは、RCOHの際にマストまで外して取り替えている。丸型断面のマストを角型断面に変えて、レーダー電波の反射方向を限定しようとしたようだ。マストの断面形状が変化すれば、マストの周囲に取り付けられたレーダーの動作に影響が出ても不思議はない。それも考慮に入れた設計が必要になりそうなものだ。
著者プロフィール
井上孝司
鉄道・航空といった各種交通機関や軍事分野で、技術分野を中心とする著述活動を展開中のテクニカルライター。
マイクロソフト株式会社を経て1999年春に独立。『戦うコンピュータ(V)3』(潮書房光人社)のように情報通信技術を切口にする展開に加えて、さまざまな分野の記事を手掛ける。マイナビニュースに加えて『軍事研究』『丸』『Jwings』『航空ファン』『世界の艦船』『新幹線EX』などにも寄稿している。このほど、本連載「軍事とIT」の単行本第5弾『軍用センサー EO/IRセンサーとソナー (わかりやすい防衛テクノロジー) 』が刊行された。