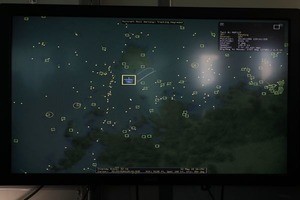これまで、System of Systems(システムの集合体)という見地から、無人機システム(UAS : Unmanned Aircraft System)にまつわる話題をいろいろ取り上げてきた。ちなみに、無人機単体だとUAV(Unmanned Aerial Vehicle)、無人機と管制システムなどを組み合わせた一式だとUASという言葉を使うのが一般的なように見受けられるが、実のところ、この辺の使い分けは曖昧である。
無人機と他のシステムの組み合わせ
閑話休題。
実は近年、UAVを単独で使うのではなく、他のウェポン・システムと組み合わせる事例が出てきている。その先陣を切っているのが、AH-64Eアパッチ・ガーディアン攻撃ヘリにおけるMUM-T(Manned and Unmanned Teaming)といえよう。
MUM-Tを逐語訳すると、「有人機と無人機のチーム化」となる。
もともと、AH-64みたいな攻撃ヘリコプターは、自前でセンサーも武器も持っていて、単独で捜索・発見・交戦の流れをこなせるようになっている。
ところが、携帯式地対空ミサイルや小型・短射程の地対空ミサイルが普及して、攻撃ヘリコプターが敵軍を射程内に収められるところまで接近するのが難しくなってきた。
従来であれば、被発見を避ける、あるいは遅らせるために、地形、森林、建物などといった障害物の影に隠れて接近するのが基本的なスタイルだったが、もはやそれだけでは身を守ることができないという考えが出てきている。
そこで、捜索・発見の部分はUAVにやらせて、発見した敵と交戦する部分を攻撃ヘリが受け持つ、という役割分担が考え出された。もちろん、それを実現するにはいくつかの前提条件がある。
まず、攻撃ヘリコプターの搭乗員が、UAV自体、それとUAVが搭載するセンサーを遠隔操作できること。UAVを地上管制ステーション(GCS : Ground Control Station)についたオペレーターが操作していて、そのオペレーターと攻撃ヘリコプターの搭乗員がいちいち無線で交信するのでは、迂遠に過ぎるからだ。
次に、攻撃ヘリコプターが長射程かつ撃ち放しが可能な兵装を備えていること。できれば、敵の地対空ミサイルの射程範囲内に入らず、しかも撃ったら直ちに回避行動に移れるように、ということである。
ミサイルが自ら敵を捕捉・交戦できるアクティブ・レーダー誘導なら万全だが、次善の策としてセミアクティブ・レーザー誘導でも良い。これはレーザー目標指示器で目標にレーザーを照射して、その反射波をたどる方式である。
通常なら攻撃ヘリコプターが自らレーザー照射を行うし、それはAH-64も同じだ。しかしそれでは、撃ったら命中するまでレーザー照射を続けなければならないので、撃ち放しにならない。だから、別の誰かさんがレーザー照射を引き受ける必要がある。それをUAVにやらせれば、攻撃ヘリコプターは後方の安全な場所に引っ込んでいられる。
MUM-T化した交戦の一例
つまり、こういう交戦の流れになる。
まず、攻撃ヘリの搭乗員がUAVの電子光学/赤外線センサーで得た映像を見ながら、敵軍を捜索・捕捉する。
そして、発見した敵軍の中から目標を選び出す。続いて、その目標に対してレーザー照射を行った上で、自機が搭載する対戦車ミサイルを発射する。撃ったミサイルは、UAVが出しているレーザーの反射波を捕捉して、それに乗って誘導される。
こうすれば、攻撃ヘリコプターはミサイルを発射した後、直ちに離脱したり、別の目標との交戦に移ったりできる。もしUAVが撃ち落とされても、人命の損耗にはつながらない。
ただ、これだけの仕組みを一挙に実現するのは時間も費用もかかる上に、開発リスクもある。そこでMUM-Tを実現するに際しては複数のレベルを設定して、段階的に開発と実装を進める形が取られている。
AH-64Eで最初に実装したのがMUM-Tのうちレベル2で、UAVのセンサーが捕捉したデータを(GCSを介さずに)AH-64Eが直接受信できるようにした。これで、UAVはAH-64Eの「外部の眼」として機能できるが、UAVやUAVのセンサーを操作する部分は他人任せである。
続いて実装したのがレベル4で、データを受け取るだけでなく、UAVやUAVが搭載するセンサーを、AH-64Eの搭乗員が直接、操作できるようにした。
レベル2だと、UAVを敵軍に近いところに置いた「眼」として使うことはできるが、「槍」にはならない。レベル4になると初めて、「槍」として使えるようになる。正確にいうと、攻撃ヘリコプターが槍(ミサイルなど)を放つための誘導手段だが。
つまり、UASというSystem of Systemsが攻撃ヘリコプターというSystem of Systemsと組み合わされていることになる。だからといって、屋上にさらなる屋を架すようにSystem of Systems of Systemsとはいわないが。
攻撃ヘリコプターが、それ自身の能力向上や性能向上によって生存性と打撃力の改善を図る代わりに、UAVと組み合わせることで目的を達成しようとしているわけだ。ただし実現に際しては、システム開発や試験にかかる負担が大きくなる泣き所がある。
著者プロフィール
井上孝司
鉄道・航空といった各種交通機関や軍事分野で、技術分野を中心とする著述活動を展開中のテクニカルライター。
マイクロソフト株式会社を経て1999年春に独立。『戦うコンピュータ(V)3』(潮書房光人社)のように情報通信技術を切口にする展開に加えて、さまざまな分野の記事を手掛ける。マイナビニュースに加えて『軍事研究』『丸』『Jwings』『航空ファン』『世界の艦船』『新幹線EX』などにも寄稿している。