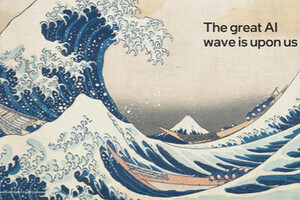4年間で900億ドルを投じて目指した技術キャッチアップ
Intel Foundry Direct Connectにおいて、先端プロセスの状況については、Intel EVP兼Intel Foundry CTO/COO/GMのナガ・チャンドラシーカラン氏が説明を行った。
同氏は、まずIntelの「5 Nodes in 4Years(5N4Y:2021年から2024年にかけての4年間にIntel 7(いわゆる7nm)からIntel 18A(いわゆる1.8nm=18Å)に至る5世代の先端ロジック開発・製造を一気に行う計画)」の実現に総額で900億ドルを投資してきたことを説明。その内訳としては、350億ドルを土地代と工場建設費、370億ドルを半導体製造装置代、180億ドルをプロセスノードや先端パッケージング技術などの開発に投じたとし、この4年間で着実に技術開発が進んだことを強調。「2025年末に生産に入るIntel 18Aは、この取り組みの最後のノード(プロセス)で、Intel Foundryが本格的に受託生産ビジネスを展開する上で重要なプロセスノードである」と述べた。
この5N4Yというプロジェクトは、ロジックプロセスの微細化で後れを取ったIntelが、4年かけてライバルのTSMCやSamsung Electronicsに追いつくためのプロセス微細化促進計画で、当初の計画では、最終ゴールのIntel 18Aについては2024年後半の生産開始としていたことを鑑みれば、1年遅れでの実現となる見通しである。それにしても1つのプロジェクトに900億ドルもの資金を投資したとは、いかにIntelという企業が巨大であると言っても、とてつもない額であると言えるだろう。
Intel 18Aは2025年第4四半期より量産を開始
同イベントで示されたロジックプロセスのロードマップの最新版を見ると、5N4Yの最後に据えられた「Intel 18A」は、同社初となるRibbonFET(一般にはGAAナノシートFETとして知られる構造)と世界初採用となる裏面電源供給技術「PowerVia(一般にはBackside Power Deliveryと呼ばれる技術)」を採用した、Intel Foundryにとっての顧客に提供される本格的な最初のプロセスノードであり、ファウンドリ事業の成否をかけた重要なノードという位置づけとなっている。
すでにオレゴン工場にてリスク生産が進められており、目標にしている性能の90~95%を実現、2025年後半には目標に達する見通しだという。また、300mmウェハ上の欠陥密度も着実に減少が進んでおり、製造歩留まりも上昇傾向にあり、2025年第4四半期末までに量産開始が予定されている。加えて、Intel Foundryのエコシステム・パートナーもEDA、リファレンス・フロー、IPなどのの量産向け設計をすでに開始しているとする。
Intel 18Aは、Intel 3(いわゆる3nmプロセス)に比べて、単位電力あたり性能が15%向上し、チップ密度が3割増加するという。すでにIntelの次世代SoC「Panther Lake(開発コード名)」に適用されることがすでに決まっており、Intelの製品部門にとっても重要なプロセスノードではあるが、2025年内の出荷はごく一部に限られ、本格的な出荷は2026年に入ってからという声も業界の一部からは聞こえている。果たして、実際にどうなるのかについては、実物が出てくる、もしくは搭載したPCがいつ、どれくらい登場するかでわかるだろう。
Intel 18Aには2種類の派生プロセスが計画
このIntel 18Aについては、派生プロセスとして「Intel 18A-P」が計画されている。これは顧客層の多くを対象に、パフォーマンス向上(Intel 18Aに比して8%向上、チップ密度は変化なし)を目的に設計されたもので、現在、初期段階のウェハのリスク製造が始まっているという。Intel 18A-PはIntel 18Aとの設計ルールの互換性確保が予定されており、IP/EDAパートナーはこの派生プロセス用に製品のアップデートを開始している。量産は2026年からの見込みとする。
また、今回新たに「Intel 18A-PT」の存在も明らかにされた。Intel 18A-Pの性能と電力効率の進化を基盤としたさらなる派生プロセスで、TSVを追加したものとなる。同じTSVの仕組みを採用しているIntel 3Tと比べると性能は20~25%向上し、チップ密度は25~35%増加するという。
さらに、5μm未満のハイブリッド・ボンディング・インターコネクトピッチを備えたFoveros Direct 3Dを使用してトップダイに接続できる仕様で、Die-to-Dieの帯域幅密度はIntel 3T比で9倍となるなど、TSVの機能を活用することで、ほかのダイとより広帯域で通信することができるようになるため、AIチップをチップレットで構築する時に最適なプロセスノードになるという。量産は2028年を予定しているとする。
高NA EUVを用いて試作が進むIntel 14A、2027年にリスク生産を予定
Intel 18Aの後継となる「Intel 14A」だが、高NA EUVリソグラフィを適用する形で開発・試作が進められている。Inel 18Aに比べて性能は15~20%向上し、チップ密度は3割増加するという。
すでに主要顧客と連携を開始しており、Intel 14AのProcess Design Kit(PDK)の初期バージョンの提供が行われ、複数の顧客企業がIntel 14Aのテスト用チップを構築する意向を表明しているという。ちなみにIntel 14Aでは、Intel 18Aのバックサイド給電テクノロジー「PowerVia」に基づいて構築された、直接接触型の給電テクノロジー「PowerDirect」の採用が予定されている。2027年よりリスク生産が開始される予定である。
Intel18A/14Aは研究開発から前工程・後工程まで米国内で完結
Intelアリゾナ工場内に新設された最新鋭工場「Fab 52」では、全製造工程の調整を無事に終え、初ロットのウエハ処理が完了したところだとのことで、米国で最先端プロセスとなるIntel 18Aのウェハ製造体制の年内確立に向けて順調に進捗していることが語られた。
Intel 18Aの少量生産はIntelのオレゴン工場で進められているが、2025年第4四半期よりアリゾナ工場にて量産が開始される予定である。
なお、Intel 18AとIntel 14Aは研究開発からウェハ製造(前工程)、アセンブリ(後工程)まですべて米国国内だけで完結された半導体であるため、トランプ政権による半導体関税の影響は受けないだけではなく、トランプ政権の「半導体製造の米国回帰戦略」に沿っていることをIntel経営陣は強調していた。
(次回に続く)