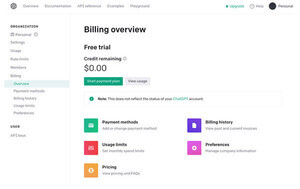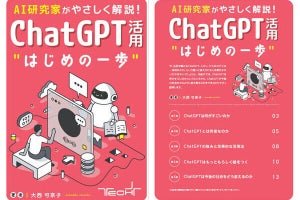前回はChatGPTの弱点について解説しました。簡単にまとめると、ChatGPTの弱点は次の5つです。
- ChatGPTはもっともらしく嘘をつくことがある
- 最新の情報には対応していない
- 同じ入力に対して違う答えを返してくる
- 入力した内容が学習に使われる可能性があるのでセキュリティに注意が必要
- ChatGPTの回答をそのまま成果物として扱う場合は著作権に留意する必要がある
これらの課題があることを踏まえても、ChatGPTが強力なAIソリューションであることに変わりはありません。ChatGPTは、世の中を変え得る可能性を秘めた存在であると私は思っています。
ChatGPTについて学ぶ本連載、最終回となる今回は、ChatGPTによって今後の世の中がどう変わっていくのかについて解説します。
本連載を1冊にまとめました!
【限定eBook】AI研究家がやさしく解説! ChatGPT活用“はじめの一歩”
>> ダウンロードはこちら
ChatGPTとは「副操縦士」である
まず、本連載の目的の1つでもあった「ChatGPTとは何者なのか」について、一言で回答しましょう。
「ChatGPTは副操縦士です」
――私はこの言葉がChatGPTの全てを言い表しているように思います。
そう、ChatGPTは飛行機で例えれば副操縦士なのです。では、操縦士、つまりパイロットは誰なのか。
それはもちろん、あなたです。
いくら副操縦士が優秀だとしても、飛行機の目的地を決めたり、実際に操縦したりするのは、操縦士の仕事です。副操縦士は、操縦士の隣にいて、双方向にコミュニケーションしながら操縦のサポートを行います。
ChatGPTも同じです。どれだけChatGPTが優秀でも、最終的に物事を動かすのは人の役割です。前回述べたように、ChatGPTは生成結果の正誤判定などはできません。だからこそ、ChatGPTの成果物を手放しで信用してそのまま使用すべきではないというわけです。
一方で、サポート役として考えると、これほど心強い味方はいません。これまでもAIは人間のサポート役として開発されていましたが、従来のAIはChatGPTのような双方向のコミュニケーションはできませんでした。
例えば、自社のサービスに関するアンケート調査を行ったとします。その内容をポジティブなものとネガティブなものに分類することは、従来のAIでも可能でした。しかし、従来のAIの仕事はそれだけで、結果を受け取ったらあとは人間が1人で考えるしかありませんでした。これは、従来のAIが「タスク型」だったからです。
ではChatGPTはどうか。アンケートのポジティブ/ネガティブ判定を行って結果を出すところまでは同じですが、その結果を見て人間が「なぜそう判定したのか」を問えば、ChatGPTは理由を返してくれるのです。これが、「コミュニケーション型」のAIであるChatGPTの大きなメリットです。
人は双方向で対話することで思考が深まっていく生き物です。人類が今日まで発展できたのは、太古の昔に言語を生み出し、コミュニケーションを通じて思考してきたからなのです。
ChatGPTにより仕事のスキル差は縮まっていく
では、ChatGPTというパートナーを得たことで社会はどう変わるでしょうか。
まず、仕事という面で言うと、今後スキルの個人差は大幅に埋まっていくでしょう。なぜなら、これまでスキルを必要としていた作業が、ChatGPTにより代行できるからです。
例えば、プログラムのコードを書く場合、これまではプログラミングの勉強が必要でした。Webを検索すればコードのひな型も見つかりますが、それは自分用にパーソナライズされたものではないので、どのようにアレンジすれば望む挙動が得られるのかについては結局のところ学ぶ必要があります。
しかし、ChatGPTであれば「最終的にどんなことがやりたいのか」を伝えるだけで、そうした学びをすっ飛ばしてパーソナライズされたコードを生成してくれます。
しかも、ChatGPTは自然言語でプロンプトを入力できるので、操作するための専門的な訓練も必要ありません。誰にでも使えて、スキル差を埋めてくれる。これこそがChatGPTが今後もたらす変化なのです。
ただし、「では知識や技術が不要になるのか」と言うと、そうではありません。何度も述べたように、ChatGPTは副操縦士であり、生成した内容の最終的なチェックは人が行う必要があるからです。部下が作った成果物を上司として確認するようなイメージでしょうか。
当然、正しくチェックするためにはその仕事に関する知識と技術が必要です。ChatGPTによって知識や技術が無駄になるのではなく、むしろChatGPTの仕事をより高位で判断するために、知識と技術はより必要になるのです。
こう言ってもいいでしょう。
ChatGPTは、これまでまったくできなかったことをできるようにするのではなく、できてはいたが時間がかかっていた作業をもっと効率的に行えるようにしてくれるもの、と。
誰もが生成AIを使いこなし、人間の能力は拡張されていく
ChatGPTが変化をもたらすのは、ビジネスの世界だけではありません。前述した「誰にでも使える」メリットは、むしろ一般社会にこそ恩恵をもたらします。
大胆に予測するなら、今後ChatGPTのような生成AIがさらに進化し、社会に溶け込んでいくことで、私たちは誰もが自然言語で生成AIに指示を出すようになるでしょう。そうやって、社会全体が生成AIを使いこなすようになれば、人は従来よりも大きく能力を拡張できるはずです。
このように書くと、「自分は大丈夫だろうか」「置いていかれないだろうか」と不安になるかもしれません。
しかし、安心してください。
Webを検索する際、例えば「東京 観光地」と単語を複数使って検索したり、Instagramなら「#東京」などのハッシュタグで検索したりしているでしょう。
今となっては感覚が麻痺しているかもしれませんが、こうした検索方法はWebが登場する以前にはなかったものであり、立派なスキルと言えます。
多くの人は、この検索スキルを学校などで学んだわけではないと思います。インターネットを使っているうちに自然と身に付いたものでしょう。
同じように、ChatGPTに代表される生成AIを使いこなすためのスキルも、使っていればいつの間にか身に付いているはずです。
本連載では5回に分けて、ChatGPTの基本的な仕組みから活用方法までを解説してきました。名前は知っていたけれど使い方はよくわからなかったという人や、なんとなく使っていたけれど仕組みは理解していなかったという人にとって、有益な情報を提供できていたら嬉しく思います。
おそらくChatGPTは今後も進化を続けるはずですし、さらにいろいろな企業から別の生成AIサービスも登場してくることでしょう。その際は、また改めて解説できればと思います。