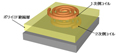交流の電圧・電流・抵抗の考え方(コンデンサが入るので)は少し複雑
連載2回目に示したように、抵抗の場合は「電圧・電流・抵抗」相互の関係は単純なオームの法則で説明できるものでした。しかし交流の場合はコンデンサが回路に入り、そのときコンデンサがふるまう様子は、先に説明したような電圧と電流の関係になります。そのため単純なオームの法則から少し拡張した形の計算になります。
RとCの直列接続回路は端子電圧の足し算がそのまま電源電圧ではない
図2-3-1のような直列接続回路(抵抗1kΩ、コンデンサ0.1μF)を考えてみましょう。直流でも交流でも、連載3回目の図1-3-1や図1-3-2で説明したように、電流は抵抗とコンデンサに同じように流れます。
例えば仮に、流れるピーク電流が5mA(周波数は5kHz)だとすると、図2-3-2のような電圧がそれぞれの素子の端子に生じることになります。なお実測結果なので計算値とは若干差異が出ています。
抵抗はピーク電圧2.32V、コンデンサはピーク電圧1.72Vです。この関係は、抵抗の端子の電圧はオームの法則そのまま、コンデンサも前回の抵抗の大きさに相当する量を算出する式によりオームの法則と同じようになります。
ただし直列に接続された場合の合成の電圧量は、同図一番下のようにそれぞれポイントごとの足し算になります。ここで回路全体のピーク電圧は2.80Vになっています。2.32V + 1.72V = 4.04Vにはなっていないことに注意してください。
では、逆にここで「5mAの電流が流れた」と仮定せず、ピーク電圧2Vの交流(同じく周波数は5kHz)が回路に加わり、それに相当する(適合した)量の電流が流れたとしましょう。この様子を図2-3-3に示します。ここでも実測結果なので計算値とは若干差異が出ています。
まず同図一番下の回路全体の電圧波形が、ピーク電圧2Vの交流になり、ここが決まることになります。
コンデンサでは、電圧と流れる電流のタイミング(位相)がずれていることはどんな状態でも変わりません。そのため結果的に抵抗とコンデンサの端子電圧は1/4周期タイミングがずれていること、これも同じように決まってしまいます。
その結果として図2-3-2の縮尺が変更されたような形になり、この図のような波形の大きさになります。ここで抵抗両端の電圧は1.60V、コンデンサ両端の電圧は1.16Vになります(回路に流れる電流は3.60mAになる)。しかし1.60V + 1.16V = 2.76Vであり、これは2Vではありませんね。
このように、合成した電圧の大きさは、単純にそれぞれの端子電圧を足し合わせた大きさにはなりません。そのため例えば図2-3-1の直列接続回路を、テスターを用いて抵抗とコンデンサの電圧を測定して足し算しても、その結果は電源の電圧の大きさにはなりません。以下の2点が重要です。
- 抵抗とコンデンサでタイミング(位相)が1/4周期ずれていること
- それぞれの電圧を単純に足し合わせた大きさが合成された電圧の大きさにならない

|
|
図2-3-3 図2-3-1の回路で2V、5kHzの電圧が加わったときの各部分の電圧の大きさ |
交流の動きを視覚で理解 - 難しい話は抜きにシミュレーションを活用
本来は回路の計算方法をきちんと説明すべきなのですが、「まずは動かしてみよう」というこの連載の視点に立って、少し難しい説明は割愛して、視覚的にわかるように話を進めていきましょう。
視覚的という視点から、以降では電子回路シミュレーションを活用していきます。電子回路シミュレータについては後ほど改めて説明します。
コイルの動きについても簡単に説明
ここでコイルの動きも簡単に説明しておきましょう。コイルも抵抗と同じように電流を妨げるように働きますが、コイルは図2-3-4に示すような構造であることから、直流信号は素通しです。
コイルは直流は素通しですが、周波数が上がってくると、周波数に比例して電流を通さないようになってきます。オームの法則的にコイルに加わる電圧と電流の関係を表してみると、

|
となります。
コイルは図2-3-5のように、電圧に対して電流の変化するタイミング(位相)が波形の1周期の1/4だけ遅くなっています。逆に電流を基準として考えてみると、1/4だけ電圧が早くなっています。
著者:石井聡
アナログ・デバイセズ
セントラル・アプリケーションズ
アプリケーション・エンジニア
工学博士 技術士(電気電子部門)