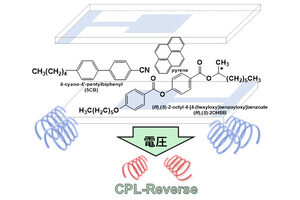「航空機とセンサー」というテーマの下、これまでに取り上げてきたのは、機体にセンサー機器を組み込む、あるいはセンサー機器をぶら下げる、といった形であった。ところが何事にも例外は発生するもので、機体の一部を脱着式センサーにしてしまう事例もある。→連載「航空機の技術とメカニズムの裏側」のこれまでの回はこちらを参照。
改良型でセンサー機器の搭載スペースを増設
それが、ロッキード(現ロッキード・マーティン)の偵察機、U-2ドラゴン・レディ。
U-2は当初、コックピット後方にあるQベイと呼ばれる区画にカメラを搭載していた。薄くて長い特製のフィルムと高性能の光学系を組み合わせたカメラにより、2万メートルを超える高度から、(晴れていれば)地上の精細な写真を撮影可能。そしてソ連上空を領空侵犯して、貴重な写真をたくさん持ち帰った。
その後の改良型では、センサー機器の搭載スペースが増やされた。まず、翼下に「スーパーポッド」と呼ばれるポッドが加わった。全長7.26m、容積2.35立方メートルで、ペイロードは350kg程度。ここはたとえば、電子情報(ELINT : Electronic Intelligence)や通信情報(COMINT : Communication Intelligence)の収集装置を搭載する。
長いお鼻は交換可能
そして本稿の本題が機首。U-2Rや現行モデルのU-2Sは、初期型のU-2と比べると機首が伸びている。実はこの機首もペイロード搭載スペースになっている。ここに搭載するセンサーの主役は2種類。
いずれも、機首に内蔵する……のではなく、センサー機器を組み込んだ機首全体をユニットとして脱着する仕組み。だから任務様態に応じて、センサーを組み込んだユニットを取り替えて飛び立つことになる。そのため、任務によって機首の外見が違っている。
したがって、機体構造はコックピットの少し前で途切れており、その前方が交換可能な部分ということになる。
搭載するセンサー(1)SYERS-2C
搭載するセンサーの一つが、コリンズ・エアロスペース製のSYERS-2C(Senior Year Electro-optical Reconnaissance System 2C)。可視光線用のカメラに加えて、短波長赤外線と中波長赤外線に対応するセンサーを備える。
これらのセンサーを組み込んだ部分全体が、機軸を中心として回転する。すると左右に首を振ることができる。だから、例えば国境線の手前側で国境線に沿って飛びながら、仮想敵国の側にセンサーを向けて映像を撮る、といったことができる。これなら領空侵犯しなくても済む。
内蔵したセンサーのユニットだけ首を振る方法も考えられるが、そうすると、首を振る範囲全体をカバーできるように、センサー窓を設けなければならない。下半分の左右を広くカバーしようとすると、おそらく百数十度の範囲に渡って継目のないセンサー窓を設けなければならないだろう。
センサー窓の部分に構造材がかかると具合が悪いから、上半分だけで強度を持たせなければならない。そんな面倒な設計をするよりも、センサーの位置に合わせて窓を開けて、機首全体を回転させる方が合理的ではある。
SYERS-2Cは3種類の波長について一度に画を撮れるから、同じ対象物が、可視光線、短波長赤外線、中波長赤外線のそれぞれで違った写り方をするはず。それらを照合すれば、例えば「可視光線では見えなかったものが赤外線だと見える」といったことが起こり得る。
搭載するセンサー(2)ASARS-2
もう一つが、ASARS-2(Advanced Synthetic Aperture Radar System 2)という合成開口レーダー(SAR : Synthetic Aperture Radar)。
SARだから、得られる映像は地表の凸凹を示すものになる。こちらはアンテナが左右に付いていて、やはり側方をサーチする。
ただしSYERS-2と違い、機械的に首を振る仕掛けはないようだ。最新型のASARS-2Bでは、アンテナがAESA(Active Electronically Scanned Array)化されて、広い範囲を迅速に走査できるようになったという。AESAアンテナなら電子的に首を振れるから、機械的にアンテナを動かす必然性はない。
初期型は事情が違った
手元に初期型U-2(U-2CならびにU-2Fに対応)のフライトマニュアルがある。それを見ると、機首はセンサーを搭載する構造にはなっておらず、航法・通信関係の電子機器が収まっていたようだ。
U-2の有用性が評価されて「あれもこれも」と要求が増えた結果として、センサーの搭載場所を増やすことになり、その一環として機首を改設計したということであろうか。
通常の航空機と比べると圧力は低いが、一応、U-2のコックピットも与圧装置は付いている。ただ、機体構造にかかる負荷が大きくなりすぎないように控えめな圧力にしているから、高高度飛行を行うとき、パイロットは宇宙服みたいなプレッシャー・スーツを着て搭乗しないといけない。
とはいえ、コックピットと機首の間にはなにがしかの圧力差がある。だから、機首の構造材には相応の強度が求められるはずだ。そこで、もともと繊細な機体構造に手を入れて、機首にもセンサー機器を搭載できるようにしたのだから、設計担当者はかなり苦労したのではないだろうか。
著者プロフィール
井上孝司
鉄道・航空といった各種交通機関や軍事分野で、技術分野を中心とする著述活動を展開中のテクニカルライター。
マイクロソフト株式会社を経て1999年春に独立。『戦うコンピュータ(V)3』(潮書房光人社)のように情報通信技術を切口にする展開に加えて、さまざまな分野の記事を手掛ける。マイナビニュースに加えて『軍事研究』『丸』『Jwings』『航空ファン』『世界の艦船』『新幹線EX』などにも寄稿している。このほど、姉妹連載「軍事とIT」の単行本第4弾『軍用レーダー(わかりやすい防衛テクノロジー)』が刊行された。