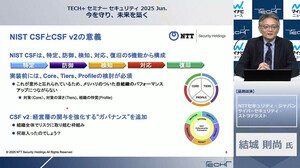今回は、ふと思いついて調べてみたテーマ。すなわち「航空機の整備におけるデジタル・ツインの活用」を取り上げてみる。誰しも考えることは似ているようで、この話をテーマにした記事がいくつも見つかった。→連載「航空機の技術とメカニズムの裏側」のこれまでの回はこちらを参照。
デジタル・ツインとは:レイセオンのIDCを見学
デジタル・ツインとは、「物理的なデバイスや製品などの仮想的な複製を、コンピュータ上に構築するもの」という意味。コンピュータ上で構築するものだから、数値・数式の形に落とし込む必要がある。実物を用いて実施している試験や検証をデジタル・ツインに置き換えることで、コンピュータ・シミュレーションによる試験や検証を行える理屈となる。
すでに、航空機の開発・製作に際して、こうしたデジタル技術を活用している事例はある。例えば、ボーイングとサーブが開発を進めている米空軍向けの新型練習機・T-7Aレッドホークが該当する。
RTXのレイセオン部門(旧レイセオン・ミサイルズ&ディフェンス)では、マサチューセッツ州アンドーバーとアリゾナ州ツーソンの事業所にIDC(Immersive Design Center)という施設を置いている。
コンピュータの中に構築したデジタル・ツインは物理的な「モノ」ではないから、それを可視化して、関係者の間で現実のイメージを共有するために、こういう施設を活用する。製品だけでなく、自社の工場施設を構築する場面でも活用しているそうだ。
従来であればパーツやコンポーネントを試作して、さまざまな設計案を比較検討したり、試験に供したりしていたものをコンピュータ・シミュレーションに置き換えることができれば、早期にリスクの低減を図り、結果として開発を迅速化・効率化する効果を期待できる。
また、操縦訓練におけるフライト・シミュレータの活用と同様に、コンピュータ・シミュレーションには「現物を作って行うにはリスクが大きすぎる試験・検証」を実施しやすくなる利点もある。「この部分をこのように変えてみたら、どういう影響が生じるだろうか?」という話が何か出たときに、まずそれをデジタル・ツインで検証する。
最終的には現物を作って試験しなければならないだろうが、そこに行き着く過程での試行錯誤、アイデアの絞り込みを行う際の迅速化は期待できよう。
機体構造の寿命予測とデジタル・ツイン
IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers、電気・電子技術者学会)のWebサイトに、航空機の整備におけるデジタル・ツインの活用について取り上げた記事があった。部品の寿命を適切に予測する仕組みを構築することで、機体整備のための戦略策定を支援するとの趣旨だった。
一般的には、過去の実績などに基づいて「この機器は○○飛行時間ごとに点検する」「このパーツは○○サイクルごとに交換する」といった形で整備基準を定めている。いわゆるTBM(Time-Based Maintenance)である。
それを、機器やパーツの状況に合わせて実施する形、いわゆるCBM(Condition-Based Maintenance)に変えようという流れがあるが、これを実現するには「コンディションを適切に把握できること」という前提条件がある。
すると、コンディションを把握するためのセンシングや、「実運用環境下で、どれぐらい使用したら交換しなければならない状態になるか」という予察の仕組みが欠かせない。このうち予察の部分で、デジタル・ツインの活用が考えられる。
実際、あるエンジン部品について「1,000サイクルごとに点検」となっていたものが、それより少ないサイクル数で壊れる事象が発生してしまい、点検サイクルの短縮をメーカーが指示した実例がある。そうしたトラブルを防ぐには、まず適切な予察ができる必要がある。時間単位であるサイクル数単位であれ、「えいや」で決めるわけにはいかない。ちゃんと裏付けがなければならない。
ロールス・ロイスの取り組み
こうした取り組みをアピールしているメーカーの一つに、ロールス・ロイスがある。同社は以下のようなことを述べている。
デジタル・ツインを活用することで、エンジンの整備や修理が必要になる時期を判断するために確率ベースの手法に依存する必要性が減る
エンジンのデジタル・ツインを構築して、それを実機に搭載した物理的なエンジンと同じように動作させる。これにより、エンジンがどのように動作しているかを判断するとともに、整備が必要になる時期を予測する
整備や部品交換が必要になるタイミングの予察を適切に行えれば、まだ使える部品を交換する無駄を減らせるのではないか、というわけだ。また、本当に整備が必要になったときに整備することで、機体のダウンタイム短縮や信頼性向上につながる、というのがロールス・ロイスの説明。
ただし、こうした話が能書き通りに機能するには、デジタル・ツインの中核となるコンピュータ上のモデルが、現物を正確に模擬している必要がある。モデルに間違いがあったのでは、ツイン(双子)どころか別人になってしまう。
そこでモデルの精度を高めるため、単にモデルを構築するだけでなく、現物を対象とするデータ収集を行ってフィードバックする仕組みが必要になる。エンジンであれ機体であれ、そこにセンサーを取り付けて状態監視を行い、そのデータをデジタル・ツインの側にフィードバックする。それが機能することで初めて、信頼できるデジタル・ツインができるといえるかもしれない。
また、そのフィードバックをリアルタイムで行えれば、デジタル・ツインの継続的な進化につながる。実際、ロールス・ロイスでは、エンジンに取り付けたセンサーからのデータ送信に衛星通信を活用するといっている。これにより、世界のどこを飛んでいる機体でもリアルタイムのデータをとれる理屈となる。
著者プロフィール
井上孝司
鉄道・航空といった各種交通機関や軍事分野で、技術分野を中心とする著述活動を展開中のテクニカルライター。
マイクロソフト株式会社を経て1999年春に独立。『戦うコンピュータ(V)3』(潮書房光人社)のように情報通信技術を切口にする展開に加えて、さまざまな分野の記事を手掛ける。マイナビニュースに加えて『軍事研究』『丸』『Jwings』『航空ファン』『世界の艦船』『新幹線EX』などにも寄稿している。このほど、姉妹連載「軍事とIT」の単行本第2弾『F-35とステルス技術』が刊行された。