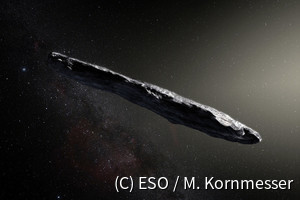2025年7月1日、地球に近づく小天体を監視する望遠鏡ネットワーク「ATLAS」が、恒星間天体「3I/ATLAS (C/2025 N1)」を捉えた。追観測と軌道解析の結果、観測史上3例目となる恒星間天体であることがわかった。
-

NASAのハッブル宇宙望遠鏡が捉えた恒星間彗星「3I/ATLAS」。2025年7月21日に撮影されたもので、この時点で彗星は地球から約4.5億km離れたところにあった。核から塵が噴き出していることがわかる Image credit: NASA, ESA, David Jewitt (UCLA); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)
3I/ATLASは10月30日ごろに太陽へ最接近して通過しており、12月19日ごろには地球へ最接近する。これまでの観測では彗星活動が確認され、コマ(ガス・塵の雲)を伴うことに加え、二酸化炭素を含む組成が示唆されている。
一方でSNSでは「異星人の乗り物」説が拡散するなど、憶測も先行した。ただ、現時点で公表されている観測結果は彗星活動と整合しており、人工物を示す根拠は確認されていない。
3I/ATLASはどんな天体か
ATLASが捉えた新天体は、追観測と過去画像の解析によって軌道が絞り込まれ、太陽系外から飛来した恒星間天体として「3I/ATLAS (C/2025 N1)」と命名された。
恒星間天体とは、太陽系外を起源とし、双曲線軌道を描いて太陽系を通り過ぎていく天体のことだ。
これまでに確認された恒星間天体は3例に限られる。ただし、太陽系に飛来した恒星間天体が3個だけという意味ではない。観測網の感度や探索範囲の制約により検出例が少ないだけで、過去にも多数が通過したと考えられている。
1例目は2017年の「1I/オウムアムア」(ʻOumuamua)で、ハワイのPan-STARRS1が発見した。発見当初は彗星として扱われたが、その後、彗星活動が明確に確認できないことなどから性質の解釈が分かれ、恒星間天体の研究の出発点となった。
2例目は2019年に見つかった「2I/ボリソフ」(Borisov)で、典型的な彗星活動が観測され、恒星間彗星として位置付けられた。
そして3例目が、今回見つかった3I/ATLASだ。軌道は「恒星間」を裏付けるほど極端で、軌道解では離心率e=6.14前後、軌道傾斜角i=175.1度(黄道面に対してほぼ逆行)、近日点距離q=1.357天文単位とされ、太陽の重力に束縛されない速度で太陽系を通過している。太陽の重力の影響がほとんど及ばない無限遠方での相対速度は約60km/sと見積もられ、軌道力学的に大きく際立つ天体のひとつである。
3I/ATLASは10月30日、太陽から約1.4天文単位(約2.1億km)で近日点(太陽に最も近づく点)を通過した。近日点通過時は地球から見て太陽の向こう側に位置していたため、地上からの観測は難しい条件となった。
今後、12月上旬には、見かけ上の位置が太陽から離れて観測が再開できる見込みとなっている。そして12月19日ごろに地球へ最接近し、地球から約1.8天文単位(約2.7億km)を通過したのち、太陽系を抜け出すように飛んでいく。
過去2例の恒星間天体よりも観測しやすい3I/ATLAS
恒星間天体は、どこからともなく突如現れること、タイミングや観測機器の制約によって観測できる機会が限られていることなどから、多くの謎と魅力を残して続けている。
3I/ATLASについても、現時点でわかっていることは限られる。それでも「3例目」という事実にとどまらず、複数の観点から注目を集めている。
最初に見つかった1I/オウムアムアは、彗星のような明瞭なコマが見えず、形状や姿勢、加速度の変化などをめぐって解釈が分かれた。一方、2I/ボリソフは彗星として比較的素直な振る舞いを示した。
3I/ATLASは、発見当初から彗星活動が確認された「恒星間彗星」であり、1I/オウムアムアと2I/ボリソフに続く比較材料として、氷や塵の性質をより詳しく検証できる点に価値がある。米国航空宇宙局(NASA)は、太陽系の彗星との差異が、他の惑星系の組成の理解に手がかりを与えるとして、3I/ATLASを科学的に重要な対象だと説明している。
“典型的な彗星活動”は複数の手段で示されている。たとえば、7月のハッブル宇宙望遠鏡の観測では、核から放出された塵が涙滴状の形状を形作る様子が捉えられた。また、別の解析では、近日点前の3.8天文単位付近でもすでに活動を見せており、太陽側から放出された塵が尾を形成していることが報告された。塵の放出量は、概算で毎秒6〜60kgと推定されている。
核の大きさは不確かながら、ハッブル宇宙望遠鏡の画像を用いた研究では、コマの明るさ分布から、核の有効半径は最大でも約2.8km程度と見積もられている。彗星は核そのものより周囲のコマが明るさを支配しやすく、核の推定は難しい。ただ、核が極端に小さい場合は揮発性物質の供給で活動を説明しにくく、一定の範囲まで推測できる。今後の観測で推定値はさらに狭まっていくだろう。
組成面では、二酸化炭素や水、一酸化炭素、シアン化物など、彗星でしばしば観測される分子が挙げられている。さらにニッケルの存在が話題となったが、彗星で前例がないわけではなく、恒星間彗星2I/ボリソフや一部の太陽系彗星でも見つかっている。
また、3I/ATLASは過去の2つの恒星間天体と比べ、観測しやすい条件がそろっていることも特徴だ。地上の望遠鏡に加え、宇宙望遠鏡による観測も多数行われている。さらに、NASAの火星探査機「マーズ・リコネサンス・オービター」(MRO)や「メイヴン」、小惑星探査機「ルーシー」なども、高解像度撮像や紫外線分光観測を実施し、彗星の周囲に広がる水素を可視化するなどの成果を挙げている。
「異星人の宇宙船」説を検証する
3I/ATLASをめぐっては、「異星人の探査機や宇宙船ではないか」という説がSNSを中心に拡散した。
とくに、ハーバード大学の天体物理学者アヴィ・ローブ教授らの論文が、拡散に拍車をかけた。この論文はarXiv(査読前論文の公開サイト)に掲載されたもので、「異星人の技術」の可能性に言及しており、「ハーバード大学教授が提示した仮説」としてSNSなどで引用された。ローブ氏は1I/オウムアムアをめぐっても、同じような説を提唱したことがある。
同論文は「教育的な演習」と断りつつ、初期観測から得られた軌道の特徴――金星・火星・木星の近傍を通る点や、近日点前後に地球から見て太陽に近い方向を通る点や、さらに重力以外の要因による加速を仮定した議論などから、異星人の技術によって作られたものである可能性に言及している。
ただし、この種の主張を支持する根拠は、現時点では乏しい。
第一に、NASAは「3I/ATLASは活動的でコマを伴うことから彗星に分類される」と説明している。また、「彗星で一般的なガス放出に伴う微小な軌道変化と整合する」とも述べており、地球外の知的生命体の存在や関与を示す技術的な兆候(technosignatures)は確認されていないことを明言している。自然起源と整合する振る舞いが複数の観測で積み上がっている以上、人工物仮説は説得力を欠く。
第二に、「軌道が特定の惑星へ接近する」こと自体は、単独では人工物の根拠になりにくい。天文学でいう「近傍」は距離の幅が大きく、自然の天体でも結果として惑星の近くを通る軌道は起こり得る。意図を示すには、ロケット・エンジンの噴射による軌道変更を示唆する動きなど、自然現象や偶然では説明しにくい追加の証拠が必要となる。
第三に、彗星の軌道に見える加速度の変化、予測からのズレは、核からのガス噴出が生む反作用で典型的に説明される。オウムアムアでも、この加速度の変化が論争になったが、それは活動的な彗星か、小惑星のようにほとんど活動していない天体かという前提がわからなかったからだ。彗星活動が明確に見て取れる3I/ATLASでは、前提が異なる。
結局のところ、人工物説を議論の俎上に載せるには、自然現象では説明できない、なおかつ再現性あるデータが必要となる。たとえば、前述のようなロケット・エンジンの噴射による加速度の変化や、人工物を示唆するスペクトル線、通信などの電波放射が出ていることなどだ。
しかし、これまでに報告されている観測結果は、氷の揮発によってコマと尾を形成する彗星としての振る舞いと整合している。太陽系の彗星と同様に、太陽光で氷が温められて揮発し、コマと尾を作る過程で説明できるのだ。
なにより、たとえ3I/ATLASが自然の天体であっても、他の惑星系で形成された物質の成分や性質を観測で調べられる機会は、きわめて稀である。その価値は、“宇宙船でない”ことによって損なわれない。
3I/ATLASという、遠い恒星のまわりで形作られた氷と塵の塊が、いま私たちに近づいている。太陽の光にあぶられ、尾から氷と塵をまき散らし、静かに息を吹き返すように活動している。その瞬間を私たちは最先端の観測技術で見つめている。3I/ATLASは、恒星間天体に関するいくつかの答えと、新たな問いをもまき散らしながら、やがて太陽系を去って行くことだろう。
【参考文献】