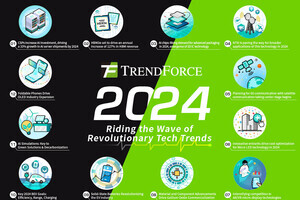台湾の半導体およびハイテク市場動向調査会社であるTrendForceが、2025年に新たなビジネスチャンスを生むであろう10個の主要な技術トレンドを発表した。
半導体分野からはAIチップ、HBM、CoWoSなどのAI関連技術テーマを含み、AIに関する話題が大半を占めるものとなっている。
生成AIがけん引、ヒューマノイドロボットとサービスロボットが大幅にアップグレード
NVIDIAやTeslaなどの大手企業のけん引によってAIが進歩し続けるなか、ロボットは2025年も引き続きAI普及の中心的な焦点の1つとなる見込みである。
その開発では、機械学習、デジタルツイン(シミュレーションプラットフォーム)、協働ロボット、移動ロボットアーム、ヒューマノイドロボットのトレーニングに重点が置かれ、さまざまな環境に適応し、シームレスな人間と機械の相互作用が目指されている。
また人型ロボットは、米国および中国メーカーからの多額の投資に支えられ、2025年から量産が開始される予定である。世界の人型ロボット市場は、2024年から2027年の間に年平均成長率(CAGR)154%という高い伸びを示し、市場価値も20億ドルを超えると予測されている。一方の産業用ロボットは主にロボットアームを活用したピッキングなどの作業に重点を置いているが、生成AIを搭載したサービスロボットは、マルチモーダルインタラクション、情報検索、テキスト要約、スケジュール作成を可能とする。これらの進歩により、サービスロボットの機動性、仲間意識、汎用性が向上し、サービスロボットはロボット技術革新の次のフロンティアとして位置付けられることとなる。
技術の進歩が市場の標準化を推進、AIノートPCの普及率は2025年に21.7%に
高性能なAI処理が可能なノートPCは、テクノロジーの急速な進歩により、今後数年間で標準になると予想されている。
2025年中にAIノートPCの普及率は21.7%に達し、2029年には80%近くまで上昇すると予測されている。この伸びは、従来のx86アーキテクチャにおける性能向上に加えて、高いエネルギー効率を提供するArmアーキテクチャの採用したモデルの販売拡大も貢献すると見られている。
エッジにおける推論需要の高まりを踏まえ、エネルギー効率の向上が重視されるため、ArmベースのAIノートPCが市場シェアを拡大する見込みである。Windows on Armシステムの人気が高まることで、消費者は高性能で低消費電力のAIノートPCにアクセスできるようになる。
AIアプリケーションは現在、クラウドコンピューティングに依存しているが、TrendForceでは、エッジAIの進歩により、AIノートPCの採用がさらに促進されると予測している。エッジAIは、ローカルでのAI処理であり、この強化によりノートPCの仕様の幅を拡大させる。これにより、音声コマンドや画像認識などのリアルタイムタスクをより効率的に処理できるようになり、ユーザーエクスペリエンスが全体的に向上することとなる。また、ローカライズされたAI処理により、特に機密情報のデータ プライバシーが確保され、AIノートPCに対する消費者の信頼が高まることも期待される。AI技術が成熟するにつれて、エッジAIはスマートオフィスや自動化されたワークフロー管理における新たな生産性の可能性を解き放ち、多様なユーザーのニーズに対応することができるようになる。
AIサーバの出荷は2025年に28%以上増加
クラウド・サービス・プロバイダ(CSP)と企業クライアントからのAIインフラストラクチャに対する需要の高まりが、AIサーバ市場の成長を牽引している。
2024年には、GPU、FPGA、ASICを搭載したものを含むAIサーバの世界出荷量は前年比42%増と大きく伸びることが予測されている。2025年は、CSPとソブリンクラウドのオペレーターからの強い需要に後押しされ、年間出荷量の伸びは同28%を超え、サーバ市場全体の15%を占めると予想されている。
また、2025年にはHBM3e 12hi(12層)が主流メモリとなり、NVIDIAのB300およびGB300プラットフォームでの採用が進むと予想されている。先行するSK hynixは12hi世代でAdvanced MR-MUFテクノロジーを活用し、各ダイスタッキングステップでプレボンディングプロセスを導入している。同社は、MUF材料を最適化し、処理時間を延長することで、ダイの反りを効果的に制御することを目指している。
追いかけるSamsungとMicronは、12hi製品にTC-NCFスタッキングアーキテクチャを採用している。この方法では反りの制御が容易になるが、処理時間が長くなる、累積応力が大きくなる、放熱性能が低下するなどの課題があるため、大量生産時に迅速な歩留まり向上を達成する上での不確実性があるといえる。
12hiの採用はHBM3、HBM3e、HBM4、HBM4e世代(2027~2029年)と幅広く進むことが見込まれるため、量産のタイムラインは数年にわたるといえる。その結果、12hiの製造プロセスの歩留まり率の改善と安定化は、2024年以降もサプライヤにとって重要な優先事項となるとみられる。
最先端プロセスとAIが半導体のイノベーションを推進、2025年にCoWoSの需要が増加
半導体製造が7nmプロセス以降の微細化に突入し、EUVリソグラフィが採用されたが、従来のFinFETアーキテクチャは3nmで物理的限界に達した。これにより先端プロセス技術の分岐が促進され、2023年に入ってもTSMCとIntelが3nm相当プロセスでFinFETの採用を継続した一方、SamsungはMBCFETアーキテクチャによるGAAFETへの移行をリードすることを目指し、2022年より他社に先駆ける形で生産を開始した。しかし、同技術は歩留まりが低迷しており、広範な採用には至っていない。
TSMCは2025年までに2nmプロセス(N2)でナノシートトランジスタアーキテクチャを導入し、Intelは1.8nmプロセス相当の「Intel 18A」にてRibbonFET(ナノシートFETのIntel独自の呼称)テクノロジを採用する予定である。Samsungは2025年での大規模生産達成を目指して、MBCFETベースの3nmプロセスの改良を継続していく見込みで、最終的に3社すべてがGAAFETを正式に採用することとなり、4面ゲートコンタクトによる優れたトランジスタ制御を目指し、より高いパフォーマンス、より低い消費電力、単位面積あたりのトランジスタ密度の向上などを顧客に提供していくこととなる。
AIアプリケーションによって促進されるカスタマイズされたチップと、より大きなパッケージ領域に対するニーズの高まりは、同時に2025年のCoWoS需要を押し上げることにもなる。2025年におけるCoWoS市場は、いくつかの重要な展開が予想されており、最大のポイントはNVIDIAのCoWoSに対する需要が、TSMCの総CoWoS生産量の約 60%にまで増加すると予測されており、こうした需要の増加を踏まえTSMCでは2025年末までにCoWoSの月間生産能力を倍増させて、約7万5000~8万ユニット規模へと引き上げる計画である。
また、2025年上半期にNVIDIAのBlackwellプラットフォームが発売されると、CoWoS-Lの需要が増加すると、CoWoS-Sの需要を上回ることとなり、CoWoS-Lが全体の60%以上を占めることが予想される。さらにCSPがカスタムAIチップ(ASIC)の開発への投資を増やしており、AWSをはじめとする大手CSPプレーヤーからのCoWoSの需要が2025年には高まることが予想されるという。
両刃の剣となるAI、複雑な攻撃に対抗するためのサイバーセキュリティ防御と脅威検出の強化が必要に
現在、世界のサイバーセキュリティの焦点は、クラウド主導のIoT時代のハードウェアとソフトウェアにある。さまざまなテクノロジーが進歩し続ける中、攻撃と防御の戦略はこれまでに比べてより複雑化しており、企業は徐々にIoTからAIへと重点を移している。一方、生成AIでは、オペレーターの権限強化と脅威検出の加速を通じてサイバーセキュリティ防御を強化するという2つの大きなトレンドが見られる。
オペレーターの権限強化により、オペレーターは自動化とデータ統合を通じて主要なリスクを特定して対応できるようになり、自然言語を使用して対話できるようになる。また、脅威検出の加速により、ユーザーをガイドし、検出サイクルを大幅に短縮する運用上の推奨事項を提供することで、脆弱性をより迅速に特定できるようになる。
しかし、生成AIはハッカーによって、列挙分析やフィッシングなどの攻撃戦術を強化するために同様に悪用される存在でもあるといえる。LLMの作成に関連するリスクを分析すると、入力操作による誤った出力、トレーニング中に導入された脆弱性、包括的なアクセス制御の欠如、機能の過剰な自律性など、いくつかの重大な課題が示されるが、2025年が近づくにつれて、これらのリスクは、企業がAI駆動型製品やサービスを開発する際に対処しなければならない差し迫ったサイバーセキュリティの課題を表しているといえる。
AMOLEDが中規模アプリに拡大、ノートPCへの搭載率が3%に
Appleは2024年、RGB AMOLED(有機EL)パネルを搭載したiPad Proシリーズを正式に発売し、RGB AMOLEDが中型製品アプリケーションへ拡大する兆しを見せた。タブレットを超えて、AMOLEDパネルをノートPCに統合するトレンドも勢いを増している。Appleは2026年から2027年の間にMacBookシリーズにAMOLEDパネルを導入する予定であるが、すでにパネルメーカーに投資の拡大を奨励し始めている模様である。現在、予想される需要に対応するために、RBG AMOLED生産ラインを第6世代から第8.6世代または第8.7世代に移行する必要がある。
この戦略的な転換により、他のブランドは既存の生産ラインを活用して市場でのポジショニングを加速できるようになる。2025年にはAMOLED搭載ノートPCの市場規模は600万台を超え、普及率は3%に達すると予測されている。
VR/MRが産業活用で浸透、ニアアイディスプレイも進展
2024年のVR/MRヘッドセット市場における最も重要な進展は、AppleのVision Proの発売である。これは、VR/MRデバイスの主な使用例を娯楽やレジャーといったホビーユースから産業分野における生産性向上ツールへと移行させ、VR/MRデバイスの再定義を促すものとなる。この再定義により、Apple以外のメーカーが革新的な新製品をリリースするきっかけとなることが期待される。
Vision ProのディスプレイはOLEDoS(OLED on Silcon)テクノロジを活用し、3000PPIを超える解像度を実現するハイエンドのVR/MRデバイスに最適なニアアイディスプレイ(人体に装着することで目の前に映像を映すことができるディスプレイ)ソリューションとなっている。TrendForceは、VR/MRデバイスの出荷台数が2030年までに3700万台に達すると予測している。
補助デバイスとして位置づけられるARグラスも、AI技術の進歩に後押しされ2024年には市場の関心が再び高まる様子を見せた。MetaのOrionは量産デバイスではないが、LEDoSディスプレイとSiCベースの導波管を統合し、70°の優れた視野角を実現し、重量100g未満の軽量設計の新たなベンチマークを打ち立げた。LEDoSに加えて、ARグラスの現在のニアアイディスプレイ技術には、OLEDoS、LCoS、レーザービームスキャン(LBS)があり、ARハードウェア設計の柔軟性を高める多様なソリューションが提供されつつある。TrendForceは、ARデバイスの出荷台数が2030年までに2550万台に達すると予測している。
人工衛星の小型化と低コスト生産が2025年に世界的な通信とIoT革命を推進
衛星アプリケーションに関する3GPPリリース17のガイダンスもあり、地球低軌道における超小型衛星(CubeSat)の数が飛躍的に増加している。新興の衛星企業は、超小型衛星の低コスト製造技術を活用し、大規模な衛星コンステレーションを形成して、低遅延の衛星通信を世界中に提供するようになっている。
2025年にかけて、超小型衛星の活用が加速する見込みで、中小規模の新興衛星事業者たちは、モジュール式の衛星プラットフォームと既製部品を活用することで、超小型衛星の大量生産を推進しており、これにより生産コストの削減が進む見込みである。同時に、これらの企業は、宇宙状況認識(SSA)用の超小型衛星コンステレーションを展開しており、宇宙ゴミ(スペースデブリ)の監視と除去に重点を置くようになっている。さらに、衛星IoTアプリケーションの開発も急速に進んでおり、農業センサなどの分野でのIoTデバイスのリモート監視をサポートし、遠隔地やサービスが行き届いていない地域での接続性におけるイノベーションを推進するようになっている。
モジュール式エンドツーエンドモデルの製造とレベル4ロボタクシーの商業化が加速
エッジAIの主要応用分野の1つである自動運転技術は急速に進歩している。Teslaはエンドツーエンド(E2E)モデルの採用を先導しているが、ほかの自動車メーカーもAI技術と計算能力への投資を加速させており、2025年にはこのアーキテクチャに基づく大量生産が始まると予想される。ただし、ほとんどのメーカーは、解釈可能性とデバッグの点で利点があるモジュール式のエンドツーエンドモデルを採用すると予想されている。
E2Eモデルはデータ駆動型であり、多様なデータセットに大きく依存している。生成AIは、そのオープン性と創造性により、これらのモデルをトレーニングするための多様で珍しいシナリオを生成する上で重要な役割を果たし、データ分布のロングテール問題に効果的に対処している。
AI技術の進歩は商業分野にも広がっている。規制の枠組みが徐々に改善されるにつれて、レベル4の自律型ロボタクシーの活用と商業化が加速する見込みである。しかし、電動化と自律運転の両方の課題は地政学的要因によってさらに深刻化しており、技術と商業の拡大の取り組みを複雑にしている。
EVとAIデータセンターがバッテリーとエネルギー貯蔵のイノベーションを推進
電気自動車(EV)市場の成長が鈍化しており、中でもBEV(バッテリーEV)の減速が顕著である。2025年までに、BEVの成長率は13%に縮小すると予測されている。航続距離の不安がBEV採用の大きな障壁であり、業界はこの課題の解決に注力している。
バッテリー技術では、CATLが4C充電レートのLFPバッテリーを導入し、10分の充電で600kmの航続距離を実現している。これらのバッテリーは、2025年には市場でより広く採用されると予想される。また、半固体バッテリーが2024年に量産に入り、2025年には車両への統合が加速すると予想されるほか、完全固体バッテリーも2027年以降に商品化されると予測されている。
充電インフラに関しては、商用トラックや乗用車向けにカスタマイズされたメガワットレベルの充電システムが2024年に導入されるなど、高出力充電技術の開発が促進されている。これらの進歩は、航続距離の不安を軽減し、より速い充電と航続距離の延長に対する高まる需要を満たすことを目的としている。
充電技術の進歩と同時に、自動車メーカーは市場の変化に適応し競争力を維持するために、EVの全体的なパフォーマンスとユーザーエクスペリエンスの向上にも取り組んでいる。スマートコネクティビティと自動運転機能がEVに広く採用され、エネルギー効率、インテリジェンス、安全性が向上することが期待されるほか、AIデータセンターの急速な拡大により、高度なエネルギー貯蔵システムの需要が急増しており、技術進歩とコスト低減により、世界のエネルギー貯蔵設備の容量は2025年には240GWに達すると予想されるとする。AI技術の急速な普及により電力需要が増加しており、再生可能エネルギーの出力を安定させ、停電時にバックアップ電源を提供し、データセンターの信頼性を向上させるためにエネルギー貯蔵システムが不可欠になっているためである。
データセンター業界は堅調な成長を続けているが、今後も新しい施設の建設は安定的に続き、次世代のエネルギー貯蔵システムに多大な商機をもたらすことが期待されている。この傾向は、AIと再生可能エネルギーのエコシステムの拡大するインフラストラクチャのニーズをサポートする上で、エネルギー貯蔵が重要な役割を果たすことを意味するという。