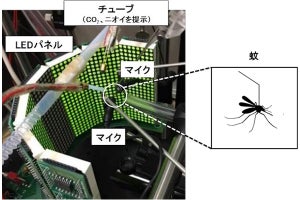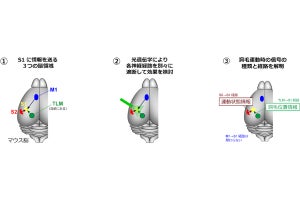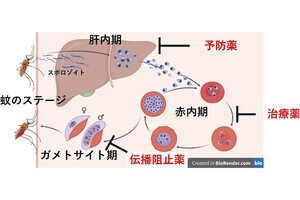理化学研究所(理研)、東京慈恵会医科大学(慈恵医大)、科学技術振興機構(JST)は6月21日、哺乳類の血液凝固に関わる血中ペプチドの「フィブリノペプチドA」(FPA)が、熱帯・亜熱帯地域に広く分布するヤブカ属の一種で、デング熱やジカ熱などを媒介する「ネッタイシマカ」の吸血を停止させる作用を持つことを発見したと発表した。
同成果は、慈恵医大の佐久間知佐子講師(現・理研 生命機能科学研究センター(BDR)栄養応答研究チーム 上級研究員)、BDR 栄養応答研究チームの小幡史明チームリーダー、BDR 無細胞タンパク質合成研究チームの清水義宏チームリーダー、同・益田恵子研究員、慈恵医大 熱帯医学講座の嘉糠洋陸教授、同・大学 基盤研究施設の岩本武夫教授(研究当時)らの研究チームによるもの。詳細は、ライフサイエンス全般を扱う学術誌「Cell Reports」に掲載された。
蚊はヒトなどの宿主を体温や呼気などで感知し、取りつくと宿主の皮膚内へと口吻を出し入れして血管を探り当て、さらに血液の味を吟味して吸血の実行の可否を決定する。蚊の吸血を促進する物質は、宿主の血液に含まれる“エネルギーの通貨”こと「アデノシン三リン酸」(ATP)だ。
ATPは血中に常にあるため、蚊は吸血促進シグナルを受け取り続けることになるが、長時間の吸血は宿主に気付かれるリスクを高めるため、適当なタイミングで吸血を停止する必要がある。吸血による腹部の膨満という物理的な制御機構が報告されていたが、一定量以上を吸血した蚊は、腹部が完全に膨満していなくても吸血をやめることから、他の制御機構の存在が示唆されていたという。そこで研究チームは今回、ネッタイシマカのメスを用いて、吸血停止に関わる物質を探索することにしたとする。
-

ATP溶液とマウス血液の摂取量の比較。蚊は、マウスからの直接吸血よりも、人工吸血法によるATP溶液の方をより多く摂取した。グラフ中の点は、実験を行った個体が示されている。摂取量の単位nlはナノリットルを示す(出所:共同プレスリリース)
まず、血中の吸血停止物質の有無を調べるため、実際の血液と、吸血を促進する合成溶液(ATP溶液)に対する吸血行動の比較が行われた。その結果、蚊はマウスからの直接吸血に比べ、ATP溶液の摂取時の方が、摂取量が多くなることがわかった。しかも、直接吸血では膨満に至る前に吸血をやめる個体が大半だったことから、吸血の後半に急速に増加・活性化する血中の何らかの物質と推測された。
-

ATP溶液に血清を添加した時の満腹蚊の割合。(左)蚊の吸血行動におけるATP溶液摂取量の解析。緑色に着色したATP溶液を摂取させることで、満腹(ATP溶液で腹部が膨満)、少量摂取(腹部が着色し部分的に膨張)、未摂取(腹部の着色・膨張なし)の3段階に摂取状態が分類された。(右)ATP溶液の摂取に対する血清の効果。ATP溶液単独の摂取では大半の蚊は満腹になるが、血清を添加した際は、満腹になる個体の割合が減少した(出所:共同プレスリリース)
次に、抑制作用を持つ物質を突き止めるため、成分ごとに血液が解析された。蚊は、血清を単独で与えても摂取しないことから、それは吸血行動に影響を与えないとされていた。しかし、ATP溶液に血清を加えたところ、ATP溶液単独と比べ、腹部が膨満になるまで吸血する蚊の割合が顕著に減少したことから、血清に吸血抑制効果のある物質が含まれていることが判明。血清の詳細な解析が実施されたところ、吸血停止効果を示す成分として、血液凝固の際にまず作られる小さな物質であるFPAが同定されたとする。
-

血清中の吸血停止シグナルの同定。(左)吸血停止効果を示す血清が高速液体クロマトグラフィー法で分析され、血清成分がa、b、cの画分に分けられた。これらの画分をATP溶液に添加したところ、cの画分で顕著に満腹蚊の割合が減少する成分があり、質量分析法の結果、FPAと判明(なおこの解析では、ウサギの血清が用いられた)。(右)フィブリンによる血液凝固過程の模式図。血中にはフィブリノーゲンが溶けており、それがフィブリンとなって血塊を生じる。FPAは血液凝固の最初にフィブリノーゲンから切り出され、血清中に残される(出所:共同プレスリリース)
傷口などを保護する血液塊は、「フィブリン」が大量に集まることでできるが、集まるためには、まず前駆体の「フィブリノーゲン」からFPAが切り出される必要がある。つまりFPAは、切り出されること自体は血液凝固の進行に重要だが、切り出された後は宿主にとって不要となるのである。FPAのアミノ酸配列はほ乳類の間で高度に保存されているため、さまざまな種の宿主から吸血を行う蚊は、血液凝固が起きていることを知るため、その際に発生する「ゴミ」ともいえるFPAを利用していることが考えられるとした。吸血完了時の蚊の体内でFPA量が高くなっていることが確認され、吸血と共にそれが取り込まれていることが明らかにされた。
-

バトロキソビンにより血中FPA量を増加させた際の吸血の比較。バトロキソビン処理をした血液を吸血した蚊では、満腹になる個体の割合が減少した。これらの個体が取り込んだ血中FPA量は、未処理に比べていずれも増加していた。fmol/μlはフェムトモル/マイクロリットルを示す(出所:共同プレスリリース)
最後に、FPAが吸血停止シグナルであることを確かめるため、人工合成ヒトFPAを添加したATP溶液や、その生成阻害剤で処理したマウスの血液が蚊に与えられた。すると、FPAが存在すると蚊は吸血を途中でやめ、存在しないと吸血が促進された。さらに、強制的に作り出す薬剤で血中FPAが増やされたところ、吸血を途中でやめる個体が増加したという。
-

今回の研究から示唆される蚊の吸血停止行動。血中のATPは吸血開始と共に蚊に摂取され、吸血促進シグナルとして作用し続ける。一方FPAは、吸血開始直後は血中濃度が低く、血液凝固反応と共に増加する。蚊は何らかの受容機構によりFPAを「吸血停止シグナル」として感知することで、吸血を始めてからのおおよその時間を認識し、順調に吸血を遂行できなかった際に吸血をやめるような仕組みを備えていると考えられるとした(出所:共同プレスリリース)
これらの結果はFPAが蚊の吸血を「腹八分目」でやめさせる役割をする吸血停止シグナルであることを示すものであり、研究チームでは、蚊には腹部の膨満という物理的な制御機構があるため、FPAの吸血停止シグナルに対し、順調に吸血できなかった際により効果を持つ可能性を考えているとしており、吸血が長時間になると、気付いた宿主に忌避行動を誘発させるため、蚊にとって危険なことから、吸血開始後に血液中に増え始めるFPAの量を感知して、通常よりも長い時間をかけてしまった際に吸血をやめる仕組みを備えていることが考えられるとしている。なお、今後については、蚊がFPAをどのように受容し、吸血を停止するのかを解明し、その機構を活性化する物質を探索することなどにより、人為的に吸血停止を誘導する手法の開発や、蚊が媒介する感染症制御への応用が期待できるとしている。